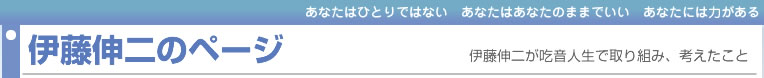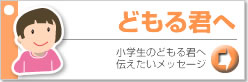子どもと語る、肯定的物語
~吃音を生きて、見えてきたこと~
全難言鹿児島大会 記念講演
2013年7月30日(火)
鹿児島県民交流センター
鹿児島大会報告集
第42回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会
第37回九州地区難聴・言語障害教育研究会
2013年7月29日(月)~31日(水)
鹿児島県文化センター(宝山ホール)・鹿児島県民交流センター
<講演>
日本吃音臨床研究会 伊藤伸二
» はじめに
昨日、鹿児島市内に入り何かとても懐かしい感じがしました。48年前になりますが,私の吃音との旅がここ鹿児島市から始まったような錯覚を覚えました。
私はそれまで、吃音に深く悩みながらも、真剣に考えることも、治す努力もしませんでした。1965年の夏、新聞や雑誌などで「どもりは必ず治る」と宣伝しており、子どもの頃から行きたかった、念願の吃音治療所「東京正生学院」に行きました。そこでまずやらされたのが、上野公園の西郷隆盛の銅像前での演説です。「突然大きな声を張り上げますが,私のどもりの克服にご協力ください」と、西郷さんが見下ろす下で、毎日演説しました。西郷さんが見守り、応援してくれているような気がしました。
私は、48年前の上野公園の西郷隆盛の銅像を出発に、吃音一色の人生を歩み、今、鹿児島市内で西郷隆盛の銅像をあちこちで見たとき、ここにようやくたどり着いたなあという感じがしたのです。
吃音については様々な考え方があります。「吃音に悩み、治したいと考えている子どもに、完全には治らないまでも、少しでも症状を軽減してあげるのが、ことばの教室の教員、言語聴覚士の役割ではないか」との主張があります。一般的な考え方かもしれません。しかし私は、少しでも治そう、軽減しようと考えることでとても辛い人生を歩んできたので、吃音症状に焦点をあて、軽減しようとする取り組みには反対してきました。
午前中の岩元綾さんの講演にとても共感しました。綾さんの、ダウン症を否定しないでほしいとの心の叫びは、私の、どもりを否定しないでほしいと結びつきます。「吃音を治そう、軽減させよう」とすることが、吃音否定につながらないことを願います。
私は今年69歳になりました。吃音と向き合った48年の人生で、いろんな人と出会い、いろんなことを学びました。セルフヘルプグループ、交流分析、論理療法、アサーティヴ・トレーニング、認知行動療法、アドラー心理学などから学んで、考えてきたことを90分の講演で話すのは難しいのですが、当事者研究、ナラティヴ・アプローチ、レジリエンス、リカバリーの概念で整理することで、これまでの取り組みを整理し、今後の吃音の新しい展望が開けるような気がしています。4つの概念について、少し説明します。
当事者研究 生活の中で困っていることを自分一人で、あるいは、周りの人と一緒に研究して、対処法を見いだす。
ナラティヴ・アプローチ
物語・物語るの意味で、人は「ストーリーを生きている」と考え、自分を苦しめてきた語りを、自分が生きやすい語りへと変える。
レジリエンス
困難な状況にあっても、生き残る力、回復力、しなやかに生きる力。
リカバリー
病気や障害が治らなくても、自分が求める生き方を主体的に追求する。
吃音に当てはめると、吃音に振り回されずに自分が幸せに生きる主人公になることです。
吃音を治したい、軽減したいと願うことで今の自分を否定し、悩みを深めた私や、多くの人の経験から、「吃音を治すではなく、吃音と共に生きよう」と主張してきました。その私の考えに、「吃音を治そう、軽減しよう」としても、吃音を否定しているわけではない、吃音を肯定して生きることと、吃音症状の軽減を目指すことは両立する、と主張する人からは、私は偏った意見の持ち主とだと思われているようです。
私のような偏った考え方で、少数派の意見であることを承知の上で、全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会の講演者としてお招き下さったことは大変ありがたく、鹿児島大会の開催事務局の方々、全難言協の関係の方々に、心から感謝いたします。
上野公園の西郷隆盛の銅像の前で、「吃音を治そう」と必死に演説していた青年が、48年の年月を経て、西郷隆盛のふるさと鹿児島市で、どもる子どもを援助することばの教室の先生の全国大会で「吃音を治そうとしないでほしい」と講演をしていること、感慨深いものがあります。
» 3期に分かれる私の体験
3歳から小学2年の秋までは、悩むことも困ることもなく平気でどもっていました。小学2年生の秋、私は当時、元気がよく、成績が良く、クラスの人気者だったので学芸会で主役をさせてもらえると思っていました。ところが、教師の配慮なのか不当な差別なのか、私は学芸会でセリフのある役を外されました。初めて吃音に対するマイナスの意識を持ちました。「どもりは劣った、悪い、恥ずかしいものだ」との吃音否定のレッテルを担任の教師から貼られたことになります。学芸会が始まって学芸会が終わる1ヶ月ほどの間に、私は全く別人になっていました。からかいやいじめが始まり、冬頃には友達が一人もいなくなりました。教師から押しつけられたこの吃音否定の価値観によって、「吃音否定」の物語を語り続けて、私は21歳まで吃音に深く悩みました。
アドラー心理学では、劣等性、劣等感、劣等コンプレックスを区別します。どもるという客観的には劣等性があっても、劣等感をもたない人はいます。私は強い劣等感を持ったがために、劣等性を言い訳にして人生の課題から逃げる、劣等コンプレックスに陥りました。「どもるから私はできない」と、勉強も遊びもクラスの役割からも逃げ、不本意な学童期・思春期を生きました。
この私の経験から、どもることそのものは何の問題もないが、吃音をマイナスに意識し、吃音否定の物語を語ることから問題が起こるのだと確信するようになりました。そこで私は、吃音をこう定義します。
「話しことばの特徴をマイナスのものと意識して初めて言語病理学の研究臨床の領域の吃音になり,症状を治す、軽減する対象になってしまう」
私は吃音さえ治れば、私の未来は開けると、吃音治療矯正所に行きました。東京正生学院の院長は「わーたーしーはー」とゆっくり話すどもらない話し方を教えてくれました。午前中は呼吸・発声練習、午後は毎日100人に、ゆっくり、やわらかく発音して、「郵便局はどこですか。警察はどこですか」と声をかける街頭練習。精神力を鍛えるために、西郷隆盛さんの銅像の前で演説をしました。日常生活でも使うように指導され、喫茶店で、「カーレーラーイースーをーくーだーさーいー」と注文すると、「カカカカカレーライスをくくください」と言っていた時よりも笑われ、からかわれました。
一方、息子の副院長は、アメリカの言語病理学を勉強していた人で、最新の治療法を教えてくれました。どもらないようにしようとすると却って、どもる不安や恐怖が増すからそれよりも、どんどんどもって話そうと、わざと意図的にどもる「随意吃音」や、「軽く、楽にどもる方法」を教えてくれました。1か月、ふたつの方法のバランスをとりながら、一所懸命治す訓練をしましたが、私だけでなくて,300人全員が治りませんでした。治らなかったけれども私にとって良かったのは、人との出会いでした。
私は、どもっていれば人から愛されない、社会人として生きていけないと、将来に大きな不安を持っていましたが、吃音に悩みながらも社会人として教師や営業職など、むしろ話すことの多い仕事に就いている人と出会いました。また、自分で自分が大嫌いだった私を愛してくれた初恋の人と出会えました。この出会いから、私は、どもりが治らなくても、生きていけると思いました。
「必ず治る」と宣伝しながら、300人全員が治らなかったのは、吃音は言語訓練で治る、軽減できるものではないのではないかと、吃音を治すことをあきらめました。もう、吃音を言い訳にした逃げの人生はやめようと思いました。この転換には、私の家がとても貧乏だったのは、今から思えば幸いでした。学費から生活費まで全部自分で稼がなくてはなりません。新聞配達店の住み込みから始まった大学生活ですが、吃音治療のために新聞配達店をやめて1か月寮に入りました。退寮するときに、新聞配達には戻らずに、いろんなアルバイトで生活しようと考えました。その時、ふたつのルールを決めました。
今まではちょっとした困難があるとすぐに「どうせ僕はどもりだから」と言い訳して逃げていたのを、どんなにつらくても1か月は我慢することにしました。また、対人恐怖だった私は、人間関係ができれば、大学の4年間そこでアルバイトを続けてしまうので、常に新しい環境に身を置こうと、どんなに条件がよくても1か月でやめることにしました。このふたつのルールは厳しく、辛い苦しい体験をしました。でも私が、逃げずにアルバイト生活ができたのは、生きるためには働かなくてはならなかったことと、治らないとあきらめて、どもる覚悟ができたことと、どもる仲間がいたからでした。
吃音治療所で知り合った人たちと、1965年の秋、セルフヘルプグループ「言友会」をつくりました。世話役を一切して来なかった私が、自分が創立した会なのでリーダーになりました。一所懸命活動する中で私は、人前で話すこと、人の話をしっかり聞くこと、文章を書くこと、何かを企画して運営することなど、様々な力が身につきました。自分を肯定できず、人の役に立つことがなかった私が、この社会には私の居場所があり、社会は安全で、私もこの社会に貢献できるという、アドラー心理学で言う共同体感覚が身についてきました。自己肯定・他者信頼・他者貢献の感覚が、いい循環になって、私は吃音と共に生きていけると確信できました。
縁あって大阪教育大学で聴覚・言語障害児教育の勉強をし、その後、その大学の教員になりました。私の研究室には全国からどもる人が集まり、これまでの吃音の悩みを語り合うことから、吃音が人生にどんな影響をしたかなど、吃音の人生を語り合いました。その時、ある青年からこんな体験が出されました。
「私は、何かをしなければならないことでも困難を感じると、何かと自分に言い逃れをして逃げ、それでも自分はどもりだから仕方がないと思い込もうとしてきた。そんな自分が恥ずかしい。責任逃れをしていながら、つい自分に甘えてきた。ひょっとすると今まで私は、どもりそのもので苦しみ悩むよりも、どもりを理由に意に反して、してきた行為に対して思い悩んできたことの方がはるかに多かったかもしれない。でもそこから一歩も踏み出せないままに、その悪循環の中にどっぷりと浸っていた。どもりについて真剣に考えてこなかった気がする」
この体験を私たちは徹底的に討議しました。これが今から言えば「当事者研究」の始まりでした。「どもる人の悩みが深いのは、治るかもしれない、もっと軽くなるかもしれないと考え、治ったら、改善したら何々しようと考えることだ」と考え、また、「吃音症状が軽減されれば、さらなる軽減を目指してしまい、完全に治るまで吃音の自分が認められない」と、一切の治す努力はやめようと、「吃音を治す努力の否定」を提起しました。
8年をかけて到達したこの考えは、セルフヘルプグループの活動や、仲間と活動する中でできたことで、仲間や相談機関がない地方の都市で、この考えは受け入れられるかの検証をしないと先に進めないと考え、私は検証の旅に出かけました。
1975年、3か月をかけて、35都道府県で全国吃音巡回相談会を開きました。吃音に深く悩む人だけでなく、「私は労働組合の書記長で、どもっても自分たちの主張はする」「町役場の助役で、答弁の時に私はどもりますと言い始めたら、楽になった」など、どもりながら豊かに生きている人たちがたくさん相談会に参加してくれました。これは大きな驚きでした。私が深刻に悩んできた経験から、「どもる人は、吃音に悩んでいるはずだ」と考えていました。ところが、私の主張が好意的に受け止められただけでなく、吃音と共に豊かに生きてい大勢の人と出会いました。大学の研究室の中だけではとても発見できない、吃音についての私の最大の収穫でした。
» 吃音者宣言へ
私は、担任の教師から「どもりは悪いものだ」とレッテルを貼られて、それを自分のものにしてしまいました。また、社会の中にある「どもりは治る、治さなければならない」の考え方にも、強い影響を受けました。
中学2年生の時に手に入れた『吃音は必ず全治する、吃音の正しい治し方』(浜本正之・文芸社)には、自殺をしたスポーツ選手、金閣寺に放火をした僧などの悲劇の物語が掲載されていました。吃音が治らないと、こんな悲劇が起こるとの圧力を受けました。この本を読んだ人は、「どもりは治さなければならない」と考えるでしょう。当時の新聞や雑誌、学校の先生の話もすべてが「どもりは努力すれば治る、軽減できる。どもっていると幸せになれない」の物語でした。ところが全国巡回相談で会った人たちは、豊かに生きていました。また、私たちのグループの中でも、吃音は軽減されていないのに、豊かに生きる人が育ってきました。これまで吃音否定の物語しかなかった中に、吃音肯定の物語を伝えなければならない。私は体験を文章にすべきだと思いました。
私たちが体験し、考え抜いてきたプロセスを、そして、吃音は、どう治すかではなく、生き方の問題に到達したことを文章にして、「吃音者宣言」文を書きました。
» 世界の吃音治療の歴史
私たちは、吃音と真剣に向き合い、話し合い、考え、研究し、10年をかけてここに到達しました。では、世界の吃音の治療の歴史はどうなっているのでしょうか。
1903年、東京音楽学校(現・東京芸術大学)校長・伊沢修二が「どもらずに、ゆっくり話す」方法を提案しました。1930年代、アメリカではアイオワ学派の人たちが「どもらずに話す」にとらわれることが、どもるかもしれないとの不安や、どもることへの恐怖を高めることになるから、むしろどんどんどもろうと「随意吃音」という、わざと意図的にどもる方法を提案しました。以来、アメリカ言語病理学は、「どもらずに流暢に話す派」と、「楽に流暢にどもる派」が激しく対立しました。
1950年、ウェンデル・ジョンソンは、吃音は症状だけの問題ではなく、聞き手や、本人がどう受け止めるかも含めた問題だと、言語関係図を出しました。これはこれまでどもる症状だけにしか目がいかなかった吃音の歴史上、画期的な提案だったと私は思います。
1970年、ジョゼフ・G・シーアンはさらに突っ込んで、吃音の問題は表面的にみえるどもっている状態は、氷山の水面上のごく一部で、本当の大きな問題は水面下に沈んでいると、氷山説を提案しました。吃音を否定し隠し逃げる行動、吃音は悪いものだとの考え方、不安やみじめな気持ちなどの感情こそが問題だと言いました。
私たちが10年の活動の中で到達した考えと、シーアンの氷山説と言語関係図はぴったり合いました。その後、私たちは氷山の水面下にある問題にアプローチしてきました。交流分析、論理療法、認知行動療法、アサーティヴ・トレーニング、演劇表現、笑いとユーモアなど、精神医学、臨床心理学、社会心理学などいろんな分野から学んできました。それらはどもる覚悟を決め、吃音と共に生きることに役立ちました。
世界最新の吃音治療について、カナダの大学院で学び、カナダの大きな病院で言語聴覚士として働き、アイスターという世界のトップクラスの吃音治療所で治療に携わっていた言語聴覚士が報告して下さいました。大学での3週間の集中プログラムは、英語の詩を40%ぐらいのスピードダウンで読んで,60%、80%、と自由にスピードコントロールできるようにする。会話は、ゆっくり、そっと、「my name わーたーしーのーなーまーえーは」と話す。これらを徹底的に身につけた後、3週間の終了時には自然なゆっくりに変えていく。「ゆっくり話す」がプログラムのすべてです。彼女が担当した青年は、15年間、500万円を使い、どもりを治すためにがんばったが治らずに、今はどもりと共に生きているそうです。この報告には本当に驚きました。1965年、私が東京正生学院で受けた治療法、さらには1903年の伊沢修二の方法と全く同じだからです。効果も限界もその経過も全く同じです。
また、バリー・ギターが提案する統合的アプローチの「ゆっくり、そっと、やわらかく」の流暢性促進技法も、1903年から、ほとんどの日本人が失敗してきたものです。「ゆっくり、そっと、やわらかく」など、子どもたちは、教えてもらわなくても知っています。どもりそうな時にちょっとゆっくり、そっと言ってみたり、ある子どもは、クレヨンしんちゃんの話し方を真似たり、それぞれに工夫をしています。
「ゆっくり言えばいい」は、どもる子ども、どもる人なら、誰でもが知っていても、できないことなのです。この程度の治療法しかない、吃音治療の歴史の100年の年月をどう考えるか。根本的な方向転換をするには、十分すぎる100年です。吃音は、治らない、治せないと認めて、ここから大きく展開していく必要があると思います。いつ転換をするのでしょうか。「今でしょう」と私は言いたいのです。
» 第10回オランダでの世界大会
1986年、私が大会会長となって、京都で第一回の世界大会を開きました。400人が集まった大会の閉会式の時、世界各国の人たちと肩を組んで、「次回、ドイツで会いましょう」と挨拶をした時、私は涙がぼろぼろこぼれました。今まで憎み苦しんできた吃音ですが、その吃音に対して「どもりで良かった」と心の底から思えた瞬間でした。第2回がドイツ、第3回がアメリカ、と続き、10回大会が、今年の6月、オランダで開かれました。「見ない、聞かない、言わないできた、これまでのあらゆる吃音のタブーを打ち破ろう」がテーマでした。私はあまり期待しないで6年ぶりに世界大会に参加したのですが、予想していたものとはかなり違っていました。アメリカ、オーストラリアはともかく、参加の一番多かったヨーロッパのどもる人たちは私たちの考えに近くなっていました。大会会長の挨拶、大会事務局長がスケジュールをアナウンスする時、大勢の前で、こんなにどもる人は久しく聞いたことがないくらいにみんな派手に堂々とどもっていました。
それまでの世界大会が、言語病理学者の基調講演やワークショップが主体だったのに比べて、今回の10回大会は、吃音に苦しみ悩み、吃音の問題を熟知した当事者の声が反映されていました。脳の研究やDFA(聴覚遅延フィードバック)、リッカムプログラムなどの講演・発表が姿を消し、治療をしても治らない現実に向き合って、「吃音治療、軽減、コントロール」が多少は残っているものの、「吃音とともに豊かに生きる」にシフトしているように私には思えました。7つの基調講演のうちの2つが言語病理学者で、5つのどもる当事者の基調講演は、「吃音と共に生きる」を主張するものでした。大会期間中、会う人々はみんな、「ゆっくり、そっと、やわらかく」吃音をコントロールすることなく、自然に堂々とどもっていました。私は6回世界大会に参加していますが、こんな印象は初めてです。
最終日のアメリカの小説家キャサリン・プレストンの基調講演は、びっくりしました。「今日は・・、今日は・・・」何度も同じフレーズを言って次につないでいきます。「ああ、今日は調子が悪い」の声がマイクからもれます。まっすぐ顔を上げて堂々とどもっている姿をみて、爽やかな感じがしました。
特別ゲストのオランダの有名なシンガーソングライターは、「ラジオ、テレビであまり派手にどもるので、視聴者からクレームがつく。だけど私はどもっていく」と言っていました。会場にあふれる、みんなの見事などもりっぷりを耳にして、治療システムが日本よりはるかに整っている欧米でも、吃音は治らず、結局は吃音を肯定して生きざるを得ないことを表しています。参加者の、自然にどもる姿に、私はうれしくなりました。
私は過去4回、世界大会で基調講演をしていますが、今回の「吃音否定から吃音肯定への語り ナラティヴ・アプローチの提案」が一番関心をもたれたようです。日本でも翻訳・出版されている、デヴィッド・ミッチェルという世界的な小説家は、13歳のどもる少年を主人公にした小説を書いています。そのミッチェルさんが、私の基調講演の要約を読んで共感をし、話しかけてくれました。100分ほど、ミッチェルさんと話し合ったのは、非常にうれしい時間でした。ミッチェルさんはこんな話をしてくれました。
「私はずっと私のどもりを敵だと思い、どもりを殺したい、攻撃したい、勝ちたいと戦いました。が、いつでも駄目でした。今度は、どもりが私を攻撃してきました。私は自分の中のものと戦い、内戦し続けてきたのです。戦いに疲れて絶望したとき、自分の考え方を変えなければいけないと思うようになりました。どもりは敵ではなく、いたずらが好きな子どもなんだと思うようになりました。そうすると少しずつ私は話せるようになりました。私の友だちにアルコール依存症の人がいます。彼はアルコールを飲まないことに成功しましたが、今もアルコール依存症者です。私も彼と同じようになりたいと思いました。私のどもりは、私の腎臓のように体の一部として私の中にいます。存在の権利があります。私の遺伝子にあるものを私は攻撃したくない。攻撃するなんておかしい。折り合いをつけて、私は私のどもりに、『いいですよ。はい。あなたが私の中にいても。あなたの存在する権利を認めます。尊敬します』と言いました。そうすると、どもりも、『いいでしょう。あなたの存在の権利を認め、尊敬します』と言ってくれました」
子どもの頃から、ことばを言い換えて生き延びてきたことが、小説家としての力になった、今はどもりに感謝していると話してくれました。
大会期間中、「I Stutter. So, What?! 私はどもる、それがどうした」のバッチをスタッフがつけていました。私のように、どもりを「生き方の問題だ」とは言い切っていないものの、ヨーロッパの人たちは、吃音症状の軽減や流暢性にはあまりこだわっていません。ドイツ、オランダ、イギリス、スウェーデンのリーダーのワークショップでは、効果がない治療法を、どもる人たちが選択しないようにとの宣言文を検討していました。
私の見聞きした範囲ではありますが、6年前に参加したクロアチアの世界大会の時と比べると、何かずいぶん違っているように感じがしました。
ヨーロッパは、日本以上にどもる人に対しては厳しい環境にあります。基調講演した人たちの何人かが、子どもの頃、どもる度に先生から鞭を打たれたとか、いじめられたと語っていました。だから、日本以上に治療にこだわった時代があったのでしょう。ドイツの何人かにインタビューしましたが、1年も2年も吃音を治療する学校に行き、そこで病院の院内学級のように通常学級に通って勉強をした経験を話してくれました。日本のことばの教室とは反対の、吃音治療が中心の学校生活で集中して吃音治療を受けていましたが、みんなかなりどもっています。大会期間中、たくさんのどもることばを耳にして、久しぶりにどもる人の世界大会に来たという感じがしました。
吃音を否定し、「完全に治らなくても、少しでも軽減してあげる」の吃音臨床から、変わる必要があると強く思いました。治らない、治せていないは世界共通でした。治らないものに、治療、改善、軽減の立場をとり、治らなければ私の人生はないと思い詰め、吃音が治ってからの人生を夢見た私たちの失敗を繰り返してほしくないと、大会期間中に強く思いました。しかし、一度吃音をマイナスに考えると、そこから「どもっても、まあいいか」と思えるようには、なかなかなりません。私は21歳であきらめました。これはとても早かったと、後で思いました。3人の体験を紹介します。
» ナラティヴから見た、3人の体験
スキャットマン・ジョンは、私と仲の良かった世界的ミュージシャンです。彼は吃音の苦しみ悩みから逃れるために、麻薬依存、アルコール依存になり、荒んだ生活を送りました。アメリカでは生活ができなくなり、ヨーロッパに渡って、ホテルでピアノを弾いていた時、「その曲は面白い。CDに出そう」と話が出ます。「もし、ヒットしたら、インタビューを受ける。すると、今まで隠してきた吃音が公になる」。彼は最大の窮地に陥ります。妻のジュデイに「CDを出すの、やめる」と言い出します。妻は、「52歳にもなって、バレるのが嫌なら、自分で公表したら」と言われて、覚悟を決めて、曲の詩に吃音を入れ、CDのジャケットに吃音について書きました。吃音の症状が軽減されたわけではなく、ただ吃音を認めたことで、彼の人生が大きく変わりました。
陽気で明るいミュージシャンとして「スキャットマン・ワールド」は日本でも120万枚の大ヒットとなり、プッチン・プリンの宣伝にも出ていました。国際吃音連盟の役員の私に会いたいと、大阪で会う約束をしていたのが、手違いで会えなかったのは残念でした。吃音治療ではなくて、吃音を肯定して生きるために、いろんな活動を一緒にしようと約束していたのですが、57歳でがんで亡くなりました。彼が吃音を肯定して生きたのはたった5年でした。それまでの苦難に満ちた人生を思うと、くやしい思いがいっぱいです。
チャールズ・ヴァン・ライパーは、私が敬愛する言語病理学者ですが、どもりであれば就職ができないと、30歳の時、ろう者を装って農場に就職し、話さないで黙々とじゃがいも堀りをしていました。その生活に絶望して、山を下りる時に老人と会います。老人に「どこへ行くのか」と尋ねられた時に、ひどくどもりました。すると老人はその姿を見てげらげら笑うんです。ライパーが怒って抗議すると、老人は、「私も、若い頃は君のように力んでどもっていたが、今はそんな元気はないよ」と話しました。この出会いで、吃音を治さなくても、老人のようにどもればいいのだと考え、アイオワ州立大学で吃音について学び、世界一の吃音言語病理学者になり、多くの弟子を育てました。
晩年は「私は私を含めて数千人のどもる人の吃音を治せなかった。慢性病の人々が、慢性病を治せないものとして受け入れるように、吃音を受け入れよう」と言い続けていました。大学でブリンゲルソンから、随意吃音を中心としたセラピーを浮けた経験から、どもり方は変えられるとの信念を持っていたようです。吃音を受け入れるだけでは十分ではない、どもり方を変えようとも言っていました。ここが、ヴァン・ライパーと私との大きな違いです。ライパーは、セラピーを受けてどもり方が変わった。私の場合は、治すことをあきらめ、生活の中でどもっていくことで、自然に変わっていった。
ライパーは、私の敬愛する言語病理学者ではありますが、弟子のバリー・ギターの統合的アプローチ「ゆっくり、そっと、やわらかく」につながったのは残念です。ライパーと同年代に生きたら、もっと議論がしたかったと思います。
アカデミー賞映画、「英国王のスピーチ」、ご覧になった方は多いと思います。ジョージ6世は、5年間、必死で吃音治療を受けますが、治りも改善もしません。開戦スピーチの40分前、言語聴覚士の力を借りて、必死で声を出そうとするけれどもうまくいかない。最後に彼は、「結果がどうであれ、君が僕にこれまで関わってくれたことに感謝する」とどもる覚悟を決めてスピーチに臨みます。どもる時はどもればいい。国王がどもってしゃべっても、国民は聞く権利と義務がある。国王の私はいかにどもっても、国民に伝える権利と義務があるとのどもる覚悟ができたのは、私から見れば、ナラティヴ・アプローチになっていたからだと思います。
「俺はもうだめだ。俺なんて国王じゃない」と、泣いて妻のエリザベスにすがる姿が印象的ですが、エリザベスは、「あなたの吃音が素敵だったから、結婚したのよ」と言い、後の首相チャーチルは、「あなたこそ、国王にふさわしい」と言います。言語聴覚士も、「誠実なあなたこそ国王になるべきだ」と、あまりに言い過ぎて、喧嘩するぐらいでした。父国王も「誰よりも根性がある。お前が国王になれ」と言います。みんなの「吃音肯定の語り」が少しずつ体に染みて、「どもる時はどもればいいんだ」と、どもる覚悟ができたのだろうと私は思います。
3人の経験を話しました。どもりの症状を治す、軽減するのではなくて、「どもってもまあいいか」と肯定的な物語に変わった時、人は変わるのだと私は思います。
» 吃音を治したいとのニーズ
「吃音を治したい、軽減したいが、子どもや親のニーズだ」と言われます。私は、吃音を治したいと言う子どもや親に、「なんで治したいの」と聞きます。すると「どもっていたら、友だちはできないし、学校生活の中で苦労するし、将来就職で苦戦し、結婚ができるか心配だ」と言います。確かに、子どもはいろいろと苦労しています。しかし、その苦労は自分が真剣に吃音に向き合えば、自分なりに解決できる問題です。治したいとの親のニーズの奥には、「子どもに幸せになってほしい」の思いがあります。それをどもりが阻むと思うから、治したいと思うのであって、治すことにこだわらなければ、学校生活の中での苦労、苦戦は、ことばの教室の先生やどもる子どもの親、子ども本人が考えて解決していける問題だと思います。
» 治したいと思わない
吃音親子サマーキャンプは、24年続いています。キャンプの様子がTBSの「ニュースバード」で流れました。中学1年生の女の子の一人が、「私はどもりを治したいなんて思わない。治らない方がいいです」と言い、もう一人の女の子は「どもりでよかったなあと思いました」と発言していました。静岡のキャンプで、「どもりを治したい人?」と言ったとき、手を挙げなかった子に「どうして治したいと思わないの?」と聞くと、「どもるのが僕だから。学校で、何回も発表するし、治そうなんて全然思わない」と言いました。 これらのことばは、48年前の私には想像もできません。当時は、治さなければ、治るはずだの情報ばかりで、こんなことばは出てこなかっただろうと思います。
» 吃音は自然に変わる
吃音は訓練をしなくても自然に変わるものだと私は思っています。吃音は、多少吃音が軽減されたり、コントロールができても完全には治らないので、アナウンサーの小倉智昭さんも「仕事ではどもらなくなったが、普段の生活ではどもる。私は吃音キャスターだ」と言います。女優の木の実ナナさんも、フーテンの寅さんの映画で、「お兄ちゃん」のセリフが言えなくて、2日間、撮影がストップした体験を語ります。職業としてことばを鍛えてきた人でも、どもる時はどもります。
一方で、どもる人の本当の悩みは、どもれない悩みだということは多くの人はあまり気づいていません。吃音症状が軽減されると、余計に「どもりたくない」の思いが強まって、吃音を隠したい思いが膨らみ、悩みを深める例はたくさんあります。教室で教えている時は、あまりどもらなくなった教師が、卒業式で子どもの名前をが言えずに悩みます。また、課長に昇任して、大勢の前での司会で、「起立、礼、着席」の短いことばが言えない。普段はどもらないので、ある場面でどもりたくないと悩むどもる人たちはとても多いのです。その人に「ゆっくり、そっと、やわらかく」言う練習をしても、役に立ちません。普段はちゃんと話している人たちにどんな訓練が必要なのかと私は思います。どこまで、軽減されれば、その人が満足するのかの線引きはありません。軽減すればするほど、あと少し、あと少しと完全を求め、際限がありません。そして、「いつか、完全に治れば」の思いが膨らみ、吃音と共に生きる覚悟ができません。「完全に治らなくても、軽減する」は、とても危険がはらんでいることは、知っておいてほしいことです。
ことばは生活の中で育つものです。吃音も、ことばに関しては、できるだけ小さな援助にとどめてほしいと考えています。ことばの教室で「ゆっくり、そっと、やわらかく」の話し方は教えないでほしいと思います。生活の中で、子どもたちが自然にそれを使っているのと、意図的に教えられて訓練するのとは違います。
どもらないで話すことにこだわる、オーストラリアの親友に、今年も、オランダの世界大会で会いましたが、彼はゆっくりとどもらないように話します。どもりませんが、とても不自然です。彼とは、人間として話している気がしません。
先日、岡山の教会の牧師さんから電話がありました。再三相談にのっている人です。彼はどもらないように一生懸命コントロールしてきたためか、周りの人から「あなたと語り合っている気がしない」と言われます。私と出会って、吃音を認めて生きたいけれども、身についたコントロールを解除するのがとても難しいと言います。ゆっくりと、抑揚のない話し方が、牧師として、信者と話すとき、人間的な会話ができないと悩んでいます
その子の幸せを願って、将来役に立つと思って、吃音のコントロール法を教えることが、実はその人のことばの個性を奪う可能性があります。すべてがそうだとは言いません。コントロールできて幸せになる人も、中にはいるかもしれない。でも、すべてがそうではないということは知っておいてほしいと思います。
どもる人でなければ絶対にしない、「おーはーよーごーざーいーまーすー」など、1965年に受けた特別の訓練、とても嫌でした。こんな訓練はしたくないと思いました。そういう訓練が、今またことばの教室で行われているとすると、私は胸が締めつけられるような気がします。そういう言語訓練ではなくて、日本語をしゃべる人であれば誰もが必要な日本語の発音・発声の練習の小さな援助にとどめてほしい。私たちは、知らず知らずのうちに母国語を身につけてきました。誰かから特別に訓練をされたわけではありません。人は生活の中で、自分の性格などいろんな条件の中で、自分のことばを育てていきます。
私も、吃音を認めた21歳から、自分のことばを育ててきました。女優の木の実ナナさんも小倉智昭さんも、自分の仕事を通して、自分のことばを身につけてきました。人それぞれが、それぞれの生活の中で、自分のことばを身につけていくのが、人間の本来の営みなのです。その子がどもるからといって、「ゆっくり、そっと、やわらかく」の訓練を、第三者がして、コンピューターのような人工のことばを育てるのは、私は、子どもに大変失礼だと思います。吃音は、放っておいても、生活の中で話すことから逃げない生活を続けていれば、自然に変わります。たくさんのどもる子どもたちと出会い、たくさんのどもる人たちと出会って、本当にそう思います。
そのような訓練よりも、その子がいかに困難な状況の中でも生き延びる「レジリエンス」を育てることが、何よりも必要なのではないかと思います。
» レジリエンス
アメリカの心理学者、ウェルナーは、貧困、暴力など劣悪な環境で育った人を長年にわたって調査研究しました。すべての人が貧困や犯罪など大変な生活を送っているだろうと思っていたが、3分の1の人が能力のある信頼できる成人になっていたと報告しました。この人たちのことを「心的外傷となる可能性のあった苦難から新しい力で生き残る能力、回復力がある」として、「レジリエンス」があると言いました。
2011年3月11日、あの東日本大震災で生き抜いている子どもたちの中にも、レジリエンスがあると私は思います。スクールカウンセラーとして被災地に入った臨床心理士の国重浩一さんと知り合いました。国重さんは、スクールカウンセラーとして鹿児島のいくつかの学校で勤務した人で、今は、オーストラリアにいます。国重さんは、「世間は、すぐに、トラウマ、心的外傷後ストレス障害とか言うけれど、世間が考えるほどには、PTSDに陥る子どもたちは多くはない。自然災害は誰の責任でもない、仕方がないことだと受け止めることができる」と話して下さいました。
どもる子どもたちを見ていると、確かに生活の中で苦労はあるけれども、それなりに立派に生き延びているなあと、私は思います。
3・11の大震災で、私は多くのことを学びました。そのひとつが、教育の持つ大きな力です。被災地では、「釜石の奇跡」と呼ばれる「防災教育」がありました。群馬大学の片田敏孝教授から、津波が起こったら、てんでんばらばらに逃げるんだという「津波てんでんこ」の徹底した防災教育を受けた釜石市の子どもたちは、学校の管理下になかった5人の子どもをのぞいて、市内の小・中学生のおよそ3000人全員が無事に生き延びました。その子どもたちがインタビューを受けて、「私たちは日頃教えられたことを実践したに過ぎない。釜石の奇跡なんかではなくて、これは僕たちの実績だ」と話していました。 一方、防災教育が徹底されなかった石巻市の大川小学校では、教職員と共に大勢の子どもが亡くなりました。なぜ子どもが命を落とさなければならなかったのか、辛い検証が始まっています。私はここに、教育の力、教育の大切さを考えます。吃音を否定することで、どのような問題が起こるのか、どんなマイナスの影響を与えるのか、私たち、マイナスの影響を受けた当事者の声を、私は伝えていきたいと思います。それを私は吃音の予防教育だと考えています。吃音になることは予防できないけれど、大きなマイナスの影響を受けないようには予防できるのです。
私は、どもりが治らないと、軽減されないと、こんな悲劇が起こるとする、吃音否定の物語ではなく、どもりと共に生きていけるという吃音肯定の物語を語っていきたいのです。どもる子どもには脆弱性があり、ストレスに弱いから、今のうちにどもりを治してあげないといけない、軽減してあげるという「脆弱性モデル」ではなくて、この子はこの子なりに力を持って生きていけるという「レジリエンスモデル」で、吃音を考えていく必要があると思います。それには、吃音を否定しないことが何よりも大切なことになります。
終わりに近づいていますが、私は、吃音サマーキャンプで会った一人の少女のことをお話しします。宮城県女川町から4人家族で参加しました。私たちのキャンプは、90分と120分の話し合い、90分の作文と、徹底的に吃音と向き合うキャンプです。阿部莉菜さんは、5年生までは順調に来ましたが、6年生になって何人かの男の子からひどいからかい、いじめを受け、2週間も経たないうちに、学校へ行けなくなりました。不登校のままキャンプに参加しました。彼女の思いを知っているので、私は6年生の話し合いのグループの担当をしました。第1回目の話し合いのときの彼女は、顔がこわばって、緊張しながらその場にいました。みんなが少しずつ自分の吃音について話し合うのを聞いて安心したのか、手を挙げて「ちょっと私の話を聞いて下さい」と話し始めました。
「私、今、学校に行ってないんです」涙をぼろぼろこぼしながら、学校へ行きたいのに行けない悔しさを話しました。すると、キャンプに複数回参加している子どもたちは、話し合うことに慣れているので、共感的に「ああそうか、それはつらいねえ」のような聞き方はせず、「その男の子は、どんな子?」「その時、先生はどうしていたの?」「からかわれた時に莉菜ちゃんは何を考えたの?」と、どんどん質問をします。質問を受けて、彼女は、学校の様子などいろんな思いを語りました。「そんなしょうもない男の子のために、大好きな学校へ行けないのは損やんか」などの発言がありました。そして、1日目が終わり、一夜明けて、2日目の朝、作文教室でこんな作文を書きました。
私は学校でしゃべることが、とっても怖かったです。どうしてかというと、どもるから。しゃべっていてどもってしまうと、みんなの視線がとても気になります。そして、なんだか「早くしてよ」と言われそうで、とってもとっても怖かったです。でも、サマーキャンプはちがいました。今年初めてサマーキャンプに出てみて、みんな私と同じでどもっているんだ。私はひとりじゃないんだと思いました。そして、同じ学年の人との話し合いがありました。その時思ったのは、みんな前向きにがんばってるんだ。なのに私はどもりのことを引きずっていた。全然前向きに考えていなかった。その時私は思いました。どもりを私の特徴にしちゃえばいいんだ。それと同じ時、キャンプに行く前にお父さんに言われたことを思い出しました。「どもりも立派ないい大人になるための肥料なんだ、肥やしなんだ」と。そうだ、どもりは私にとって大事なものなんだ。そういうことを昨日思いました。そして今日朝起きたとき、気持ちが楽でした。まだサマーキャンプは始まったばかりですが、とっても学校などでしゃべれる自信がつきました。
学校にはまだ、いじめる子がいます。クラスの担任の先生が、いじめている子どもに何の指導もしていません。また、同じことが起こるかも知れない、何も変わっていない安全とはいえない環境なのに、キャンプが終わった後すぐに、彼女は学校へ行き始めました。
ナラティヴ・アプローチは、本人の語る否定的な物語の中に、語り切れていない「ユニークな結果」を引き出す質問をします。そして、それを肯定的物語に変えるお手伝いをします。子どもたちの発言の中に、こんなものがありました。「莉菜ちゃんは学校へ行きたいから、このキャンプに来たんだよね。遠いところからキャンプに来た。すごいねえ」。キャンプに参加している子どもたちは、ナラティヴ・アプローチのことばさえ知りません。それなのに、こういう発言をする子どもたちの語る力を尊敬します。
莉菜さんは中学1年生、2年生とキャンプに参加し、将来は福祉の仕事に就きたいとの夢を語っていました。中学3年生の時、クラブの試合と重なって、キャンプに参加できませんでした。そして、2011年3月11日、大津波に巻き込まれて、お母さんと共に彼女は亡くなりました。私は、この5月の連休に彼女が幸せに生きた宮城県女川町に行ってきました。瓦礫が片付いただけで、まだ一面焼け野原のようです。こんな遠いところから、彼女は滋賀県のキャンプに家族で来ていたんだなあと思いました。彼女の生きていた場所で冥福を祈ってきました。阿部莉菜さんのことは決して忘れないでおこうと、その後の講演活動で話しています。
» 当事者研究
吃音症状の軽減が、自信になり、幸せにつながる子どももいるかもしれません。けれども、私がたくさん出会った子どもたち、48年間の吃音人生の中で会った数千人の人たちは、どもりを治そう、軽減したいと思い詰めて悩んできました。そして「まあ、どもってもいいか」と吃音を肯定して生きることで人生が変わってきました。私は子どもと共に「吃音否定の物語」から「吃音肯定の物語」に変えていくことが、教育の現場であることばの教室でできる最大のことではないかと思います。
吃音を治す、軽減するは、医療の発想です。私たちは、学校生活の中で苦戦をする子どもたちと、苦戦をしている課題に「当事者研究」の考え方を使って研究を進めます。子どもたちは「当事者研究」と言うと「研究? 研究するの?」と目を輝かせて自分の困っていること、困難に思っていることを研究しようとします。自分の課題のすべてを専門家に丸投げするのではなく、自分自身が主人公になって、自分の課題に取り組むのです。
» 子どもと何を学ぶか
子どもと吃音否定から肯定的な物語を語るために、何が必要かを考えます。
私たちが苦しんだのは、吃音についての正しい情報がなかったからです。どもりは必ず治るとの情報しかなく、治療法があり、治ると思っていました。ところが100年経っても、ゆっくり言うことしかない。孫がどもった時に、おじいちゃんおばあちゃんでも、「ちょっとゆっくり、そっと言ってみたらどう?」と言うでしょう。この程度のことが治療法だとの現実を、子どもたちに伝えるべきだと思います。そして、子どもが吃音と共に生きていくのに役立つ知識を学びます。私が、東京正生学院で「まあどもってもいいか」とあきらめがついたのは、吃音に悩んでいるから東京正生学院に来ているけれど、帰ったら、学校の教師や会社の営業職など、話すことの多い仕事に就き、どもりながら生きている人と出会えたからです。当時大学生だった私は、どもりながらでも社会人として生きていけるんだと安心しました。
ことばの教室の教師仲間と書いた『親、教師、言語聴覚士が使える、吃音ワークブック』(解放出版社)には、どもる人がどんな仕事に就いているかのワークがあります。子どもたちは、どもる人がこれだけ多くの仕事に就いていると知ってびっくりします。どもる人がどんな人生を送っているか、知ってほしい。吃音と共に豊かに生きている先輩と出会ってほしい。「どもりを治したい、やっぱりどもっているとだめだよね」という、今吃音に悩んでいる先輩ではなく、どもりながら苦労しながら生きてきた先輩と出会ってほしい。
吃音親子サマーキャンプには、複数回参加している人と初めて参加する新しい人が混じり合っています。子どもたちが変わっていくのは、先輩の子どもたちが、自分が学校で苦戦しながらも、豊かに生きていることを語るからです。そして、そのことを聞いて学んでいくからです。また、肯定的な物語を語るために、自分のことを語る力を育てたい。対話する力がどんどん落ちていると言われています。ちょっと批判されると、すぐ相手を攻撃する、嫌な日本になってきています。人と人とが違うのが当たり前で、それを乗り越えて対話していく力を身につけてほしい。
私が一人でどもりに苦しんでいた時、役に立ったのは読書と映画です。一人ぼっちだったから、時間がたくさんあったので、たくさんの児童文学や小説を読みました。中学生では、映画ばかり見ていました。私は読書や映画から、いろいろな苦しみがある中で、人は生きている、他人の人生を学びました。吃音を治すためではなく、生活の中で力のあることばを育て、日本語の発音・発声についても学んでほしい。私たちは、詩や演劇の手法を使って自己表現を学んでいます。
私は、からかいや真似をされることで、みんなは話を聞いてくれないと、他人を信じられずに悩みました。学校のみんなは自分のことを分かってくれない、敵だと思うと、いくら自分がどもっても大丈夫と思っても、音読や発表はできません。
アドラー心理学で言う共同体感覚は、「私は私のことが好きだ」という自己肯定、「人々は仲間で、信頼できる。中にはからかったり真似する子もいるけれども、基本的には先生も友だちも、私の仲間だ」と思える他者信頼、「私は人の役に立っている能力がある」とする他者貢献の3つから成り立ちます。私は、セルフヘルプグループの活動の中で、自己肯定、他者信頼、他者貢献を取り戻しました。今まで人の役に立ってこなかった私が、創立した会のリーダーになりました。すると、「伊藤さん、今度の行事、良かったね」と会員が喜んでくれた。自分も人の役に立っていると思えて初めて、他者貢献が、自己肯定になり、他者信頼へと循環していきました。自己肯定感だけを育てようと思っても無理です。他者貢献、他者信頼があって初めて実現します。共同体感覚を育成するために、学校生活の中で、クラスの中で、その子がどんな役割を持つのか、どういう生活をするのかを通常学級の先生とことばの教室の先生と一緒に考えてほしい。そして、劣等コンプレックスに陥らないようにしてほしい。
人が生きていく上で、劣等感があるのは当たり前で、劣等感がない方がおかしい。劣等感があったとしても、そのために逃げることはやめたい。「どもりだから~できない」と、課題から逃げる人生は、今から思うととても残念です。劣等感があっても、そのために、劣等コンプレックスに陥らないようにする。そのためにも、共同体感覚の育成が必要だと思います。
» 氷山の水面下への取り組み
アメリカ言語病理学は、氷山の上の部分だけに取り組んでいるように私には思えます。吃音肯定、吃音受容のことばは使うけれども、実際の取り組みは、「ゆっくり、そっと、やわらかく」の流暢性促進技法のアプローチです。吃音氷山説の上の部分の吃音は、日常生活を大切に、人を大切に、自分を大切に生きていけば、自然に変わります。自然に変わるのだから、軽減する方だけでなく、前よりどもるようになる子どももいます。
小学4年生からサマーキャンプに参加し、あまりどもらないままに高校3年生で卒業した子が、大学2年生になってかなりどもるようになり、周りが心配しました。でも、彼女は、どもる覚悟、自己概念がしっかりしていたために、接客のアルバイトをしながら、大学を卒業し、薬剤師として、大きな病院で働いています。吃音も3年ほどで元の状態に戻りました。
アメリカ言語病理学は、放っておいても変わる吃音症状を「治す、軽減する」ことに取り組むものの、放っておいたら変わらない氷山の下の部分の、行動・思考・感情への取り組みをしません。私たちは、吃音を否定することから起こる、氷山の水面下の課題にアプローチするために、認知行動療法、アサーティヴ・トレーニング、論理療法など、たくさんのことを学んでいます。吃音に絡めたそれらの本を出版しています。興味がもてたら、お読み下さい。
» おわりに
オランダの世界大会で、たくさんのどもる人たちのことばを聞いた時、私は教育評論家の芹沢俊介さんが、私の『新・吃音者宣言』(芳賀書店)を、「どもる言語を話す少数者という自覚は実に新鮮である」と紹介して下さったのを思い出しました。その本の中で、こんな文章を書いていました。それを最後にお伝えして、講演を終わります。
「治らないから受け入れるという消極的なものではなく、いつまでも治ることにこだわると損だという戦略的なものでもない。どもらない人に一歩でも近づこうとするのではなく、私たちはどもる言語を話す少数者として、どもりそのものを磨き、どもりの文化を作ってもいいのではないか。どもるという自覚を持ち、自らの文化を持てた時、どもらない人と対等に向き合い、つながっていけるのではないか」
私の大切なことばの教室の教師の仲間たちと一緒に作った『吃音ワークブック』には、氷山の水面下のへのアプローチのワークが載っています。NOP法人全国ことばを育む会のパンフレット『吃音とともに豊かに生きる』には、48年間の私の人生が凝縮されて書かれています。48年間の人生を、90分の講演で語るのは難しいことです。私の話に少しでも共感する部分がありましたら、是非お読み下さい。いつも本の宣伝で終わって、恐縮ですが、ちょうど時間になりました。ご静聴、ありがとうございました。