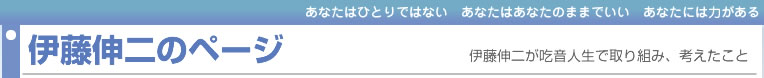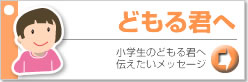どもる子どもと向き合い、子どもと語る
~当事者研究、ナラティヴ・アプローチ、レジリエンス~
北海道言語障害児教育研究大会 渡島・函館大会 記念講演
2014年9月12日(金)
ロワジールホテル函館
第47回北海道言語障害児教育研究大会 渡島・函館大会
2014年9月12日(金)~13日(土)
ロワジールホテル函館・函館市立中部小学校
日本吃音臨床研究会 伊藤伸二
» はじめに
講演前に、今、話さないと忘れそうなふたつの話をします。
「私は、社会不安障害と診断され、教師を続けるには常に安定していなければと、ずっと薬を飲んできました。伊藤さんの話を聞いて、多少の不安があるままの私でいいのだと思い、薬をやめて、今2ヶ月になりますが、薬を手放せてよかったです」
7月の札幌市での「言語障害臨床研修会・吃音」に参加した人が、会場で話しかけて下さいました。僕の吃音の話を、自分の人生に置き換えて受け止めて下さったこと、涙がにじむ、うれしい話でした。
会場の書籍コーナーに東田直樹さんの『自閉症の僕が飛びはねる理由』などの本が並んでいます。東田さんが世界的に注目されるようになったきっかけは、イギリスの著名な作家、デイビット・ミッチェルさんが、その本を翻訳し、海外で出版されたからだと、NHKの番組で知りました。デイビット・ミッチェルさんとは、昨年6月、オランダで開かれた、第10回世界大会で親しくなりました。僕の基調講演の要約を読んで共感し、話しかけて下さいました。長い時間話した中で、「私は、今までどもりと戦い、戦いに疲れて絶望して、自分の中のどもりを認めて、その後の人生が変わった。伊藤さんとまったく同じ考えです」が、とても心に残りました。
では、本題に入ります。北海道は思い出深いところです。大学4年生の時、3ヶ月かけて日本一周をしました。その旅の中で、函館の夜景を見た時、涙がぼろぼろこぼれました。風景を見て涙を流すのは最初で最後の経験です。なぜ、函館の夜景に涙を流したのか、函館に来てずっと考えていました。僕は小学校の2年生から苦しい学童期、思春期を送りました。僕を理解するひとりの教師もなく、友だちもなく、勉強もせず、夜はいつも自転車でさまよい、夜の浜辺に打ち寄せる波を見ていました。函館の夜景が、苦しかった頃を思い出させ、今の幸せを、宝石のようにちりばめられた夜景に見たのだと思います。
僕は、吃音を否定し、「吃音が治らないと、僕の人生はない」と思いつめ、「治る」ことばかりを考えて生きてきました。21才の夏休み、1か月、吃音治療所で必死に治す努力をしましたが、治らず、治すことをあきらめ、「吃音と共に生きていこう」と決意しました。「どもっても、まあいいか」と、吃音を認めることで僕の人生は変わりました。苦しかった時代と、今の違いは「吃音を否定しているか、肯定しているか」だけです。
この僕の経験や、「吃音否定し、吃音との戦いに敗れた」たくさんの人の人生を聞く中で、どもる人の苦しみの根源に、「吃音否定」があると確信するようになりました。「吃音を否定しないでほしい」が、僕の話したいことのすべてです。だから、吃音を否定する動きには敏感に反応し、それに対して僕はずっと戦ってきました。
アメリカ言語病理学が、「吃音治療・改善」にいつまでもこだわる中で、日本のことばの教室のみなさんは、「吃音を治す」にとらわれていません。リッカムプログラムや統合的アプローチなどが紹介されると、言語訓練しなければならないのかと
不安になるかもしれませんが、これまでの指導にどうか自信をもって下さい。どもる子どもに、「あなたはあなたのままでいい。あなたは一人ではない。あなたには力がある」と僕は言ってきましたが、ことばの教室のみなさんが、同じメッセージを、僕の話から受け取っていただければうれしいです。
7月、札幌市で開かれた「言語障害臨床研修会・吃音」に僕が招かれたのは、昨年7月、札幌のどもる看護師の青年が自殺したことを受けてのことだと思います。今後どもる子どもの教育をどう考えるかを話したのですが、90名近い参加者の皆さんから、これまでの自分の取り組みが間違っていなかったと確認できてよかった、新しい視点が得られたなどの感想をいただきました。その感想に勇気を得て、今回も僕の考えを思い切って話します。
「吃音の理解がない社会の中で、学校生活を送ったり、仕事をしたりするとき、吃音は大きな障害になる。完全には治らないまでも、少しでも、吃音症状を軽減し、改善してあげることが必要だ」
あのようなできごとが起こると、このような意見が出てきます。この、どもる人、どもる子どもの幸せを考えているかのような考え方は、役に立たないどころか、弊害があると僕は考えています。「改善してあげる」は、治療法があり、訓練や本人の努力で症状の軽減、改善ができる場合に言えることです。「ゆっくり、そっと、やわらかく」の1903年に始まった治療法は、ほとんどの人が失敗してきたものです。これほど医学、科学が進歩した時代でも、「ゆっくり話す」こと以外、吃音の治療法はありません。治療法がない吃音を否定し、少しでも改善しなければと考えることは、どもる現在の自分を否定し、悩みを深めます。これは、僕を含め、世界中のどもる人が散々経験してきたことです。
自殺というできごとがあったからこそ、「吃音を改善する」ではなく、吃音と向き合い、吃音哲学を学び、「吃音とのつきあい方」を学ぶ必要があります。理解がない社会であっても、サバイバルして生き抜く力を育てることが必要です。まず、吃音への理解が全くない職場でサバイバルしている若い消防士の話をします。
消防士の体験
彼は、大学生4年生の時、「僕は消防士になりたいが、僕のようにどもる人間が、緊急の連絡や報告が多い消防士になってもいいのか」と相談してきました。
「どもることでの苦労はどんな仕事に就いても出てくる。自分のしたい仕事で苦労したほうがいい。何年かかっても夢を追求してほしい」と僕は薦めました。彼は、面接でかなりどもりましたが、東京消防庁に合格しました。しかし、消防学校は予想以上に過酷な場所でした。担当教官の控え室に入るときには「何年度、何組の誰々、入ります」と言わなければならないが、自分の名前が言えない。練習を何度もさせられ、「インターネットには、どもりは治せるとある。消防学校の間に、どもりを治せ」と言われました。さらに、「お前のようにどもっていて、東京都民の命が守れるのか」とも言われました。とてもつらかったと思います。僕たちは彼の話を徹底的に聞き、支えました。そして、彼は苦労しつつも、消防学校の1年間を終える日、こんなメールをくれました。
-伊藤さん、おかげで明日消防学校を卒業することになりました。10月からは消防学校学生兼職員として消防署に勤めていたのですが、10月からの半年間は、正直、消防学校とは違った意味のつらさがありました。電話が鳴ると若手が積極的に出るのが当たり前なのですが、電話の第一声がどうしても出ません。でも、それが仕事なので甘えることはしていません。自分なりに工夫して多少第一声が出やすい方法を見つけるのですが、それに慣れてきた頃にはその方法でもことばが出なくなります。
そしてまた新しく何か方法を考え、それでも出なくなる。そのいたちごっこで大変でした。今現在吃音が激しい時期で今日は一人ずつ名前を呼ばれて返事をするのもことばが出ませんでした。
周りから特にとがめられることはないのですが、自分自身がこのことを全く気にしない、というメンタルはまだないようです。しかし、消防活動技術の試験では褒められることもありました。正直電話応対やコミュニケーションの面で人より時間がかかり、聞き取りづらかったり、迷惑をかけたりすることが多々あると思いますが、これなら負けない、というものを見つけてがんばっていきたいと思います。4月からは本庁で勤めることになりました。また環境も変わり、吃音の調子も変化していき、しんどいことも増えていくと思いますが、がんばります。とりあえず、今は明日の卒業式で「はい」といえるのかどうかが不安です。また伊藤さんや大阪の皆さんに力を借りることがあると思いますが、その際はよろしくお願いします。- (1)
なぜ彼は、1年間の厳しい消防学校生活に耐え、今消防士として働くことができているのか。ここにどもる子どもの指導に生かせるポイントがあります。彼は、小学4年生から吃音親子サマーキャンプに参加し、吃音と向き合い、吃音について語り合い、学習してきました。そして、彼には、困ったとき、いつでも相談し、一緒に考えてくれる両親や、どもる大人がいました。困難な状況でもしなやかに生き延びる、回復力である、レジリエンスが彼に育っていたのです。「吃音を生きる力」を育てることの大切さを物語っていると思います。生きる力、レジリエンスを育てるのが、ことばの教室の役割だと僕は考えています。
» 吃音の問題とは何か
吃音は治らない、治せない
「完全には治らないまでも、少しでも吃音の症状を軽減してあげるのが、ことばの教室の役割ではないか」との主張が根強くあります。しかし、原因がわかっていない吃音は、薬や手術の治療法はありません。軽減してあげるのが役割だと言われても困ります。ある治療法で「治った、軽減した」との論文が出されても、それは訓練室の中だけのことで、その成果を持続させ、日常生活に生かせないのは、100年以上、ずっと変わらず続いている世界の吃音の治療の限界で、常識です。
世界最新の吃音治療について、カナダの大学院で学び、カナダの大きな病院で言語聴覚士として働き、アイスターという世界のトップクラスの吃音治療所で吃音治療に携わっていた言語聴覚士の池上久美子さんが実情を報告してくれました。(2)
「ゆっくり話す」のスピードコントロールが、治療法のプログラムのすべてで、4週間の治療で効果があったとする人も、100%が再発するそうです。彼女が担当した青年は、アイスターやアメリカの著名な大学教授に治療を受け続け、15年間、500万円を使ったが治らず、今は、どもる事実を認めて生きています。
池上さんが、カナダの大学院で言語病理学を学んだときは、吃音治療の話ばかりで、「吃音と共に生きる」発想はまったくないどころか、「吃音受容」もことばだけで、1970年に出された「吃音氷山説」は、説明すらされなかったそうです。世界トップクラスの北米の最新の治療法は、1965年、僕が東京の吃音治療所で受けた治療法や、1903年の伊沢修二の楽石社の方法と全く同じです。
100年以上も効果のなかった言語訓練を、僕たちは45年前にきっぱりとやめました。世界一の吃音研究者であり、臨床家のアメリカのチャールズ・ヴァン・ライパー博士も、80年の生涯をかけて「吃音は治せない」と言い続けました。
「私はこれまで数千人以上のどもる人の治療に当たってきたが、自分を含めて、誰ひとり吃音を治せなかった。新しい治療法が提案されるたびに、一つくらいは本物があるだろうと期待して調べたが、すべてインチキで、何一つ満足できるものはなかった。心臓病などの慢性病を受け入れざるを得ないように、吃音を受け入れましょう」(3)
この主張は、僕と似ていますが、ライパー博士は「吃音を受け入れるだけでは十分ではない。どもり方は変えられる」と、「楽にどもる」ことも提唱しました。ライパーの弟子、バリー・ギターは、「吃音を受け入れる」ことより、流暢性促進技法の「ゆっくり、そっと、やわらかく」の言語訓練を強調しました。しかし、それも全く効果がないのです。それが、アメリカ言語病理学の限界です。(4)
僕も、ライパー同様に、48年の吃音の取り組みの中で、数千人のどもる人に出会いましたが、誰も治っていませんでした。「吃音は治らない、治せない」と考えて、「吃音といかにうまくつきあうか」に集中する僕と、「楽にどもる」のライパーや、「流暢性の形成」にこだわる、弟子のバリー・ギターとは、根本的に違います。
どもる人たちも、完全に治ることを求めているわけではなく、少しでも軽減し、言いたいとき、吃音をコントロールできれば、楽にどもれればいいと考えています。しかし、それができないから、どもる人は悩みます。15万人以上いるといわれるアメリカの言語聴覚士の95%が吃音の臨床に苦手意識をもつのは、吃音の改善、コントロールも教えられないからです。それをめざすと、教える方も教えられる方も苦しくなります。僕たちの仲間の、ことばの教室の担当者や言語聴覚士は、それらをまったく考えていないので、苦手意識はありません。吃音は、治せないだけでなく、軽減させることもできないと考えて下さい。
あまり意味のない吃音の改善
吃音の症状だけが吃音の問題なら、症状の重い人より、軽い人の方が悩みが小さく、吃音からくるマイナスの影響は小さいはずですが、その反対の場合が実に多いのです。かなり吃音の目立つ人が、どもる事実を認めて、教師など話すことが多い仕事に就いている一方、吃音と分からない程度の人が吃音に深く悩んでいます。吃音は、どこまで、症状が軽減されれば、その人が満足するかの線引きはありません。軽減すればするほど、あと少しあと少しと完全を求め、際限がありません。そして、「いつか、完全に治れば」の思いが膨らみ、吃音と共に生きる覚悟ができないのです。それだけではなく、人生の旅立ちをも遅らせる危険があるのです。
成人のどもる人の苦悩は、「どもれない苦しさ」です。50歳で課長に昇進した人が、大勢の前で、「起立、着席、願います」の決まった短いことばを言えません。普段の業務は、問題なくこなせているので、どもりたくないのです。年に2回の司会のために、仕事を辞めようかと悩んでいます。吃音が改善されても、吃音を否定していれば、さらなる大きな悩みが始まります。多分、みなさんがどもる人のグループのミーティングに参加したら、驚くだろうと思います。からだとことばのレッスンの竹内敏晴さんが、僕たちのところに最初にレッスンに来て下さったとき「これくらいしゃべれれば十分じゃないか。私は君たちを治そうとは思わない」と言われました。僕たちも当然それを竹内さんに求めたわけではありませんが、あまりどもらない人が多いのに驚いたのです。
学校で音読や発表が苦手な子に、音読や発表の練習をして、学校でうまくどもらずに音読や発表ができたとしても、そのときはいいのでしょうが、それが生きる力になり、将来的にも大丈夫ということにはなりません。小学校6年間、ことばの教室に通い、あまりどもらないままに卒業した子どもが、中学生、高校生、大学生になって、あるきっかけで悩み始め、学校へ行けなくなるなどの話は、僕はたくさん聞いています。
ことばの教室で改善できなくても大丈夫
2002年の全国難聴・言語障害教育研究協議会・千歳大会で、千葉市のことばの教室の渡邉美穂さんが6年生の男子K君の実践を報告しました。吃音を肯定し、どもりながら堂々と発表する姿をビデオで紹介したのですが、「ことばの教室で6年間指導したのに、こんなにどもらせて、成果があったと言えるのか」と助言者から厳しく批判され、会場も批判的な空気に包まれ、渡邉さんは悔しい思いをしました。その後、僕は大学生になったK君と会ったのですが、ビデオでみた彼とは違い、あまりどもらなくなっていました。「ビデオの撮影のとき、すごくどもりながら最後までできたのは気持ちがよかった。ことばの教室で、吃音について話して、勉強したことがよかった」と彼は話してくれました。
今、彼は千葉県のある市役所で楽しく働いています。どもったまま卒業しても、吃音を学べたことばの教室の取り組みは、彼を大きく成長させたのです。渡邉美穂さんは、2011年の全難言・札幌大会では「どもりカルタ」の実践を発表しましたが、北海道の人たちから好意的に受け入れられたと喜んでいました。
吃音の改善を目的とした言語訓練の副作用
「吃音は悪いものと否定しているわけではない。吃音を肯定しながらも、改善に向けての努力はすべきだ」との意見は根強くあります。しかし、僕たち当事者の間で長年論議した結果、両立はできないと、「吃音を治す努力の否定」を40年以上も前に提起し、一切の吃音を改善する努力をやめました。吃音を認めながら、治す・改善する努力ができる人なら、そうすればいいですが、子どもの場合は、難しいです。
リッカムプログラムの、どもったら言い直しをさせ、どもらなかったら褒めるというアプローチは、子どもが吃音を否定する可能性があります。また、ことばの教室の先生が、治すために「ゆっくり、そっと、やわらかく」などの言語訓練を一所懸命してくれればくれるほど、「どもることは、いけないことだ」との、吃音へのネガティヴな感情や考えを子どもに持たせてしまいます。吃音を少しでも軽くしてあげようは、教師の善意には違いありませんが、改善を目的とした言語訓練は、「吃音否定」の物語を作りかねないのです。
吃音否定から、逃げの人生を歩む結果となりやすいのが、吃音の治療から受ける副作用です。吃音を強く否定した人が、「どもっても、まあ、いいか」の吃音肯定の道筋に立つのは並大抵のことではありません。僕は21歳でしたが、チャールズ・ヴァン・ライパーは30歳、僕と仲の良かった世界的ミュージシャン、スキャットマン・ジョンは52歳までかかりました。吃音の改善を目的にした言語訓練をする人は、「あなたたちは、ただ遊んでいるだけ、話しているだけではないか」と、みなさんを批判するかもしれません。その批判に耳を貸す必要はありません。「遊び、語り合う」に大きな意味があるのです。これらのことは、子どもが成長し、変化する妨げにはなりませんが、吃音を改善しようとする言語訓練には副作用の危険がはらんでいるのです。
吃音氷山説
吃音の問題は、氷山のようなものです。吃音の原因は分かっていませんが、吃音に悩み、生活にまで影響する原因は分かっています。吃音を否定することが悩みを深め、マイナスの影響を与えます。1970年にジョゼフ・G・シーアンは、吃音氷山説を提起しました。(5) 吃音の症状は吃音の問題のごく一部だとし、言語訓練室で、母音の引き伸ばしや、ゆっくりしたしゃべり方を教え、徐々に普通のしゃべり方へと近づけて、日常生活でも使えるようにしようとする「どもらずに流暢に話す派」を専門家として無責任だと激しく批判しました。(6)
シーアンの氷山説の水面下の問題について、私はこう整理します。
〈行動〉吃音を否定し、吃音を隠し、話すことから逃げ、消極的になっていく行動
〈思考〉どもりは悪い、劣った、恥ずかしいもの、どもっていては有意義な人生は送れないなどの考え
〈感情〉不安、みっともない、恥ずかしい、恐ろしい、情けないなどの感情
〈身体〉緊張して話すとき硬直してしまうからだ、人と触れあうのを拒むからだ
これらは、人間関係の中で不安や劣等感、様々な悩み、生きづらさを抱えている人がもつ共通の課題です。精神医学、臨床心理学、社会心理学などの領域は理論や技法をもっています。吃音の症状にこだわらなければ、これらの領域から学ぶことができます。僕たちは、3日間のワークショップで、交流分析、論理療法、アサーティヴ・トレーニング、笑いとユーモア、竹内敏晴・からだとことばのレッスン、認知行動療法、森田療法、アドラー心理学、当事者研究、ナラティヴ・アプローチなどを学び、冊子として、書籍として出版しています。
» 人や吃音が変わるということ
人が変わる要因
アメリカの臨床心理学者が3年間かけて1960年代から現在までの、来談者中心療法、精神分析、ゲシュタルトセラピー、認知療法など心理療法3000件の論文で人間が変わっていく要因を調べました。人が変わっていく効果の要因を100%にして、効果があった共通の要因を明らかにしました。
特殊な訓練などのスキル 15%
この人なら、この治療法、この病院ならなどの効果期待 15%
セラピストとの関係性の質 共感性 30%
セラピー以外の、何か特定できないこと 40%
この、人が変わる効果の統計的、科学的エビデンスは、臨床心理学の世界の人たちを驚かせ、大騒ぎになりました。しかし、事実は事実として受け止めて、今後カウンセラー教育にどう生かすか模索していると、スクールカウンセリングの第一人者で、大学院で臨床心理士の養成にあたる、九州大学の村山正治名誉教授が話して下さいました。(7)
吃音も、言語訓練のスキルは役に立ちません。教師と子どもとの人間関係、子どもと楽しく遊び、喜んで通級してくることでの期待、その子どもの家庭生活や学校生活などの日常生活で起こる様々な出会いやできごとが、吃音や子どもが変わることに影響しています。
吃音は自然に変化する
吃音は言語指導を受けずとも、言語訓練をしなくとも、どもりながら話していく日常生活の中で自然に変わっていきます。幼児期の吃音の45%は自然消失しますし、場面で吃音は変化します。吃音が自然に変わるのは、明らかです。
吃音親子サマーキャンプで会う子どもたちも、どもる人のセルフヘルプグループ、大阪吃音教室の仲間もそうです。この変化は、自然に変わったものですが、あまりどもらなくなった結果だけを見て、言語訓練でも「吃音は改善できる」と錯覚してしまいます。
音読ができるようになったことが自信になり、その後の生活が充実してきたという子どもが中にはいるかもしれません。しかし、どもる覚悟、吃音と共に生きる覚悟ができていないと、何かのきっかけで、再びどもり始め、悩むことはよくあります。大学生が就職を控えて、あるいは社会人になって3年目に、また、昇進したことがきっかけで、最近よくどもるようになったと、相談の電話をかけてきたり、セルフヘルプグループに来る人は、とても多いのです。
吃音親子サマーキャンプに小学4年生から参加し続けた伊藤由貴さんは、キャンプ卒業時ほとんどどもらなくなっていたのに、大学の薬学部の2年生から3年間かなりひどくどもるようになりました。母親や周りは慌てましたが、本人はなんとか乗り切り、今は薬剤師として働いています。吃音症状の改善よりも、吃音と共に生きるという、自己概念の方が大きな力になった例です。(8)
日常の学校生活の中でこそ、吃音は変化する
近藤邦夫・東京大学教授が、小学校の4年生の授業を見学したとき、出会ったどもる子どものことを書いています。
-この学校のどの教科の授業でも、子どもたちが「自分が考えたこと」や「感じたこと」をものおじせずに積極的に表現する。「合唱」で、曲に合わせてからだをしなやかに動かし、のびやかに声を出している。その中に、強度の吃音症状を示す男児がいた。言い終えるまで長い時間がかかる男児に、子どもたちは、ざわつくことも苛立つこともせず、「それが当然」と、彼の発言に耳を澄まし、彼も堂々と時間をかけて発言していた。二年後訪れた時、他の子どもと見分けがつかなくなっていた。この変化の背景に、何があったのか。彼が吃音治療機関に通った形跡も、担任が「教育相談、カウンセリング」に特に興味をもち配慮をする教師でもない。子どもの吃音症状を、ゆっくりや早口と同等の癖あるいは個性ととらえ、学習活動の中で彼じっと見つめていたのだ。
「自分の体験を思考につなげ、他児と関わり自分の思考を展開させる」
「自分の問題やテーマを、自分の方法で追究する」
「自分の声を出す」
「自分の思いをストレートに表現することを通して自分が生きている感じをつかむ」
こう求める担任に応えて、しなやかに自分の声を出し始めた子どもたち、たどたどしい彼の言語表現をごく自然に聞いていた級友たち。このような教室の中で、ごく自然に吃音は変わっていったらしい。教室の中でのこのような「世界づくり」と「自分づくり」と「仲間づくり」の過程が、恐らく、彼の吃音の変化を促したのだろう。それが学校の「臨床」ではあるまいか- (9)
これが、子どもが変化する基本だと思います。皆さんのことばの教室で、楽しく遊び、歌い、絵本や詩を読んで培ってきた表現力と、ほっとできる場で、どもりながら一所懸命話したことを教師に聞いてもらえた喜びは、通常学級の生活の中で、話し、発表し、友だちと遊ぶことにつながり、そして、吃音は自然に変化していくのです。
基本設定されている吃音
どもる人は、誰もが吃音と共に生きていけるよう基本設定されていると僕は最近考えるようになりました。関節リュウマチの人と知り合い、その生活の苦悩を聞きました。24時間激痛で眠れない。薬で多少痛みが和らいだとき、少し眠れる程度だとの話を聞いて、驚きました。この人たちに関節リュウマチが基本設定されているなんて、とても思えません。しかし、吃音は痛みなどの身体的苦痛は一切ありません。そして、民族の違いを超えて発生率は人口の1%と言われ、紀元前300年のデモステネスの時代から、人間は悩みながらも吃音と共に生きてきました。どんなに吃音を否定しようとも、吃音と共に生きてきたことは誰も否定できない事実です。
「どもりは神様が百分の一の人にどもりをプレゼントして、そのプレゼントに当選した人だと思ったらいいよと言ってくれて、すごく心に響きました」と吃音親子サマーキャンプで書いた子どもの作文を、岡山、静岡、群馬などのキャンプで紹介すると、子どもたちはとても共感し、その輪が広がっていきました。
言語病理学ができ、「治すべきもの」と吃音が治療の対象となって、吃音の新たな問題が生まれたように思います。吃音を、自分の話しことばの特徴だと考え、あまり悩まず生きている人はたくさんいます。吃音を肯定すれば、吃音と共に生きる力は働きます。そうすると、日常生活で起こってくる不都合や不便さは、どもる本人が主体となって、当事者研究でサバイバルしていけるのです。
「どもりながら、治したいとの思いを持ち続けて、不本意に生きる」
「治らない現実を認め、納得して、覚悟を決めて生きる」
吃音が治っていない現実の中で、どんなに治したいと願っても、吃音を否定しても、すべての人が吃音と共に生きています。不本意に生きるか、納得して生きるかの違いがあるだけです。どもる事実を認め、納得して覚悟を決めて生きる子どもに育てたいと思います。
» どもる子どもと何に取り組むか
子どもは、脆弱性がある弱い存在ではない
どもる人の40%に対人恐怖症(社会不安障害)があるとの調査報告を紹介する人や、どもる子どもの脆弱性や運動機能が劣ることを指摘する人がいます。
僕はおそらく世界一、どもる人やどもる子どもに会っていると思います。僕の25年間の吃音親子サマーキャンプで出会った子どもたち、島根、岡山、静岡、山口、群馬などの吃音キャンプで出会った子どもたち、僕の仲間のことばの教室に通ってくる子どもたちは、笑われたり、からかいを受けたりしながらも、しなやかに生きています。どもる子どもは、基本的には「こころは健康」です。
弱い存在だからと、過剰に配慮することは、その子どもの生きる力を奪っていきます。周りが吃音をどう理解するかは課題のひとつですが、親や教師が子どもと相談せずに勝手にすることではなく、どもる子ども本人が、他の子どもにどう理解されたいかを考えます。自分のことばで説明するか、親や教師がするかは、子どもと相談します。仮に、親がクラスの子どもに手紙を書いたとしても、子どもの選択です。自分の力で自分が生きやすい環境に変えていくことになります。
「怖かった、どもりの勉強 するまでは」は、栃木県宇都宮市のことばの教室に通う、小学2年生の子どもが、どもりカルタの読み札として作ったものです。僕たちが苦しんだのは、吃音の正しい知識や情報がなかったからです。どもりは必ず治るとの情報しかなかったため、僕は治療法があり、治ると思っていました。「ゆっくり言う」ことしか治療法がない現実を、子どもたちに伝え、子どもが吃音と共に生きていくのに役立つ知識を学びます。ことばの教室では、あたかも教科を学ぶように、吃音学、吃音哲学を学びます。子どもも、ことばの教室の担当者も、どもりについて正しい知識をもてば、将来を、いたずらに悲観することはなくなるでしょう。愛媛大学の水町俊郎教授が、どもる人の就労実態の調査報告を紹介しました。どもる人が様々な職種の仕事に就いている事実を知れば、保護者も治してあげなくてはとあせることは少なくなります。(10)
子どもと教師は対等。一緒に悩むことが大切
教師と生徒の役割はあっても、人間としては常に対等です。吃音は原因も分からず、治療法もないのですから、吃音の取り組みは、迷い、悩みながら、それでも楽しみながら、常に子どもと相談しながら取り組むのが吃音の学習活動です。時にうまくいって喜び、失敗して落ち込み、一緒に苦労をする。吃音の症状を改善させてあげることはできないが、一緒に考え、悩むことはできます。自分が取り組む課題に一緒に関わってくれる、吃音についてよく知っている、仲間のようなことばの教室の教師の存在は、どもる子どもにとって、どんなにありがたいことか。原因も分からず、治療法もない吃音に、アドバイスや訓練はなじみません。吃音が生活にどう影響しているのか、一番知っているのはどもる子ども自身です。吃音の知識・情報のある教師と、当事者として吃音を知っている子どもが、対等の立場で取り組んでこそ、意味ある取り組みができます。
ことばの教室は吃音学を学ぶところ
ことばの教室は医療機関ではありません。医者でも治せない病気はたくさんあります。治療法のない吃音を、教員が「改善しなければ」と考えることはありません。アメリカでは、公立小学校に言語聴覚士が配置され、どもる子どもの治療に当たります。その治療を受けて成人になった多くの人が、子どものころの言語訓練が嫌だったと言っていると、どもる人の世界大会で何度も聞きました。幸い、日本では、教員が学童期のどもる子どもの指導にあたります。治そうとする言語聴覚士ではなく、吃音教育に取り組むのは、アメリカより素晴らしい教育システムです。
先月、東海四県の難聴言語教育研究大会の吃音分科会で「私は、教員免許をもっているが、言語聴覚士の資格がない。そんな私が吃音の指導をしてもいいのか」と質問を受けました。僕は、言語聴覚士養成の大学や専門学校数校で吃音の講義をしていますが、彼らにも、「吃音は教育だ」といいます。吃音は教員にこそ関わってほしいと強く思います。吃音は言語訓練ではなく、教育だからです。ことばの教室で、子どもとしっかり対話し、社会や国語の教科を学ぶように吃音を勉強します。また、吃音が将来マイナスに影響しないよう予防教育をします。
吃音に向き合うとは
アメリカやイギリスの吃音治療のビデオを見ると、どもった時、のどがどんな状態だったか、呼吸はどうだったか、どんな時どもるかなど、吃音に向き合うといっても、すべて、吃音の症状についてです。吃音の話題も、吃音症状にまつわることばかりです。日本で、吃音をオープンに話すことが広がっていますが、社会科で歴史を学ぶように、吃音の治療の歴史や、どもる人がどう生きてきたかも学んでほしいと思います。『親、教師、言語聴覚士が使える、吃音ワークブック』(解放出版社)で、子どもたちとこれまでの吃音治療法を勉強すると、「そんな練習、絶対嫌だ」「これなら、してもいい」などと、とても盛り上がります。また、吃音は症状だけの問題ではないとの、言語関係図を学び、自分の言語関係図を作ります。さらに、吃音を否定的にとらえることで起こる、マイナスの影響である吃音氷山説を学びます。
最近、吃音検査法が出版されました。日本音声言語医学会が試案を提案した時、実際に使って、信頼できる検査ではないことや、弊害があることを学会で指摘しました。作成をあきらめたかと思っていたのが、30年前とまったく同じものが出版されました。これは、おどろくべきことです。吃音の検査は、することで指導する人が、検査を受けることで子どもが、吃音症状にマイナスの意識をもちます。吃音検査法を批判した僕は、検査に代わって、自分の行動、思考、感情の「自己チェック」を提案しました。変えることができることから、変えていきます。吃音の予防はできませんが、吃音から受けるマイナスの影響は予防できます。それが、吃音氷山説の水面下の問題を知り、行動することです。(11)
吃音に向き合うとは、吃音のマイナスの影響について向き合うことです。
学童期の社会心理的発達課題は勤勉性/劣等感
ライフサイクル論で知られる心理学者・エリクソンの言う、学童期の社会・心理的発達課題の勤勉性で、それを阻むものが、劣等感です。学童期の子どもに関わる教師は、この劣等感について考えておく必要があります。アドラー心理学では、劣等性、劣等感、劣等コンプレックスを分けて考えます。客観的な劣等性があっても、主観的な劣等感をもたない人はいます。僕は吃音をマイナスのものと強く意識し、劣等感が大きくなったために、劣等性、劣等感を口実に、つまり吃音を言い訳にして人生の課題から逃げる劣等コンプレックスに陥りました。
アドラー心理学で言う、人生の課題とは、仕事の課題、人間関係の課題、愛の課題の三つです。子どもの場合の仕事とは、勉強すること、友だちと何かの課題に取り組むことです。「どうせ、どもる僕は何もできない。みんなから笑われるに決まっている」と思った僕は音読や発表ができなくなり、勉強をしなくなりました。友だちとの人間関係、クラスの役割からも逃げ、楽しくない、不本意な学童期・思春期を生きました。劣等感は誰にもありますが、どもる子どもがどもることを理由に、劣等コンプレックスに陥らないようにするのが、僕の言う「吃音の予防教育」です。
ライフスタイルは自分が決意すれば変えられる
アドラー心理学では、10歳前後にさまざまな経験をもとに、「私はこう生きる」とのライフスタイルを決めるといいます。僕もちょうどその頃、吃音に強い劣等感をもち「どもらないように、できるだけ音読や発表はしない」「傷つきたくないから、友だちと仲良くしない」などのライフスタイルを身につけました。
いわゆる吃音症状は、自分の意志に関係なく、自然にどもってしまうことなので自分の力では変えることはできませんが、自分が決めたライフスタイルは、決心し直せば、自分で変えることができます。氷山説の水面下の行動、思考、感情を変えることで、ライフスタイルは変わり、ライフスタイルを変えることで、行動、思考、感情は変わります。ライフスタイルを変えることは、ナラティヴ・アプローチの、「吃音否定の物語」から「吃音肯定の物語」に変えることでもあります。
どもりを治したいのニーズの奥に
「子どもや親には治したいとのニーズがある。それに応えるのが臨床家として当然だ」という意見があります。相手の気持ちに寄り添っているように思えますが、吃音を確実に改善できる時代がきて初めて、そのニーズに応えられます。治せないものを、治したいとの思いに共感すると、治さなければならないの物語をより強化してしまうことになります。
私たちは、「治したい」と子どもが言ったら「なんで治したいの?」と、対話をしながら明らかにしていきます。治したいのニーズの奥には、友だちがほしい、学校で気持ちよく過ごしたいなどの当然の欲求があります。吃音は治せないけれど、友だちを作るにはどうすればいいか、音読や発表をどのように考えたら、学校で気持ちよく過ごすことをできるかは、一緒に考えられます。さらには、「幸せに生きたい」が奥にあるニーズだと思うので、どうしたら幸せに生きられるかを考えます。その時、「どもりが改善したら何々しよう」ではなく、「吃音と共に、豊かに幸せに生きる」を考えた方が現実的です。
吃音が治ること、改善することが必ずしもその人の幸せにつながらないことは、長年吃音と共に生きてきた人ならわかるでしょう。吃音が治ったとしても、改善されたとしても、バラ色の人生がくるわけではないのです。
自分がしないこと、されて楽しくないことはしない
自分が生活の中で決してしないこと、指導されて楽しくないことを他人に勧めてはいけないと思います。教師は学校生活の中で、常に話すことを意識して、「ゆっくり、そっと、やわらかく」話すことをしないでしょう。ゆっくり言う練習は、指導する側も、される子どもも楽しくありません。子どもがどもるからといって、不自然な、仮面のようなことばを教えるのは、ある意味虐待だとさえ僕は思います。どもる子どもも成人も「ゆっくり、そっと言えば、あまりどもらない」ことくらい、教えてもらわなくても知っています。それが生活の中ででき、身につくのなら、世界中、吃音に悩む人はいなくなります。吃音を治したいと心から願いながら、「ゆっくり」話す言語訓練を知っていながら、続けられないのには次の理由があります。
・特別な方法なので、続けることで、ますます吃音をマイナスに意識してしまう。
・練習が楽しくなくて、何時間、何日練習を続ければ改善されるかの見通しがない。
・不自然な話し方なので、日常の生活で使えない。
言語指導をするなら日本語のレッスン
言語訓練は基本的には必要がないと僕は考えていますが、その子どもにとって必要だと考えたら、誰もがして楽しい、意味ある「日本語の発音・発声」の基本を学び、表現力をつけるレッスンをして下さい。竹内敏晴さんの「からだとことばのレッスン」を受けたとき、声を出す気持ちよさ、表現する喜びと楽しさを味わいました。これなら自分自身も楽しく取り組め、子どもたちと一緒にできると思い、僕たちは、吃音親子サマーキャンプで、楽に声が出るように、相手に届く声が出るように、芝居のセリフを言い、歌を歌い、「日本語のレッスン」に取り組んでいます。どもらないようにするための言語指導ではなく、楽に声を出す、相手に伝わる日本語の発音・発声の基本です。今回はお話する余裕はありませんが、『親、教師、言語聴覚士が使える、吃音ワークブック』に、日本語の発音・発声の取り組みを詳しく書きましたのでお読み下さい。
5つの確認
1 世界中どこにも確実な吃音治療法はない。ただ、「ゆっくり話す」ことしかない。
2 治療を受ける受けないにかかわらず、ほとんどの人の吃音は治っていない。
3 吃音の悩み、吃音から受ける影響には、大きな個人差がある。ひどくどもる人が、どもりながら豊かに生きている一方で、ほとんど分からない程度でも、深く悩んでいる。
4 吃音は自然に変化していく。どもらないようにも、どもるようにも変化する。
5 吃音の原因は解明されていないが、吃音に悩み、吃音が問題になる原因は明確になっている。吃音を、悪いもの、劣ったものとマイナスにとらえることで問題となる。
» 当事者研究とナラティヴ・アプローチのすすめ
べてるの家
北海道が世界に誇れることのひとつが、精神医学、臨床心理学、福祉の分野で注目されている、北海道・浦河町の「べてるの家」の「当事者研究」実践です。統合失調症の人たちが、生活の中での苦労をなくすために、薬物でコントロールするのが、これまでの精神疾患の医療でした。日常生活の中で困難が少なくなっても、自分の力で身につけたものではなく、薬によって管理されたものです。べてるの家では、薬をどんどん減らしていきます。当然、日常生活の中で困難がいっぱい起こってくる。これを、べてるの人たちは「苦労を取り戻す」として、生活の中での苦労、困難を、自分が主人公になって、仲間や専門家の協力を得て、生きづらさから自分を助けるための「当事者研究」をします。
障害があっても幸せに生きる「リカバリー」の考え方が、精神障害、発達障害などの枠を超え、様々な分野に広がりを見せています。(12)
吃音の問題を吃音症状だととらえると、「吃音症状の治療・軽減」をめざすことになり、問題を専門家の治療に委ねることになります。しかし、吃音の問題を、吃音を否定することから起こる、どもることへ不安や、恐怖、どもった後の惨めな気持ちにあると考えると、これは当事者が自らしていることなので、自分で取り組むことができます。ここに、「吃音の当事者研究」の可能性があります。子どもが主体的に、学校生活の中で苦戦していること、困っていることを研究する立場で取り組みます。吃音が問題なのではなく、吃音を否定することで起こる問題が問題なのだと考えるのが、ナラティヴ・アプローチです。どもっていても、吃音を否定せず、困っていなければ、何も問題はないのです。
自分の気持ちや生活での困難を知っているのは、子ども自身です。子どもが、吃音と向き合い、自分の吃音の課題に取り組む研究者としての当事者研究が、「吃音を治す、改善する」言語訓練に代わる、ことばの教室の取り組みになってほしいと願っています。その共同研究者になるのが、ことばの教室の教師の役割だと僕は考えています。
どもる子どもの当事者研究
子どもは常に守られ、配慮されなければならない、弱い存在ではありません。弱い部分があるとしたら、それは、知識がなく、勇気をくじかれているからです。吃音を治す、軽減するは、医療の発想です。私たちは、学校生活の中で苦戦をする子どもたちと、苦戦をしている課題に「当事者研究」の考え方を使って研究を進めます。子どもたちは「当事者研究」と言うと「研究? 研究するの?」と目を輝かせて自分の困っていること、困難に思っていることを研究しようとします。自分の課題のすべてを専門家に丸投げするのではなく、自分自身が主人公になって、自分の課題に取り組むのです。
子どもの頃、失敗をしない前に、傷つく前に、周りの人間が手をさしのべ過ぎると、困難な場面に直面したとき、サバイバルしていく、生きる力が育ちません。吃音の場合も、それと同じようなことがあると思います。
どもらないように、吃音をコントロールすることを教えて、仮に100%できるようになったとしても、それはごまかし方を覚え、どもりたくないという思いを強化することにつながります。それよりは失敗して、傷ついたら、その中でどう立ち直っていくのかを学ぶことの方が将来役に立ちます。失敗しないようにさせることは、却ってその子の生きる力を奪っていくだろうと思います。
どもることを笑われる
ひとつの例として、クラスでどもることを笑われた時のことを考えます。まず、人はどんな時に笑うのか、ここから研究が始まります。ちょっとした違いからくる自然な笑いを攻撃的だととらえると苦しいのですが、さげすみや攻撃の笑いでないことに気づけば、「笑われた」の意味が変わります。笑いも研究対象です。からかいの笑いにどう対処するかは、たくさんの選択肢があります。岡山のキャンプで子どもたちがこんな意見を出しました。
◇無視して、その場から逃げる
◇先生に相談して、やめてもらうようにお願いする
◇仲のいい友だちがいたら、友だちに相談する
◇真似されるのは嫌だから、止めてとアサーティヴに言う
◇それでもだめなら、殴ったり、あるいは大泣きをする
◇親がクラスの子どもたちに、やめてほしいと言いに行くか手紙を書く
子どもたちと、それはいい、それは無理やなど、わいわい言いながら話し合いました。子どもたちは、時に大人や友だちの力を借りながら、自分の力で対処しています。僕はこれからの子どもにとって、何かに耐えることは大切ですが、弱音を吐けること、人に助けを求めることができることが大切だと考えています。最近、いじめや体罰による自殺が報じられる度に、常に、逃げるという選択肢をもつことの大切さを思います。
こうして自分の力で問題を解決した力は、その後の生きる力になります。
モノローグ(独語)から、ダイアローグ(対話)へ
僕は、自分の苦しみや悩みを自分のことばで語ることばをもたず、他者に語ることをせず、いつも独り言(モノローグ)で、「オレはだめな人間だ、どもっていたら社会には通用しない」と自らに語り、どもって失敗したり、うまくできない体験をするたびに自分のストーリーを強化して苦しんできました。
中学時代に読んだ、『どもりは必ず3週間で全治する』(浜本正之・文芸社)」の冒頭の「吃音の悲劇」の章には、どもりが原因で自殺をした人、国宝・金閣寺の放火事件などが紹介され、吃音を治さないと将来大変だと書かれていて、治療を薦めます。「吃音悲劇」の物語の影響で、僕は「吃音が治らないと僕の人生はない」と思いつめました。吃音否定の物語は、自分の体験や思いだけでなく、このような一般社会的からの「流暢にしゃべることに価値がある」、「どもっていたら有意義な人生は送れない」「どもりは努力次第で改善できる」などの支配的な言説(ドミナント・ストーリー)に影響を受けます。
21歳の夏、同じように悩む人たちと出会って、どもってもいいとの安心、安全な場で、僕は自分のことばで悩みを語り、対話(ダイアローグ)を通して、自分の課題を客観的に見つめられるようになりました。また、他の人の語る物語を初めて聞き、「将来就職できない」と考えていたのが、「どもっていても仕事に就ける」物語を知りました。吃音治療所には吃音に悩むから来たのですが、みんな地元に帰れば、教師や営業職の人もいて、悩みながらも、仕事をしていたのでした。
1965年、僕はどもる人のセルフヘルプグループをつくり、吃音が自分の人生にどう影響してきたかを語り始めました。吃音を治そうと考え、治す努力することが、いつまでも、吃音の改善を求め、自分の人生を生きられないと、「吃音を治す努力を否定」し、よりよく生きるために努力をしようと、「吃音者宣言」を書きました。吃音否定の物語からの大きな転換点でした。吃音の問題は、どもるかどもらないかではなく、どもるために自分のしたいことも簡単にあきらめ、また当然しなければならないことでもしないで、どもるからと自分に甘え、逃げの人生が身についてしまったと理解しました。
ナラティヴ・アプローチとは
「ナラティヴ」は、「物語」「物語る」の意味で、「ナラテイヴ・アプローチ」とは、「困難や、問題をかかえる人が物語るストーリーこそが、その人の人生を形作っていると考え、困難なストーリーの改訂のために、より好ましい素材を一緒に探し、新しいストーリーを共同で練り上げていくアプローチ」です。
僕は、同じように悩む仲間と出会い、語り合い、他の人が語る人生を知り、吃音の否定的な物語から、「どもっていても、豊かな人生は送れる」の物語に変えることができ、生きやすくなりました。セルフヘルプグループで僕たちは、「吃音否定」の物語を「吃音肯定」の物語に変えていったのです。
「その人が問題なのではなく、問題が問題なのだ」
「人には、その人の人生を生きる能力がある」
このナラティヴ・アプローチの哲学は、ジョゼフ・G・シーアンの氷山説そのものです。 ナラティヴ・アプローチでは、人と問題とを切り離すために、「外在化」の質問をする対話をしていきます。「外在化」とは自分と吃音を切り離して、「どもり君」などと名前をつけて、自分の中のどもりが影響を与えるのではなく、外在化した「どもり君」が、話すことから逃げたり、消極的にさせるなどと、考えます。「どもり君」の影響をあまり受けない経験を見つけるための対話を繰り返し、「どもるから何々ができない」ではなく、「どもりながらも何々ができる」のオルタナティヴ・ストーリー(別のストーリー)に変えていきます。吃音に影響を受けない物語をつくっていきます。
1 吃音と吃音の問題を切り離し、吃音の問題を子どもから切り離して考える。
2 どもる子どもや家族に対する吃音の影響を描き出す。
3 子ども自身が語る、吃音の物語の中に、どもりながらできたことなどに着目する。
4 どもる子どもの本来もっている生きる力、回復する力、レジリエンスを取り戻す。
5 新しい物語を語り、祝福する。(13)
ナラティヴ・アプローチの会話術
ナラティヴ・アプローチの基本的な技法は「外在化」の質問です。吃音は学童期に内面化し、劣等感を強めます。自分の内面にある吃音を自分の外に出し、客観的に見るのが外在化です。私たちの仲間は、子どもたちと言語関係図を一緒に作ります。低学年の子どもにはブロックを使って、吃音の問題を外に出します。どもりカルタや絵本を作って、自分の吃音、吃音から受ける影響について、対話を続けます。最近は、「どもりキャラクター」と対話をする実践を、僕たちのことばの教室の仲間は取り組んでいます。その中で、どもりは敵で悪者のキャラクダーだったのが、対話を重ねる内に、怖くなくなり、どもりが友だちになる物語に変わっていきます。その対話の中から、これまでの吃音の否定的なナラティヴから、これからも吃音とつきあえるというナラティヴに変わっていくのです。
「吃音否定」の物語を「吃音肯定」の物語に変えていくことが、吃音を治すための言語訓練に代わる、今後の吃音の取り組みだといえるでしょう。(14)
レジリエンス
アメリカの心理学者、ウェルナーは、貧困、暴力など劣悪な環境で育った人を長年にわたって調査研究しました。すべての人が貧困や犯罪など大変な生活を送っているだろうと思っていたが、3分の1の人が能力のある信頼できる成人になっていたと報告しました。この人たちのことを「心的外傷となる可能性のあった苦難から新しい力で生き残る能力、回復力がある」として、「レジリエンス」があると言いました。
レジリエンスの構成要素として挙げているものを、吃音に絡めて紹介します。これらは、新しいことというより、吃音と共に生きる中で僕たちが考えてきたことばかりです。
・洞察 吃音の問題の影響について考え、学び、理解する。
・独立性 吃音に支配されることから、自分が人生の主人公になる。
・関係性 親密で満足のできる人間関係。人と結びつき、人を大切にする、人間への信頼。
・イニシャティヴ 問題に立ち向かい、自分を主張し、自分の生きやすい環境に変える。
・創造性 悩みの中から自分を解放させていくプロセスが、新しいものを創造する。
・ユーモア 自分の欠点や弱点を人ごとのように笑い飛ばし、自分の嫌な気分を解放する。
・モラル 吃音と共に、充実したよりよい人生を送りたいという希望をもつ。(15)(16)
» おわりに
吃音親子サマーキャンプで出会った阿部莉菜さん
最後に、吃音親子サマーキャンプで出会った子どものことを話します。小学校6年生になった阿部梨菜さんは、3人の男の子にいじめられ、1週間で不登校になりました。吃音親子サマーキャンプに両親と妹と家族4人連れで、宮城県女川町から参加しました。
グループの話し合いが始まって何人かが、自分のことを語るのを聞いて、阿部さんは手を挙げました。6年生になって、男の子からいじめに合い、学校に行けなくなったことを、涙を流しながら話しました。キャンプの子どもたちは、「そうか、大変だったね」の共感だけの聞き方をしません。「その男の子はどんな子?」とか、「先生は何をしてくれたの?」「友だちはどうしていたの?」など、彼女の話を聴き、彼女の問題の背景を質問していきました。質問に答える中で、彼女の語りが少しずつ変わっていきます。最後に男の子が「梨菜ちゃんはすごいね。学校が大好きで、学校へ行きたいという思いが強いから、遠くから、このキャンプに参加したんだね」と言いました。90分の話し合いの中で、彼女は、自分自身が不登校になっている弱い存在ではなく、学校へ行くために努力している存在だと気がついたのだろうと思います。話し合いが終わるころ、彼女の顔の表情が全く変わりました。そして、翌日の午前中の作文教室で、彼女はこんな作文を書きました。
どもってもだいじょうぶ!
小学6年 阿部莉菜
私は学校でしゃべることがとてもこわかったです。どうしてかというと、どもるから。しゃべっていても、どもってしまうと、みんなの視線が気になります。そして、なんだか「早くしてよ!」と言われそうで、とってもこわかったです。なんだかこどくに思えました。でも、サマーキャンプはちがいました。今年初めてサマーキャンプに来てみて、みんな私と同じで、どもってるんだ、私はひとりじゃないんだと思いました。そして、夕食後、同じ学年の人と話し合いがありました。そのときに思ったのは、みんな、前向きにがんばってるんだ、なのに私はどもりのことをひきずって、全然前向きに考えてなかった。そのとき、私は思いました。どもりを私のとくちょうにしちゃえばいいんだ。そのとき、キャンプに行く前にお父さんに言われたことを思い出しました。どもりもりっぱな、いい大人になるための、肥料なんだよ。そうだ、どもりは私にとって大事なものなんだ。そういうことを昨日思いました。今日、朝起きたときは、気持ちが楽でした。まだサマーキャンプは始まったばかりだと思うけど、とても学校などでしゃべれる自信がつきました。
その後、彼女は2年間、キャンプに参加して、中学生活も楽しく送りました。中学3年生では、クラブの試合とぶつかり、彼女はキャンプに参加できませんでした。そして、2011年3月11日、東日本大震災が起こりました。女川町と聞いて皆さんはすぐおわかりになっただろうと思います。僕たちと出会って新しい人生を見い出し、仙台育英高校に合格して、高校生活を楽しみにしていましたが、制服姿を人前で見せることなく、彼女は亡くなりました。彼女のことは決して忘れないでおこうと、その後の講演会などで紹介しています。ブログにも実名で書いたら、親戚の方がメールを下さり、彼女のことを書いたパンフレットをたくさん注文されました。阿部莉菜さんのことを覚えていてくれることがうれしいと、とても喜んで下さいました。
僕は、聞き方には、初級、中級、上級があると思っています。初級は、共感をして聞く、カウンセリングでみられる聴き方です。中級は相手に関心をもっていろいろ質問しながら聞きます。質問を繰り返す中で、その人が浮かび上がります。上級は、相手が言ったことに対して、その物語の中から、ナラティヴ・アプローチでいうユニークな結果、つまり、自分にはこんな力があると気づいてほしいという期待をもって対話していく聞き方です。 この聞き方が、「その人が問題なのではなく、問題が問題なのだ」「人には、その人の人生を生きる能力がある」との観点に立った聞き方です。子どもたちは、ナラティヴ・アプローチについて一切知らないのに、その子どもを応援しようとして、このような聞き方になったのでしょう。常に話し合いを続けてきた子どもたちの力を思います。
吃音の改善のための言語訓練ではなく、子どもの生きる力を信じて、子どもと対話を続け、吃音肯定の物語を子どもと作り上げていただければと思います。そのために、吃音治療法の研修ではなく、当事者研究、ナラティヴ・アプローチ、レジリエンスなどについて関心をもって学んでいただければ、うれしいです。ご静聴ありがとうございました。
引用・参考文献
(1)「スタタリング・ナウ」NO.240 2014.8.23 消防士として吃音と共に生きる息子へ 兵頭潔
(2)「スタタリング・ナウ」NO.213 2012.5.22 北米の吃音治療の現状 池上久美子
(3)『親、教師、言語聴覚士が使える、吃音ワークブック』解放出版社 伊藤伸二、吃音を生きる子どもに同行する教師の会
(4)『吃音の基礎と臨床』学苑社 B・ギター著 長澤泰子監訳
(5)『To The Stutterer』アメリカ言語財団 邦訳『人間とコミュニケーション』日本放送出版協会 内須川洸 大橋佳子 伊藤伸二訳・編
(6)「愛媛大学教育学部障害児教育研究室紀要」1987年 第11号 水町俊郎
(7)「カール・ロジャーズのパーソンセンタードグループ入門」日本吃音臨床研究会 2008年度年報 村山正治
(8)「スタタリング・ナウ」NO.240 2014.8.23 吃音の大きな波を乗り越えた娘 伊藤康子
(9)『子どもの成長 教師の成長』 東京大学出版会 序章 学校臨床の発想
(10)『治すことにこだわらない、吃音とのつき合い方』ナカニシヤ出版 水町俊郎
(11)「吃音評価の試み-吃音検査法の検討を通して」音声言語医学 1984 Vol.25,No.3
(12)『吃音の当事者研究-どもる人たちが「べてるの家」と出会った』金子書房 向谷地生良、伊藤伸二
(13)『新しいスクール・カウンセリング 学校におけるナラティヴ・アプローチ』金剛出版 J・ウィンスレイド,G・モンク著 小森康永訳
(14)『ナラティヴ・セラピーの会話術』金子書房 国重浩一
(15)『サバイバーと心の回復力~逆境を乗り越えるための七つのリジリアンス』金剛出版スティーヴン・J・ウォーリン 奥野光 小森康永訳
(16)『レジリアンス-現代精神医学の新しいパラダイム』金原出版株式会社 加藤敏 八木剛平