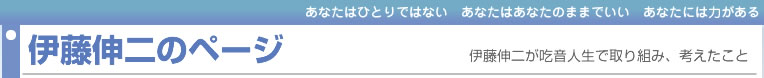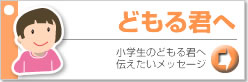「英国王のスピーチ」の豊かな世界
第10回 静岡県親子わくわくキャンプ・講演
2011年10月22日(土)
ロワジールホテル函館
第10回 静岡県親子わくわくキャンプ 10月22日(土)~23日(日)
当日の演題:映画「英国王のスピーチ」に学ぶ、どもる子どもの吃音臨床
~国王の息子兄弟の劣等感、劣等コンプレックスをめぐって~
スタッフのことばの教室の担当者、言語聴覚士対象の学習会での講演記録。当日の講演に、少し加筆したものを紹介します。
日本吃音臨床研究会 伊藤伸二
» はじめに-当事者研究-
映画『英国王のスピーチ』は、吃音の臨床に役立つ、大きな学びと教訓が詰まっています。
主人公は、ジョージ5世の次男であるヨーク公、後のジョージ6世です。長男は社交性があり、流暢にしゃべり、聡明で国民にも人気があります。弟のヨーク公は、物心ついてから、どもらないでしゃべったことはないと本人が言うほどに、吃音に強い劣等感を持ち、悩んで生きてきました。
この映画は、ローグというオーストラリア人の言語聴覚士と英国王の吃音治療の記録映画とも言えますが、社交的な長男と、引っ込み思案な次男の葛藤の話でもあります。 国王は、クリスマスや、国にとって大事な時にスピーチするのが公務です。次男のヨーク公にも話さなければならない局面が出てきます。
1925年の万国博覧会で、ヨーク公が挨拶で、「・・・」と、どもって言えません。
「・・・」と息が漏れたり、間があったり、しゃべれない。そのスピーチを聞いている国民は、一斉に目をそらし、何が起こったのかと、怪訝な表情で顔を見合わせるところから、映画『英国王のスピーチ』がスタートします。
2011年11月、吃音ショートコースというワークショップがありました。テーマは「当事者研究」で、北海道の精神障害者のコミュニティ「べてるの家」の創設者で、ソーシャルワーカーの向谷地生良さんが講師として来て下さいました。べてるの家の実践は、精神医療の世界だけでなく、ひとつの社会的現象として様々な分野から注目されています。一人でする当事者研究もありますが、ひとりでは、堂々巡りになったり、ひとりよがりになる危険性があります。仲間や臨床家など、第三者と研究することが、より効果的です。
小説でも映画でも、読者、観る人の数と同数の感想、受け止め方があります。王室に関心ある人、第二次世界大戦当時の歴史に関心ある人、家族のあり方に関心のある人で、「英国王のスピーチ」はさまざまな研究ができます。映画「英国王のスピーチ」で描かれたジョージ6世を、吃音に深く悩み、吃音に長年取り組んできた伊藤伸二という第三者の目を通して「研究」します。
» 臨床家における対等性
ヨーク公を愛称「バ-ティ」と呼ぶ
まず、セラピストとクライエントの関係です。
ことばの教室の教師や言語聴覚士とどもる人、どもる子どもとの関係です。セラピーが成功した要因のひとつが、「対等性」です。
私はこれまで、教育や、対人援助の仕事にかかわる人に、向き合う相手との「対等性」の重要性を言い続けてきました。特に、原因もわからず、治療法もない吃音は、一緒に悩み、試行錯誤を繰り返さざるを得ません。共に取り組むという意味で、対等性が何よりも重要です。
ジョージ5世の次男、ヨーク公には、これまでにたくさんのセラピストが治療しますが、すべて失敗に終わります。そのために本人はあきらめ、もう吃音治療はしたくないと言います。しかし、妻のエリザベスはあきらめません。夫に内緒でいろいろと探し回り、新聞広告で見た「言語障害専門」という看板のある、ライオネル・ローグの治療室に来ます。
「あらゆる医者がだめでした。本人は希望を失っています。人前で話す仕事なので、どうしても治したいのです」
「それなら転職をしたらどうですか」
「それは無理です。個人的なことは聞かずに治療してほしい、私のところに来てほしい」
「だめです。私の治療室に通って下さい。治療に大切なのは、信頼と対等な立場です」
エリザベスが、クライエントがヨーク公だと身分を明かしても、ローグはこれまでの態度を変えることなく、対等性にこだわります。ヨーク公と直接対面した時、ヨーク公が「ドクター」と呼ぶのを遮り、「ライオネル」と呼んでほしいと言い、ヨーク公を「殿下や公爵」ではなく、家族しか呼ばない愛称「バ-ティ」と呼ぶと宣言します。
ヨーク公は、「対等だったらここに来ない、家族は誰も吃音を気にもとめない」と抵抗しますが、「私の城では私のルールに従っていただきます」と譲りません。イギリス人のセラピストなら、王室の人間に対等を主張することはありえません。オーストラリア人だからかもしれませんが、それにしても、あの時代としてはすごいことです。二人にとって、この対等な関係がとても大きな意味をもちました。
ナラティヴ・アプローチ
対等の関係であることは、どんな臨床にも必要だと私は思いますが、それにいち早く気がついたのが、家族療法の分野です。家族療法の世界では近年、ナラティヴ・アプローチが注目を集めています。その中で言われるのが「対等性」です。なぜ対等性が言われるのでしょうか。
ナラティヴとは、「物語」、「語り」の意味ですが、人はそれぞれ自分の物語を作ります。自分についての物語は、本人が誰よりも知っていることへ敬意です。だから本人に教えてもらう、「無知」の姿勢を貫きます。ここに対等性が出てきます。
本人が語る物語がネガティヴであれば、その物語に捉われて悩みます。ジョージ6世は、「どもりは劣ったもの、悪いもの、恥ずかしいもの」の物語を繰り返し語ります。その物語には伏線があります。弟はてんかんでした。その弟は世間から隠されて13歳でひっそりと亡くなります。弟の話は王室ではタブーです。その弟に優しかったのが、兄であるヨーク公です。
彼はそこで、王室は自分の愛する弟を障害があるからといって隠すのだ、という物語に出会います。そして、王になるような人間は、吃音という言語障害をもっていては駄目だとする物語を強化していきます。
世間一般も、同じように、どもる人間は王にふさわしくないという物語をもっています。自分が語る物語と、世間一般の物語によって、ヨーク公は、どもる人間は国王になるべきではないとの物語をもっています。ヨーク公は次男なので、長男が生きている限り、彼が国王になることはないのですが、吃音の国王は考えられないのです。
この、自分を不幸にする物語に、新しい物語を、セラピストと一緒に作っていくのがナラティヴ・アプローチです。自分の否定的な物語の上に、肯定的な、自分がよりよく生きていくための物語を作っていく。「英国王のスピーチ」は、吃音治療の物語ではありますが、結果として、このナラティヴ・アプローチになっていたと私は思います。
ヨーク公は、ヨーロッパ中から治療者を探し、治療を受け続けても結局改善しません。そして、賛否両論のある異端のセラピスト、ライオネル・ローグに出会うのです。
ローグの献身的な、集中的な治療でも吃音は治りも、改善もしません。にもかかわらず、目標だった第二次世界大戦の国民に向けての開戦スピーチは成功するのです。吃音治療の結果ではなくて、ジョージ6世が自分の物語を変えていくことができた結果です。そのために「対等性」が意味をもちます。人に言えない悩みを話し、それに共感して聞いてくれる友達がいた。吃音に悩む人間にとって、治療者ではなく、友人が必要なのです。
映画のラストに、ジョージ6世は、ローグを生涯の友として考えていたとあります。吃音が治れば、あるいはある程度改善されれば、それで治療者との関係が切れます。しかし、治らない、治せない吃音の場合は、この対等の友人であることが、何よりも必要だったのです。
映画のエンディングにテロップが流れます。
「1944年、ジョージ6世はローグに、騎士団の勲章の中で、君主個人への奉仕によって授与される唯一の、ロイヤル・ヴィクトリア勲章を授与した。戦時下のスピーチには毎回ローグが立ち会い、ジョージ6世は、侵略に対する抵抗運動のシンボルとなった。ローグとバーティは生涯にわたり、よき友であった」
セラピストも劣等感や弱点のある存在
ローグがオロオロする場面があります。ヨーク公の時代、国王になる不安を爆発させ、ローグと決裂し、セラピーをやめてしまいます。その後、国王になってやはりローグが必要になり治療の再開を頼みに、妻が留守のはずの自宅に国王夫婦が尋ねた時です。その時、思いがけずにローグの妻が帰ってきます。妻に内緒でセラピーをしていたローグはあわてます。国王が、自分の家にいたら誰もが驚くでしょう。妻とエリザベスが出会ってしまい、話すのをドア越しに聞きながら、国王を紹介するタイミングでオロオロと困っているローグに「君は、随分臆病だな。さあ、行きたまえ」と、ドアを開けます。ジョージ6世はそこで初めて、ローグも、臆病な、気の弱い人間だと、自分に近いものを感じます。
ローグが自分の弱さを見せたことで、ジョージ6世は、ピーンと背中を張ってドアを開けます。このシーンのコリンファースの演技は見事です。ここで、本当の意味で、対等を感じて信頼できたのだと思います。
言語聴覚士の専門学校で講義をしてると、伊藤さんは吃音だからそんなことが言えるけれども、吃音の経験もない、経験の浅い人間にそんなことは言えないとよく言われます。人間、誰もが何がしかの挫折体験、喪失体験があります。受験の失敗、失恋、祖母の死などを経験して生きています。そのような誰もがもつ経験を十分に生きれば、吃音の経験のあるなしは関係がないと、学生には言います。弱いからこそ、劣等感があるからこそ、自覚してそれに向き合えば、セラピストとしていい仕事ができるだろうと思います。
私は、死に直面する心臓病で二十日以上入院しました。そのつらい時に、活発で、はいはいと明るすぎる看護師さんよりも、「大丈夫?」とほほえんで声をかけてくれる優しい看護師さんの方にほっとしました。自分が弱って困っているときに、堂々と笑う豪快なカウンセラーに相談に行く気には私はなりません。
自分には、大したことはできないけれども、せめてあなたの話だけはしっかり聴いて、一緒に泣くことならできそうかなあというような人のところに私は行きます。入院を三回経験した、弱った人間としては、そう思います。
私は、福祉系の大学でソーシャルワーク演習を担当しています。そこでの対人援助者の講義や、教員の研修で、私はヘレン・ケラーとサリバンの話をよくします。
奇跡とも言える教育が成功したのは、ヘレンがサリバン先生を信頼する前に、まずサリバン先生がヘレンを信頼したからです。ヘレンはきっと人間としてことばを獲得し、成長するという信頼があった。また、目も見えない耳も聴こえないで生きてきたヘレンへの尊敬があったと思います。
ローグも、相手に対する尊敬と、この人はきっと変わる、いい国王になるという信頼があったから、それに応えてジョージ6世もローグを信頼したのです。変わるというのは、いわゆる一般的に思われているような「変わる」ではありません。吃音そのものではなく、彼の思考や行動や感情は変わると、信頼をもっていた。
どもらずに堂々とスピーチすることが成功ではない。不安をもちながら、おどおどしながら、嫌だ嫌だと思いながら、そしてどもりながら、なんとかスピーチをやり遂げたことが成功です。
弱音を吐けること
弱音を吐けることは、人間が生きていく上で大事なことだと思います。人に助けを求められる能力も大切です。「助けて」と言えるのは、自分の弱さを認めることでもあります。
ヨーク公には、弱音が吐ける、自分が自分でいられる場がありました。ローグから対等を求められたとき、即座に彼は、家族は対等で、妻も娘もちゃんと聴いてくれ、吃音は何の問題もないと言います。吃音があっても人間としては対等だと言います。弱さを認めて、愚かな人間だ、自分は大した人間じゃないと認めるシーンがあります。
エリザベスが、ピーターパンの絵本を読んでいた時、「ピーターパンのように自由に飛んで行ける奴はいいなあ」と、ヨーク公が言ったあとで、娘二人からおとぎ話をせがまれます。そこで、ペンギンの真似をしますが、娘はさらに求めます。
「では、ペンギンの話をしよう。魔女に魔法をかけられペンギンになったパパが、二人の姫に会うために、海を渡ってやっと宮殿にたどり着き、姫にキスをしてもらいました。姫にキスをしてもらって、ペンギンは何になりましたか?」
娘に聞くと、娘たちはうれしそうに、「ハンサムな王子様!」と言います。すると、「アホウドリだよ」と言って、大きな翼を広げて、二人の姫をしっかりと抱きしめます。ペンギンのままでは愛する姫を抱けないが、大きな翼のあるアホウドリなら抱けるからです。
このペンギンの話を娘に聞かせることで、自分の劣等感、惨めさを客観視して話したのだろうと思います。つい見逃しそうな場面ですが、自分の弱点とか愚かさを、ユーモア、自虐ネタのように使うのは、自分の弱さを認めていたからでしょう。
また、戴冠式のニュース映像を家族で観ている時に、自分の映像が終わった後、ヒトラーが演説するシーンがでてきます。「この人、何を言っているの?」と聞く娘に、「何を言ってるか分からんが、演説はとてもうまそうだ」と言います。ヒットラーの演説はうまい、自分にはできないスピーチだと認める。これも大事なシーンだと思います
1936年12月12日、王位継承の評議会で、すごくどもってしゃべれませんでした。そしてその夜、もう自分は駄目だとエリザベスの胸で子どものように泣きじゃくります。クリスマス放送で不安がいっぱいになります。
「クリスマスの放送が失敗に終わったら…。戴冠式の儀式…。こんなのは大きな間違いだ。私は王じゃない。海軍士官でしかない。国王なんかじゃない。すまない。情けないよ」
「何を言うの…あなた…かわいそうに、私の大切な人。実はね、私があなたのプロポーズを二度も断ったのは、あなたを愛していなかったからじゃないの。王族の暮らしをするのが嫌で嫌で、がまんできなかったわ。あちこち訪問したり、公務をこなしたり、自分の生活なんかなくなってしまうから。でも、思ったの。ステキな吃音、幸せになれそうって」
エリザベスは、どもりながら一所懸命話すヨーク公の姿に誠実さをみたのでしょう。あなたの吃音を聞いて、「Beautiful」と言う。そして、「素敵な吃音のこの人となら、私は幸せになれるかもしれないと思って結婚したのよ」と言う。とても素敵なシーンです。
こういうふうに、自分の弱さを、妻にも娘にも、アホウドリという表現をしながら、自分なんか大した人間じゃないよと言う。家族に弱音を吐けるのはすごく大事なことです。
人が生きていく上で、嫌なこと辛いことは山ほどあります。弱音を、誰かに話したい。私はよく、教師や援助職のセルフヘルプグループ、弱音を吐ける教師の会のようなものがあればいいなあと思います。愚痴を言い合える仲間が必要だと思います。
どもる子どもに対して、強くなれ、そんなことで逃げちゃだめ、泣いちゃだめ、と言うのではなくて、弱音が吐ける子どもに育ててほしい。困った時には困った、苦しい時には苦しい、助けてほしいと素直に言えるしなやかさが必要です。強くたくましく生きる必要はない。弱音を、家族にもセラピストにも話せたから、ローグとの臨床が成功したのだと思います。もしあの家族の、妻の、娘たちの支えがなかったら辛いです。そういう意味では、これは家族の支えの映画でもあったと言えると思うのです。
» 吃音の問題とは
ローグが治療を引き受けるとき、「本人にやる気があれば治せる」と言います。吃音治療の要望に言語訓練はしましたが、これまでの経験から効果があるとは思ってなかっただろうと思います。治療の初期には80日以上連続して集中的に訓練を続けますが、まったく効果がありません。
全く改善しないままに、最後の開戦スピーチの録音室に向かいます。スピーチ5分前まで、歌ったり、踊ったり、悪態を叫んだりして、必死で声を出す練習をしますが、うまくいかない。不安を抱きながら、スピーチをしますが、自分でも満足できる成功を収めます。なぜ成功したのか。ここに吃音の臨床の大きなヒントがあるのです。
はじめのシーンで出てきた、口にビー玉を含んで話す治療は、紀元前300年代ギリシャのデモステネスが実際に訓練した方法で史実です。海岸の荒波に向かって大声を出す練習などで吃音を克服し、大雄弁家になったと言われています。彼は吃音を治すために過酷な訓練を続け、成功したと言われていますが、訓練の結果ではないと私は考えています。
デモステネスも、ギリシアの国を守る責任感と、政治家として弁論をしなければならない役割と立場があった。それらがデモステネスのことばを変えたのであって、訓練がことばを変えたのではない。
私も、21歳までかなりどもっていましたが、治すことを諦めて、どもりながら生きていこうと覚悟を決めて、日常生活に出ていきました。仕送りの全くない東京の大学生活を送るためのアルバイト、自分が創立したどもる人のセルフヘルプグループの発展のために必死に活動しました。その後、大阪教育大学の教員になり、人前で自分の考えを伝えなければならない立場に立ちました。
グループの責任者として、大学の教員として、「語るべきことばと、語りたいことば」を話していく中で、私のことばは変わりました。
デモステネスも、ジョージ6世も、私も、人前で話せるようになったのは、吃音治療の結果ではなく、自然に変わったのです。ローグが治せると言ったのは、吃音症状そのものではなくて、吃音不安、吃音恐怖だったのです。
心の問題だと捉え、不安や恐怖へアプローチしたのです。
ジョージ6世の話すことへの不安と恐怖は、映画全編に出ています。不安が頂点に達したのが、国王にならなければならないかもしれないと感じ始めた時です。
吃音への不安が頂点に達した時
兄が、愛人と一緒にいる山荘に、弟夫婦を招待した時に、ヨーク公は、王としての仕事をしない兄に苦情を言います。その時兄は、「お前はスピーチの練習をしているそうだが、王位を奪おうと思っているのか」と、彼のどもる真似をします。とても仲のいい兄弟だったから、今まではあまりなかったことだろうと思いますが、その時に、怒りが込み上げても、兄に何も反論もできず、本当に悔しい思いをします。悔しい思いを、ローグのところに行ってぶちまけます。ローグが誘って散歩をするシーンです。
「長男の国王が、離婚歴のある人間と結婚するつもりらしい。王室では、離婚経験者とは結婚できない」と話した時に、ローグが、「あなたが王になったらいい、立派な王になれる」と言います。すると、現実には兄が王の座にいるのに、王を侮辱するのかと怒ります。これは、兄が侮辱されたことへの怒りというよりも、国王になることへの不安が頂点に達したのだと思います。
兄が本当にシンプソン夫人と結婚したら、王ではいられなくなる。となると、絶対になりたくなかった王に自分がならなくてはならない。国王になるとスピーチをしなければならない。不安が頂点に達する。ローグがいなければ本当は困るにもかかわらず、不安が恐怖になり、思わず「お前とのセラピーはおしまいだ」と決裂します。
このシーンが、大きなポイントになっています。 吃音そのものではなく、彼の不安と恐怖にこそアプローチをしなければならないと考えたローグのセラピーに対する考え方は、的を得て、とても素晴らしいと思います。
異端の、卓越したスピーチセラピストであるローグは、1920年代にすでに、スピーチセラピーは大した効果はないことを知っていた。セラピーすべきは、吃音への不安と恐怖から、全てに自信をなくしている、心の問題だと見抜いたのです。
» 吃音治療の歴史
ローグの時代の吃音治療
1920年から1930年代当時の治療技法が発達していなかったからうまくいかなかったと皆さんは考えるかもしれませんが、映画に出てくる技法は、ビー玉を口に入れること以外は、全部現在でも使われているものばかりです。
これまでたくさんの治療を受けながら、少しも改善しないために、ヨーク公本人は吃音治療をあきらめていますが、妻のエリザベスはあきらめません。探し回ってローグに行き着きます。彼女の強い希望で、仕方なく、ローグの治療室を訪れますが、「バーティ」と対等に呼ばれることに抵抗感もあり、気乗りはしません。「誰にも私の吃音は治せない」と言うヨ-ク公に、今でも使う、マスキングノイズを使います。
「私はあなたが、全然どもらずにしゃべれることを証明してみせる」と1シリングの賭けをします。シェイクスピアの有名な「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」の台詞を読ませますが、どもって読めません。そこで、ヘッドフォンをつけさせ読んでみなさいと言う。ヘッドホンから大音量の音楽が流れる中で読ませてレコードに録音します。
「無駄だ、絶望的だ。この方法は私には向いていない」と去ろうとするとき、「録音は無料です。記念にお持ち下さい」とレコードを渡される。
父親のクリスマス放送に立ち会ったとき、「お前も練習してみろ」と原稿を渡され、読んでみた。どもって全然読めずに落ち込んだ。そして、ひとりで、部屋で音楽を聴いていたとき、ふと、あのレコードのことを思い出し、聴いてみました。すると、「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」とどもらずに読んでいます。自分の耳には、音楽が聞こえているから、しゃべってる声は全然聴こえません。これがマスキングノイズです。びっくりして、ひょっとすると役に立つかもしれないと思い直して、ローグのもとを再び訪れ、治療が始まります。
ローグは、治療として、音楽をヘッドフォンで聴かせる、腹式呼吸、からだや顎や舌などの筋肉をゆるめる、大声で発声する、ゆっくり間をとって話す、歌って話すなどを試みますが、驚くことに、それらは現在とまったく変わっていません。その後新たな治療法は何一つ生まれていないのです。しかし、ローグは、あの当時は異端であっても、現代にも十分通用する、吃音臨床に対する哲学をもっていました。
ローグは、吃音の問題はことばにあるのではなく、心の治療こそが必要だと言います。あの当時も、いろいろな治療法をするセラピストがいたでしょうが、何の役にも立たないと、ローグ自身はわかっていたのでしょう。だから他のセラピストとは違う異端のセラピストだとの評価がされていたのです。これは、当時としてすごいことです。
アイオワ学派の治療
1930年代に、吃音に悩んで、吃音を研究したいと考えた人たちが、アイオワ大学に集結しました。チャールズ・ヴァン・ライパー、ウェンデル・ジョンソンらです。
彼らは、従来の「わーたーしーはー」という不自然であってもどもらない話し方を身につける、吃音をコントロールするセラピーは、どもることへの不安や恐れをかえって大きくすると批判しました。吃音の問題は、吃音症状だけにあるのではないとの考え方です。
ウェンデル・ジョンソンは言語関係図で、ライパーは吃音方程式を作り、吃音は症状だけの問題ではないと強調しました。
この二人よりも明確に言ったのが、アメリカの著名な言語病理学者、ジョゼフ・G・シーアンです。吃音は、随伴症状を含めて周りから見えていて、本人も意識しているのは、氷山のごく一部で水面上の小さな部分だ。本当の吃音の問題は、水面下に大きく隠れている。それは吃音を避けたり、どもると惨めになったり、不安になったり、恐怖に思ったり、そういう感情の問題だとする、吃音氷山説を主張しました。
1970年、シーアンは、この考え方を、アメリカ言語財団の冊子「To The Stutterer」で発表しました。その冊子を、内須川洸筑波大学名誉教授と一緒に翻訳して出版したのが、『人間とコミュニケーション-吃音者のために』(日本放送出版協会)です。
私が自分の体験を通してずっと考えてきたことなので、うれしくて、シーアンに手紙を書きました。とても共感し合え、新しい著書も送っていただきました。シーアンよりも丁寧に整理すると、行動、思考、感情はこうなります。
行動は、吃音を隠し、話すことから逃げ、いろいろな場面で消極的になっていくことです。
ジョージ6世は、吃音を隠し、話すことから逃げて、すごく非社交的な生活をしました。王室は社交の世界で、社交が大事な公務であるのに、彼はすごく引っ込み思案で、王室としては困った存在でした。エリザベスと結婚することで、社交の場は広がったようですが、人前に出るのをとても嫌っていました。ヨーク公は、どもりを隠し、話すことから逃げ、できたら話さないでおきたかったのです。だから国王なんかになりたくないと逃げ続けました。これが行動です。
思考は、「どもりは悪いもの、劣ったもの、恥ずかしいもの」。「どもっている人間が王などになるべきではない」。「どもってするスピーチは失敗だ」などという考え方です。「どもってスピーチすると、国民はこんな情けない国王を持って、不幸せだと思うに違いない」という考え方です。
感情は、どもることへの不安、スピーチすることへの不安、恐怖です。どもった後の恥ずかしい、みっともないと思う気持ち。どもることで相手に迷惑をかけたと思うなどの罪悪感です。
シーアンは、これこそが吃音の問題なのだと主張しました。それなのに、アメリカ言語病理学は、1970年のシーアンのこの提案を吃音にどう生かすか、全く考えずに放置してきた。やっと最近、吃音評価と臨床のために「CALMSモデル」という多次元モデルが、何か新しいことのように出されました。
けれど、それよりもはるか前にシーアンが言った方が、吃音の本質をついて、シンプルで臨床に使いやすいモデルを提案していたのです。シーアンは、水面下に隠れた大きな部分が、吃音の問題だと言ったわけですが、1920年代のローグがすでに考え、実際にやっていたのです。
ローグの孫が、ローグの日記やセラピーの記録を、脚本家のサイドラーに提供したことで、吃音治療の真実が語られることになりました。サイドラーは、アカデミー賞の脚本賞をもらいましたが、思春期までかなり吃音に悩んでいました。また、子どもの頃に、ジョージ6世のスピーチを実際に聴いています。自身の体験と照らして、セラピー記録をもとに、当時の吃音治療を詳細に調査して脚本を書いていますので、「英国王のスピーチ」に出てくる吃音の治療場面は、正確で間違いないだろうと思います。
そう考えると、この映画が誕生したのはいろいろな要素がからみあった奇跡のような気がします。
吃音治療に関するローグの基本的な考え
ローグの吃音治療の考え方が明らかになるシーンがあります。戴冠式の準備の時です。
医者や言語聴覚士の免許もなくて、吃音や臨床の研修の経験もないことが、王室の調査機関で分かり、宮殿でローグはヨーク公から責められます。大司教から、セラピストを変えるように言われるからです。一向に治療効果がないことへのいらだちもあって、資格のない人間が、どうして吃音治療をしているのか、お前は詐欺師だと、ローグを責めます。その時に彼が反論したことが、彼の臨床を物語っています。
「言語障害専門」と看板を掲げるローグのもとに、様々な言語障害に悩む人が相談に来ます。ベトナム戦争のあと、帰還戦士が戦争後遺症から、自殺をしたり、さまざまな精神障害に悩まされます。心的外傷後ストレス障害やトラウマのことばが一般に知られるようになりましたが、それより前の第一次世界大戦で、人を殺し、友人が知人が死んでいくのを目の当たりに見た兵士たちが、戦争が終わった後、しゃべれなくなります。そのような兵士のセラピーの体験を語ります。
「私は医者ではないが、芝居はそれなりにやった。パブで詩を読み、学校で話し方も教えた。戦争になり、前線から戻る兵士の中に、戦争神経症でしゃべれない人間がいた。誰かが私に言った。「彼らを治してやれ」と。運動や療法も必要だが、心の治療こそが大切だ。彼らの叫びに誰も耳を傾けない。私の役目は、彼らに自信をもたせ、“友が聞いている”と力づけることだ。あなたの場合と似ているだろう」
「見事な弁明だが、詐欺師だ」
「戦争で多くの経験を私は積んだ。成功は山ほどある。経験はたくさんしている。ドクターと自分で言ったことはない。詐欺師だというなら、私を監禁しろ」
このやりとりで、ジョージ6世は、ローグが自分の話をよく聞き、真剣に向き合ってくれたことを思い出します。資格がなくても自分にとってはローグが必要だ。大司教の推薦するセラピストを、「これは私個人の問題だ」と断固拒否し、改めてローグをセラピストとして選びます。本当の信頼関係が確立した瞬間です。再びセラピーが始まります。
» 人間が変わっていく要因
九州大学の村山正治先生に紹介していただいた、カウンセリング、精神療法、心理療法の効果要因の研究があります。ゲシュタルト・セラピー、交流分析、論理療法、来談者中心療法などいろんなセラピーに共通する効果要因の調査研究です。
それぞれの流派は自分たちの技法が一番効果的だと考えていましたが、流派による差はなく、その代わりに興味深い数字が出ました。人が変わっていく要因の全体を100%とした場合の数字です。
①特殊なスキル 15パーセント
②期待効果 15パーセント
③セラピストとの関係性 30パーセント
④セラピー以外の場 40パーセント
これは心理臨床の研究ですが、自然に変わっていくことの多い吃音臨床の場合、④は、この数字以上だろうと僕は考えています。
特殊なスキルとは、多くの臨床家が自分こそはと誇るその流派の特殊な治療技法で、15%。
治療に期待する効果は15%。
アメリカでは、偽薬の研究が盛んです。あまり信頼できない医者が処方する本物の薬より、信頼できる医者の小麦粉が効く場合があるくらい、セラピストとの関係性は大きく、30%。
一番大きい40%は、セラピーの技法などと関係ない、セラピー以外の場です。いい仲間や恋人ができた、仕事がうまくいった、楽しめる趣味のようなものが見つかった、思いがけず宝くじに当たったなど、生活の中のセラピー以外の場で起こっているさまざまな出会いやできごとです。いわゆる自然治癒といっていいかもしれません。自然治癒力、免疫力、私は自己変化力と言いますが、日常生活を送る中で、何かは特定できないけれど自然に変わったのが、40%です。
これはアメリカの長年の膨大なデータをもとにした、信用できる報告です。これが報告されたときに、村山先生の大学院の臨床心理士になろうとしている学生がショックを受けるから、紹介しないほうがいいよとの話が冗談まがいに出るくらい、治療技法を学ぼうとしている人にとっては衝撃的な調査結果だったようです。
私は言語聴覚士養成の専門学校で講義をしていますが、学生は吃音治療のスキルを求めます。ことばの教室の教師もそうです。治療技法を探し、研修する人がいい臨床家だと錯覚している人がいます。問題を抱えて、人が生きる中では、治療技法よりもセラピストとの関係性の方がずっと大きいのです。相手を対等と見て、尊敬し、信頼する。相互尊敬、相互信頼のないところにセラピーは成り立たないのですが、その重要なセラピストとの関係性でも30%です。何か分からないけれど、自然に変わったが一番多いのです。
ジョージ6世の場合も、開戦スピーチが成功した要因は、後で詳しく話しますが、ローグの吃音治療のスキルよりも、国王を支える妻のエリザベスを中心とした家族の愛、国王としての、スピーチを含めてのさまざまな公務の中での人やできごととの出会いが影響しています。セラピー以外の場の40パーセントだろうと思います。
ことばの教室でも、あれこれと教室で40分ほど言語指導して、指導に効果があったと考える人がいるかもしれませんが、それは疑問です。仮に変わったとしてもそれはその子どものもつ、自然変化力によるものでしょう。学校生活の中で、先生や同級生との関係がいい方向に変わった、何か喜びや楽しいことができたなどの可能性の方が、ずっと大きいのです。
このことに関係して、再び「対等」の話をします。映画での「対等」は、治療の場では、国王も国民も対等だということに矮小化されそうですが、そうではありません。セラピストとクライエントは対等で、セラピストがクライエントよりも優れていたり、吃音に関して何か特別の知識や技能があるわけではなく、対等とは、セラピストの、自分は大したことはできないとする、「無力宣言」に等しいのです。大したことはできないけれど、対等の人間として誠実に関われば人は変わっていくのです。
家族療法におけるナラティヴ・アプローチでは、「無知」と言います。自分を苦しめている問題が、どう自分の人生に影響しているかを一番知っているのは研究者や臨床家ではなく、本人です。当事者本人に教えてもらうしかない。無力で何も知らないから、本人に教えてもらうのです。ことばの教室だったら、吃音についてどんなことを考え、どんなことで困り、どんな将来へのイメージをもっているか、子どもに教えてもらわないと、取り組みは成り立たないのです。
なのに、あえて強い言葉で言えば、傲慢にも、吃音研究者や臨床家は、自分が吃音について一番知っているかのような錯覚を起こして、自分の数少ない臨床経験の中で、こうやればこうなるはずだと考えてしまう。これはとても危険なことです。
ローグは徹底して彼の側に寄り添い、真剣にジョージ6世の話を聴いています。まさに臨床です。
ローグが対等の立場で、よく話に耳を傾けることによってジョージ6世は心を開き、自分の苦しかった幼少期について話します。王室では、母が育てず、乳母が育てるようですが、乳母につねられたり、食事を与えられないなど3年間虐待を受けた苦しみや、兄との関係や、13歳で死んだ弟のことなどを話します。
その話は、一般国民のセラピスト、ローグには想像もつきません。言語障害の専門家ではあっても、その人がどう生きてきたかは、教えてもらうしかないのです。私は何も知らないから、あなたが物語って教えてほしい。無知であることに徹底します。対等は能力的にも上下関係ではないので、セラピストも当然のことながら失敗します。ローグもいっぱい失敗する。しくじった、しくじったと何度も言っています。
特に吃音は、確実な治療法がなく、ローグにしても、自信があったわけでも、こうなると見通しをもってジョージ6世に関わったわけでもなかったでしょう。治療法のない、吃音の取り組みは、失敗して当たり前、しくじって当たり前なのです。だからしくじったら、ごめんなさいと謝って、悩んで落ち込む。対等ということは、一緒に落ち込み、一緒に悩み、一緒に失敗し、一緒に成功する。その中で一緒に何かを探し出していく。その姿勢が、対等であるということです。
映画でも、ローグを専門家であるけれども、一人の劣等感をもつ人間として描いています。彼は、オーストラリア人であること、オーストラリア訛りがあるために、シェイクスピアの劇のオーディションに失敗したことなどの劣等感をもっています。弱さや劣等感をもっている仲間として対等で、一緒に歩んでいく。これが僕が言う対等性です。
ローグは見事に対等性があったが、映画の冒頭に出てくるような、消毒してあるからと言ってビー玉を口に含ませて、「ビー玉に負けず、集中して」と、上から押しつけるような医者であれば、絶対に成功はしていません。
セラピストも、自分と同じ匂いがする、劣等感をもっている弱い存在なんだと思えたから、ジョージ6世はローグを信頼したのだと思います。ジョージ6世とローグの互いに信頼する対等な人間関係が30パーセントです。
治療場面以外の場が40パーセントとすると、いわゆる言語治療は大きな位置を占めていないことが分かるでしょう。実際に言語訓練はまったく効果がなかったことが、開戦スピーチの直前の様子をみても分かります。では、何がジョージ6世を変えたのか、さらに考えましょう。
» 吃音に悩む人が変わるには
I have a voice
英国王のスピーチは、この一言のために作られた映画だといっていいくらいです。今後の吃音臨床でもっとも重要な意味をもつことです。「I have a voice」は、言葉を変えれば、「私は、国王としての責任を全うする」です。この責任感が、開戦スピーチ成功の一番の要因です。
戴冠式の準備の時、大司教から、ローグがスピーチセラピーの研修経験もセラピストの資格もないことを知らされたジョージ6世は、自分の吃音を治せなかったローグを責めます。
「お前は研修経験も資格もないが、度胸だけはある。戦争が迫る中、この国にことばなき王を押しつけた。私の家族の幸せを壊した上に、治る見込みのないスター患者を罠に陥れた。ジョージ3世のように狂気の王になる。狂った王、どもりのジョージ。危機の時代に国民を失望させる王」
このように責められている間に、ローグは戴冠式に使う王座に座ります。それを見たジョージ6世は怒ります。
「立て、王座に座ってはいかん」
「ただのイスだ。観光客の落書きもある」
「戴冠式用のイスだ。私の言うことを聞け、立つんだ」
「何の権利でそういうことを言う」
「神の権利だ。私は王だ」
「あなたは、王になるのは嫌なんだろう。そんな人のことばをなぜ聞く必要がある」
「I have a voice」
「そうとも、あなたは忍耐強く、誰よりも勇敢だ。りっぱな王になる」
「I have a voice」、ジョージ6世の凛とした声が響くこのシーンが、この映画のハイライトです。字幕には、「私には王たる声がある」とありますが、公開前の宣伝映像の字幕は、「私には伝えるべき言葉がある」でした。これが吃音の臨床の眼目です。
流暢に話せることが重要なのではない。どもらないように工夫してしゃべることに意味があるのではありません。その人の話の内容に大切な意味があるなら、どんなにどもっても人はその話を聞きます。でも、どんなに流暢でもその人の話が空疎なら、しゃべればしゃべるほど人は聞きません。
僕の親友の結婚式の経験です。感動的な結婚式の最後に、新郎の父親の意味のない挨拶が延々と20分以上続きました。聞き手の反応にお構いなしに話は続き、参加者みんながうんざりして、折角の感動の結婚式が台無しでした。
真実の言葉を語るときは、どもった方がいいと世界的作曲家の武満徹さんが名エッセー「吃音宣言」の中で書いています。詩人の谷川俊太郎さんとの対談で、僕が女性にもてた話をしたときに、「どもる人は、誠実だと誤解されるんだよね。とつとつと話す言葉に真実がある」と言いました。「私はあなたのことが好きだ」と、早口で軽く言われても相手に伝わらない。「す……………好きだ」の方が伝わると言うのです。
平和な時代の王であれば、「I have a voice」と言う必要はありません。ヒトラーが、イギリスの説得を無視して戦争が始まります。日本の僕たちが考える戦争と、ヨーロッパの人たちが考える戦争とは全然違います。沖縄の人たちが経験していることですが、地続きのヨーロッパでの戦争は、目の前を戦車が通り、人が撃たれて死に、建物が破壊されます。目の前で起こる大変なことを第一次世界大戦で経験しているヨーロッパの人たちが、また、その戦争に再び巻き込まれる。政府としては苦渋の選択です。
開戦のスピーチは、国王が、国民に説明し、勇気づけ、安心感を与え、みんなでこの困難を耐えようと訴えなければならない、大変重要な言葉です。結婚式のお祝いのスピーチではありません。空疎な「頑張ろう!」なんてことでは国民は納得しません。どれだけの人に影響を与えるかを知り尽くした上での国王としての言葉なのです。
国王としての立場、責任、地位、役割、それらの中から絞り出された、「I have a voice」です。ローグへの怒りを込めながら、しかし、大いなる決意を込めて、威厳をもっての「I have a voice」。
本当の王が誕生した重要なシーンです。
吃音治療に関するローグの基本的な考え
吃音に劣等感をもち、治したいと悩むどもる人や子どもに伝えたいメッセージは、言葉がどもるか、どもらないかの前に、「あなたには語るべき言葉があるのか」です。
2000年6月、NHKの『にんげんゆうゆう』という番組にスタジオ出演しました。柿沼郭アナウンサーが、「伊藤さん、最後に、吃音で苦しんできた人として、何か言葉について考えていることはないですか?」との質問に僕は話しました。
「吃音を否定的に考えて、これまで、すらすらしゃべることに価値があると普通に近づくことばかりを追いかけてきた。でも、どもりながらでも、その人の話を聞きたいと思えば、人はいくらどもっていても聞くだろう。たとえ、立て板に水のようにすらすらしゃべっても、空疎で内容がない話だったら、人は聞かない。どもるどもらないより以前に、あなたには言いたいことがあるか、言うべき内容があるかを、自分たちで問いかけたい。 どうしてもしゃべりたいことがあれば、どもる恥ずかしさや恐ろしさを超えて、人は話していくだろう。そして、それが結果として言語訓練にもなる。どうしてもしゃべりたいという気持ちが出るような、生活の質、充実した生活をいかに送るかが大切で、その中でしゃべりたい内容を育てる。それが大切なんじゃないでしょうか」
この番組を息子さんが録画して、それを観た落語家の桂文福さんが「吃音に悩んできた同じ仲間として共感しました」と電話を下さいました。以来、仲間としてのつきあいが続いています。落語家生活40周年記念パーティーの場で、特別に僕を吃音の仲間として紹介して下さいました。
「I have a voice」。国王として、「伝える言葉」があったから、その責任を重いものとして自覚していたから、開戦スピーチができたのです。
一方、どもる私たちやどもる子どもたちが苦しいのは、このように、重要な、伝えるべき言葉だけではないことも知っておいてほしいことです。
小学校の健康観察の時の「はい、元気です」や、「おはようございます」など、簡単で、あまり重要ではない言葉が言えないことです。幼稚園で、謝るときには「ごめんなさい」を言うようにと指導され、「ごめんなさい」の「ご」がどもるため言えずに、いじめられていたとの話を聞きました。
どうしても言わなければいけない言葉ではない、あるいは、言いたいことではない言葉で、多くの人は苦戦しています。作家の重松清さんも「語りたい言葉でどもるのはいいが、どうでもいいような言葉でどもるのは嫌だ」と言っていました。だから、重松さんも僕も、社交辞令の言葉だけが飛び交うパーティーや懇親会、雑談が嫌いです。ジョージ6世もパーティーや社交が苦手でした。
静岡でのキャンプの話し合いで、「どもりを、別に治したいと思わない」と言った小学4年生の片山悠太君は、健康観察の時、「か」がどもって言えないので、「か」を言わずに、「たやまゆうた、元気です」と言っていると言いました。するとある子は、「おはようございます」の「お」が出ないから、「はようございます」と言っていると、悪びれずに言っていました。子どもたちがつくった『どもりカルタ』に「サバイバル、はい、元気ですの、「はい」をとり」がありました。
語りたい、語らなければならない言葉は、どんなにどもっても語る。どうでもいいような言葉は、伝わりさえすればいい。このように柔軟に考えることが、吃音と共に生きるということです。
ナラティヴ・アプローチの実際~「吃音否定」から「吃音肯定」への語り~
言葉が生きる世界を作り出します。開戦スピーチの成功は、「どうしようもない王」という吃音否定の物語を、ローグを中心とした周りの人の力で、「やればできるかもしれない」という吃音肯定の物語に変えたことにあります。
「英国王のスピーチ」の吃音治療は、結果として、ナラティヴ・アプローチになっていたと僕は考えています。
ジョージ6世は、「どもっていては人から好かれない」「どもっていてはスピーチの成功はない」「どもっていると人は聞いてくれない」の物語を、子どもの頃から作り、自分で語り、それに捉われて、どもっていたら何もできないと思ってきました。
親などから影響を受け、世間から影響を受け、自分自身で語り続けてきたのです。この吃音に対するネガティブな、悲しい苦しい物語を、新しい物語に変えたのが、この映画なのです。誠実であれば、責任感があれば、どんな場であっても、どもっても出ていける、人間として成長できるという新たな物語を語ることができたのです。それがナラティヴ・アプローチです。
「英国王のスピーチ」には、物語を語り直すプロセスが描かれているといっていいでしょう。
「まあいいか」、吃音肯定の語りへ
映画の中で、吃音にまつわるネガティブな物語は再三再四語られます。吃音否定の物語が頂点に達したのが、1936年12月12日、王位継承評議会の場でひどくどもった夜、妻エリザベスの胸にすがって号泣するシーンです。
「クリスマスの放送は、失敗するに決まっている。戴冠式・・・、これは大いなる間違いだ。僕は王じゃない。将校でしかない。王なんかじゃない。すまない。情けない」
このような強固な吃音否定の物語を変えていくのは容易なことではありません。
エリザベスを中心にした家庭では、吃音はそのまま肯定されていますが、それだけでは十分ではありません。「あなたの素敵な吃音を聞いて幸せになれそうと思ったから結婚したのよ」のエリザベスの言葉も、ローグの「あなたは立派な王になる」の言葉も、繰り返し繰り返し語り続けられました。映画の中で語られた肯定的な語りを拾いましょう。
<妻・エリザベス>「私があなたと結婚を決意したのは、あなたの吃音が素敵だったから。あなたは立派な素敵な人だ」
<父親のジョージ5世> 「兄は、他人の夫人にしか興味がない、父親にまで嘘をつく人間だ。もし彼が王になれば、一年以内に国は滅びるだろう。それを救うのはお前だ。おまえは兄弟の誰よりも根性がある」
<後の首相・チャーチル> 「兄が離婚歴のある人と結婚をするからではなくて、不誠実で責任感に欠けている。戦争をする大事な時に、国民が本当に頼れる王が必要だ。あなたこそ、その、頼れる王だ」
<ローグ> 「あなたは忍耐強く、誰よりも勇敢で、あなたこそ立派な王になれる」
流暢にしゃべる社交的で聡明な兄よりも、弟のもつ誠実さ、責任感に価値を置き、弟の方が人間的に優れていると、父国王も、チャーチルら周りの人も語り続けるのです。
言われたそのときには受け止められなくても、たびたび言われるこれらのメッセージを受けて、ジョージ6世は、「責任感を持ち、国民の声に耳を傾け、国民に対して誠実に語りかければ、いかにどもっていようと、国王としての役割が果たせるのではないか」と思い始めます。戴冠式の準備の時の、「I have a voice」は、吃音を肯定して歩む第一歩でした。そして、映画の最後のシーンに象徴的な言葉が出てきます。
突然入った開戦スピーチ。40分前に、ローグも呼ばれ、準備をします。大声で怒鳴ったり、歌うように言うなど、スピーチの数分前でも、いろいろと声を出す試みをしますが、声が出ません。まじめに厳しい訓練をしても変化のない吃音のまま、ジョージ6世はマイクに向かわざるを得ませんでした。スピーチの40秒前です。
「結果がどうであれ、君の努力には心から感謝している」
これは、言葉を変えれば、「いくらどもっても、私には語るべき言葉があり、語る権利がある。国民はそれを聞く義務がある」との物語ができたからです。どもるときは、どもりながら話そう、どもっても責任を全うしようと、ジョージ6世が覚悟を決めました。どもりながら、一言一言かみしめながら、間を置いて、丁寧に語ることばが、国民には伝わっていきます。
セラピストであるローグは常に、新しい物語を彼に語らせようとしました。物語る材料は、セラピストであるローグにあったのではありません。「吃音があっても大丈夫」と、ローグがジョージ6世を説得したのではありません。ジョージ6世本人が語る物語の中から、材料を見逃さずにキャッチして、それをもとに物語る手伝いをします。
家族療法のナラティヴ・アプローチをする人たちは、本人や家族が語るネガティブな物語から、何かヒントになる言葉を逃さずにキャッチします。ジョージ6世は、ネガティブな物語ばかりを語りますが、その中で、これまでと違う、長所を本人が語る場面がありました。
父・ジョージ5世が死ぬ直前に、「あいつは、兄弟の誰よりも根性がある」と周りに言っていたと、ジョージ6世はローグに話しています。もっと早く父親が直接息子に話していれば、もっと早く肯定の物語に変えることができたでしょうに。
妻も、父親も、チャーチルも、ローグも、再三「あなたは、王になる資質がある」と言い続けた言葉がだんだんと身に染み入っていったから、ジョージ6世は、最後の土壇場にきて、「たとえ、どもって立ち往生しても大丈夫。最後まで読み切ることで、自分の王としての責任をとることができる。立派にできる」と、どもる覚悟ができたのです。「失敗したら失敗するまでだ」と腹をくくることができたのは、周りの人の力を借りながら、新しい物語を、ローグとジョージ6世が、一緒に作り上げてきたと考えることができます。
相手に向かって言葉を届ける
不安と緊張が高ぶって、放送室に行く長い廊下を歩く時、チャーチルが、自分も言語障害だったが、自分なりに克服したと言います。実は、チャーチルは吃音です。チャーチルの吃音はジョージ6世の吃音よりも有名で、欧米のどもる人なら誰でも知ってるくらいです。その映像を、僕はクロアチアでの世界大会で見ました。「私もマイクが嫌いだったんだよ」と、チャーチルがさりげなく言ったのも、勇気づけになりました。
飛び跳ねたり歌いながら声を出そうとしても効果がありません。いろいろやってもうまくいかない。もう駄目だと思ったとき、ローグが「聞いてもらう権利がある」と、ジョージ6世に言わせます。「権利がある、権利がある」叫ぶ内に、彼は、「私には、国民に聞いてもらう権利がある」と確信するのです。「聞いてもらう権利」という言葉、ディビッド・サイドラーの見事なシナリオです。 どんなにどもっても、聞いてもらう権利が私にはあると、自分に言い聞かせてスピーチの場に出て行きます。スピーチまであと3分というとき、国王としての覚悟ができていきます。そして、40秒前の、あの「結果がどうであれ、ローグ、君には心から感謝をしている」につながるのです。
ことばが人に届くとき
「頭を空っぽにして、私に話しかけろ。私だけに、友達として」
これがどもる人の話すときのポイントです。
僕たちはどうしても大勢の人の目を気にします。僕も、1000人を超える聴衆の前で講演をしたこともありますが、やはり怖い。1000人の聴衆を見るのではなく、会場の中のこの人に話そうと焦点を当てます。頷いてくれている人や優しそうな人を探します。その人一人に向かって話します。みんなに向かって話すことはできません。
教室で教員が子どもに語りかける時もそうでしょう。40人の子どもみんなをボヤーッと見て語るのではなくて、この子、この子とひとりひとり相手を見ながら、その子だけに話しかけるように話すと、他の子も聞くことができます。全体に焦点を合わせて語ったのでは、言葉は子どもに伝わりません。
ローグは、マイクに向かって話すのではなくて、マイクの向こうにいる私を見て、友達である私に話せと言います。世界の四分の一の人口の人が聞いていると考えると、気が遠くなりますが、友達であるローグになら語れます。その瞬間、ふっと力が抜けて、間をとりながら「重大な、困難に、直面して…」とスピーチを始めるのです。
ジョージ6世のスピーチは、YouTubeで聴くことができます。ゆっくりと、ゆっくりと語っています。聞き手にはどもっていないように聞こえますが、本人としては、どもっている意識はあったと思います。ブロックの状態にあるのが、絶妙の間となって聞き手には伝わっています。どもった瞬間を、間として生かしているのです。
» 劣等性、劣等感、劣等コンプレックス
最後に、この映画のもう一つの見所、兄と弟の劣等感の葛藤の話をします。
あの映画を違う角度から観ると、兄と弟の、劣等感の葛藤の映画だと僕は捉えています。兄はハンサムで、有能で、社交的で国民に人気があります。王にふさわしいと誰もが思っています。弟は、吃音のために引っ込み思案になり、消極的で、社交性がありません。兄とは全然違います。弟が兄に対して劣等感をもっていただろうことは誰もが想像できます。しかし、僕は、兄の方が弟に対して強い劣等感をもっていたと思うのです。
劣等性、劣等感、劣等コンプレックスの三つの違いを言ったのは、アドラー心理学です。
劣等性は、平均値より低いなど、ある程度客観的なものです。しかし、劣等性があるからといって、劣等感があるとは限りません。この人がなぜ劣等感をもっているのか不思議なくらいの人が劣等感をもっていたりします。劣等感は、主観的なものです。
劣等コンプレックスは、劣等性、劣等感を利用し、口実や言い訳にして人生の課題から逃げることです。人生には、「仕事」、「人間関係」、「愛」という3つの課題があります。仕事は、成人の場合は職業ですが、子どもの場合は、勉強や友達と一生懸命遊ぶこと、スポーツに打ち込むことなども含みます。人間関係は学校、クラス、地域での人間関係です。愛は、人を愛し、家族を作り、子どもを育てることです。
これを読み解くと、子どもの吃音臨床に展望が出てくると思います。兄は有能だけれど、ある意味軽いです。弟は、吃音の悩みの中から身についてきた、忍耐力、我慢強さ、誠実さがある。兄は人気があるので、何をしても好かれるが、弟は悪いことをしたら相手にされないからでもないでしょうが、誠実、真面目になっていきます。
みなさんがつきあう、どもる子どもに、真面目、誠実さを感じませんか。悩むということは、誠実だからです。他者に、自分の人生に、誠実でなければあまり人は悩みません。悩むことは悪いことではなくて、その人の誠実さの現れであると言っていいと思うのです。
兄が弟に強い劣等感をもっていたと分かるシーンがあります。
王である兄の山荘でのパーティに出席したジョージ6世は、仲がいいからこその苦情を兄に言います。「王たる姿勢で、公務を怠らず、愛人との生活に溺れず、仕事をしてほしい」。すると兄は、「彼女は愛人ではない。結婚するつもりだ。平民は愛があれば結婚ができるのに、なぜ王であればできないのか。お前は、スピーチの練習をしているとの噂を聞いたが、国民にスピーチしたいのか。弟が兄の私を王から引きずり落とそうとしているのか」と、弟のどもりを真似をします。
弟に対する強い劣等感がなければ、それまでとても仲がよかった兄が、弟の一番嫌がるどもる真似などしません。勤勉性、責任感、誠実さなどの人間性や、王の資質に関して、弟の方がはるかに優れていると、兄は弟に対して密かに、強い劣等感をもっていて、その劣等感が爆発したのです。
そして、劣等コンプレックスを使ったのは、どもる弟ではなく、人間性で劣ると劣等感をもっていた兄の方でした。弟は、人前に出て行かないとか友達を作らないとか、軽い意味での劣等コンプレックスは使ったけれども、最後の土壇場では使いませんでした。ジョージ6世を演じたコリンファースは、インタビューに応じて、ジョージ6世をとても勇敢な人物だったと語っています。
「彼自身は自分のことを勇敢だと思っていなかっただろうが、いざとなれば臆することなく恐怖に立ち向かったんだからね。国王になるよう育てられていなかったにもかかわらず、兄が王位を捨てると、黙って王位を継ぎ、決して運命を呪ったりしなかったんだ」
「私は退任をします。王を退きます。その理由を皆さんはご存知でしょう。国王として重大な責任と義務を果たすのが、愛する女性の助力がなければ私には不可能でした。この決断は難しくはなかった。弟は長く公務の研修、研鑽を積んできました。私が王を辞めたからといって、弟に代わったからといって、国民が一切の不利益を被ることはないでしょう。弟は立派に国王としての仕事をこなしてくれるでしょう」
兄は、自分よりも弟の方に王の資質があることを知っていた。そして、平和な時代なら自分でも国王としてやっていけるが、第二次世界大戦という大変な国難の中で、国王として責任を全うする実力が自分にはないと知っていた。だから逃げた。
「王冠を捨て、愛に生きる」なんて、一般受けするかっこいい言い訳を作り、国王は、離婚歴のある女性と結婚できないことを利用して、国王の責任から逃げたのです。
どもる子どもが、流暢に話せないことに劣等感をもつとしたら、劣等感や自信について子どもと一緒に、考え、話し合うことが必要です。表面的な、運動や勉強ができるなどよりも、信頼や責任感、誠実さの方が、人間の本質的に価値があることを知ってほしい。
どもる子どもの多くがもっている、まじめさ、優しさ、誠実さ、苦しくても逃げない忍耐力、工夫してサバイバルして生きる力こそ、幸せに生きる力になる。これらをもとに、「吃音否定」の物語から「吃音肯定」の物語に、一緒に変えていくことを、どもる子どもと取り組みたいのです。
この映画は、脚本家・サイドラーが、自分自身が吃音に苦しんできたこともあって、少しひいき目に弟を見ていたこともあるかもしれません。国民的人気の兄の伝記やエピソードはたくさん残っていますが、弟はあまり関心がもたれず、ほとんど伝記がない地味な王だったようです。
サイドラーは、長年、資料を調べ、脚本を書く時に、兄の方が弟に対して劣等感をもっていたのではないか、「王冠を捨てた恋」とかっこよく見えてもそうでないのではと感じたのではないでしょうか。少なくとも、映像からは、僕にはそのように感じられました。
そこに興味があって、脚本家サイドラーと話をしたいとインタビューを配給会社にお願いしましたが、手続きが大変なので断念しました。機会があれば聞きたいと思います。