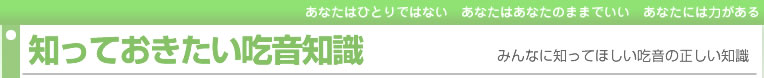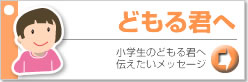米国吃音セラピー報告
『スタタリング・ナウ』2006.11.21 No.147
東京吃音ネットワークが主催し、伊藤伸二が講師として参加している「吃音ワークショップ」に吉田裕子さんは、2回参加している。初めて出会ったとき、アメリカの大学院に留学し、言語病理学を学びたいと熱く語っていた。大学院に合格し、学ぶ前にアメリカで吃音セラピーを受けたという。ぜひ詳しく紹介して欲しいとお願いした。アメリカの新しく始まった大学院の忙しい生活の中で、英文のメモや記録を整理し、翻訳するという大変な作業をして下さり、次のメールを添えて報告して下さった。現在のアメリカの吃音事情の一部を知る貴重な資料となった。
(スタタリング・ナウ編集部)
Intensive Stuttering Clinic for Adolescents
and Adults Who Stutter
Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio
2006年6月26日~7月13日
コロンビア大学大学院 吉田裕子
私はまだ1学期目で必修科目をとるのに精一杯で、とにかく時間に追われて、ほかの事は全くできない状況なのでこちらの状況はまだ把握できていません。でも、教授やスーパーバイザーに私個人の吃音に対しての哲学、“自己受容と吃音を素直に受け止め生きていく”ことを話しても、特に驚くこともなく、チャールズ・ヴァン・ライパー(注:私たちとも親交のあった吃音研究臨床の第一人者・1905~1994 )の話につながります。特に成人に関してのセラピーは結局クライアント自身で決断することで、その人それぞれに要求が違うと思います。私は伊藤さんの言うように、“治すこと”に興味はありません。それより、吃音について話したり、もっとカウンセリング的な、思想、論理療法を求めているので、専攻をカウンセリングに変更しようかとも正直考えたりしています。
でもやはり、自分の吃音を通して経験し感じているバーバルコミュニケーションの意味や、カミングアウトのインパクト(同性愛者のに共通するんですね)など、やはりコミュニケーションの分野にはいたいと思っています。たかが吃音、されど吃音。でも大切なことは皆それぞれに悩み、困難、コンプレックスがある。同じように思えます。そう思えるようになりたいです。
はじめに ▶
なぜこの時期にセラピーを受けたのか
きっかけ
プログラムの概要 ▶
14日間のセラピーの内容 ▶
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
9日目
10日目
11日目
12日目
13日目
14日目
私の個人的な感想と見解 ▶
このような練習、話し合いをする理由
随伴運動の削除について
随意吃、擬似連発の練習