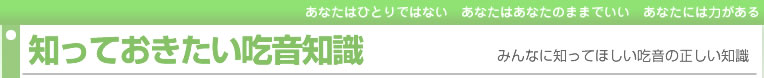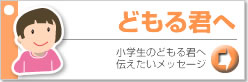私の個人的な感想と見解
» このような練習、話し合いをする理由
楽に吃る技法から吃ったときの対処法を何度も練習したが、これらは、「どもりを治す、吃らないように話す」ためのものではなく、「吃る自分と向き合って、吃る自分を隠さない。吃ることを恥じずに話す」ということが背景にある。
したがって全ての練習は、吃っているときに、またはその前後に、生体的に、心理的に自分の中で何が起こっているのかを適確に認識し、対応、処理していける能力を養うために行われていると言えるだろう。
» 随伴運動の削除について
身体を使って「無理に、強引に言葉を出すためにする随伴運動(頭を振る、足を蹴る、目を動かす、など)は徹底的に指摘される。他のクライアントのビデオを見てどんな随伴運動をしているかも観察する。正直、初めは、「他人の話し方を評価するのはよくないし、気分が悪い」とクリニシャンに打ち明けた。が、後になぜ自分の随伴運動を理解し、止める必要があるのかが理解できた。
一つの理由は、随伴運動によってより一層時間がかかり、本来言いたいことへのポイントから遠ざかってしまうということだ。また、随伴運動は吃らないように話すために身体の「反動、勢い」を使って言葉を出すため、吃音を、吃る自分を否定していると言えるのだ。したがって、随伴運動をなくすことは、素直に吃ること、吃る自分をさらけ出し、恥じず、話し方より話の重要性を相手に伝え、なおかつストレートに、直接的に早く話をすることにつながる。
» 随意吃、擬似連発の練習
わざと吃る、随意吃も単刀直入に言うと、「自分の本性を暴露する」ことになり、とても勉強になった。面白いことに、擬似連発をし始めると、本来の私の吃音が出てこなかった。「わざわざ吃る」ということは、「わ、わ、わ、わたしの名前は・・」と書いてある文をそのまま音読するような感じで、自分の話し方ではないような、誰かの真似をしているような感じだった。
ここで最も大切なことは、聞き手は私の本来の吃音と擬似連発を区別できない、ということだ。わざと吃るときは恥という気持ちよりはむしろ、「相手をあやつって、騙して情けや同情を招いている」ように感じ、気が引けたのも事実だ。もちろん、一番初めは個別セッションでクリニシャンの前で擬似連発をしたが、なんとも気分が悪く、恥ずかしかった。「もっとはっきり、大げさに吃って!」とのアドバイスも容易には実行できなかった。でも、よくよく考えると、この場合の恥とは、「本当の自分ではない」と思っていることから起こることで、でも実際私は吃る人間なのだと思うとできることなのだ。吃音の摩訶不思議を知らされた。
相手が本当の吃音と、疑似連発の吃音を区別できないのに、話す当人にとってはこんなにも心理的に影響するのだ。私たちの多くは話すとき、「どこまでどもりを隠せるか」に対し必死で、吃らなければ「成功、上手くいった」と判断しがちだ。これらはアメリカでは、“lucky fluency(たまたまのラッキーな流暢さ)” と呼ばれている。これはその名の通り、「たまたま」吃らなかっただけであり、確率の非常に低いラッキーな流暢さを追い求めるために毎分全エネルギーを使い、自己否定し続けていていいのだろうか?
それより、吃る自分をそのまま受け入れ、そのままで他人とコミュニケーションをはかる。はかれるようになる。そのために擬似連発が練習に取り入れられているように思う。