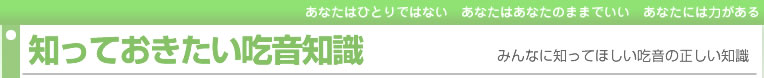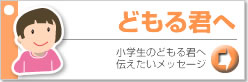プログラムの概要
2006年、6月26日から7月13日までの約14日間にわたる“夏季吃音集中セラピー”と名づけられているこのプログラムは、月曜日から金曜日は、9:00~17:00。土曜日は、10:00~15:00という、毎日フルスケジュールだった。
宿題・課題も毎日個別にでて、クリニックを夕方5時に出た後は夕食を済ませ、それらをやるのが精一杯で、あとは大学の寮で共同のシャワーを浴び、ぐったり寝るだけ。寮の前のベンチで若い学生達がはしゃいでいる中、私はというと涼しい風にあたりながら、毎晩自分の吃音や感情、人生を振り返り、数ページ書き綴り、また音読を録音したりと、私にとって貴重な時間だった。ついこの間のことだが、すでに懐かしく思われる。
今年の参加者は少々少なく、私を含め4人。他の3人は夏休み中の中学生・高校生の男子で、市外、州外から参加していた彼らは家族と大学の近くのホテルに滞在していた。私は大学の寮に滞在した。
クライアントと大学院生のセラピストの割合は1対1、もしくは学生が2人つく。そのほかにこれらの学生をサポートするST(スピーチセラピスト)2人(博士課程の大学院生や現役ST)がスーパーバイザーとなり、全般を指導するのが、ディレクターである、ガーベル教授だ。このプログラムの目的、ゴールは以下の3点だ。
①吃音について学び、追求する
②吃音について話し合い、受容していく
③吃音の行動、感情を修正、変革していく
午前中は、教授の講義で、生物学的なことば、スピーチの創られる構造や論理的療法などを学ぶ。午後は、個別に担当セラピストについて復習し、自分の吃音を分析する。
吃音にまつわる様々な感情(劣等感、無力感、恥、など)を全て書き出し、それらについて、「なぜそう思うのか」ということから、「どうすればその感情を改善できるか」をとことん話し合う。
実践的な練習、訓練としては、学生食堂などにいる一般の学生や、他の校舎に出向き、どもりに関するアンケートを実施する。その時は、意識的、意図的に吃る随意吃や、語頭を軽く繰り返す擬似連発を使って話しかけなければならない。当初は多少戸惑ったが、最終的にはそのアンケートをとる際に実行し、相手の反応を見ることができた。
そこで何を発見したかというと、吃音者自身が自分に正直に、そして自信をもってコミュニケーションをはかれば、そのポジティヴさが相手に伝わり、吃音が示すマイナス面を上回るということだ。逆に言うと、吃ることを恥じながら相手に接すれば、その自己否定がかえってマイナスの印象を与えてしまうということなのだ。
米国文化においては、相手に“自信”を見せることは非常に大切なことだが、日本ではこれはあまり強調されておらず、むしろ“ひかえめ”に振舞うことが美とされている。この自信とは、“我が強い”ことではなく、素直に自分を受け入れ、好きでいることなのだと思う。誰でも自分を否定し、いつも下を向いている人より、どんな障害、困難があるにせよ前向きに明るく頑張っている人のほうに惹かれるものだ。日米、そんなにアプローチの仕方は変わりなく、むしろ“自己受容”を最大視する傾向は同じだと感じた。
ただ、日本ではそういう練習の場(セラピー)がまだまだ普及されていないことを感じた。
4日間のセラピー期間中、6回のスピーチがある。セラピストとクライアント合わせて10名位の前で話すのだ。最終日の6回目のスピーチでは、「My Story」と題し、自分の人生をまとめ、そして今日このクリニックを去ってからどのように吃音と、人生と向き合っていくか、を発表する。最後のスピーチでは、私が誰よりもまして年上だったため、必然的に人生経験が長い分、長いスピーチになった。どういうわけか、緊張もあまりせず、スラスラと多少の冗談をまじえながら終えることができた。時折感情的になり、涙を流したが、最後まできちんと“観客”の目を見て話し続けることができた。