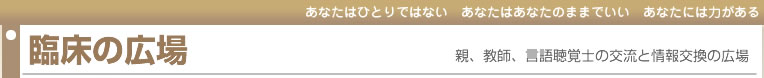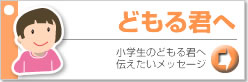バリー・ギター著「吃音の基礎と臨床」
詳しくは原著をお読みいただくとして、私の臨床との違いを明らかにするために、流暢性促進のスキルについてのみ引用する。「臨床家は、常に吃る子どもの流暢な発話を増加させるための努力をしなければならない」と、学童期・思春期の子どもの吃音緩和法と流暢性形成法が紹介されている。
■筆者の臨床アプローチは、吃音に対する否定的な感情を軽減させるために吃音を探究することから始め、その後、弾力的な発話速度、軟起声、構音器官の軽い接触、固有受容感覚といった、流暢性スキルを促進させつつ、一方で吃音を上手に扱うためのスキルを教えるものである。また年少の子どもには、自分の吃音についてオープンに話し合うことで、吃音に対する恐れや回避を軽減させる練習をし、その一方で、流暢性阻害要因への過敏性を減少させたり、いじめやからかいにうまく対処したりするスキルも学習させる。(P.367)
» 流暢性促進スキル
・ 弾力的な発話速度(Flexible Rate)
単語の発話速度、中でも第一音節発話速度を下げる。発話速度を下げると言語企図や発話運動の遂行に、より多くの時間をかけることができるため、吃音を効果的に軽減できる。吃ると予期する音節の発話速度のみを下げるため「弾力的な発話速度」と呼ぶ。臨床家が手本を示した後、子どもにその単語を「弾力的な発話速度」で発音させ、目標に近づいたらその発音を強化し、すべての音を練習させる。
・ 軟起声(Easy Onsets)
楽に柔らかく声を出す。まず声帯をゆっくりと振動させて声を出すと、吃ることなく滑らかに発声を続けられる。軟起声の教え方は、まず臨床家が様々な音を使いながら目標となる行動やスキルの手本を提示して子どもに軟起声のまねをさせる。
・ 構音器官の軽い接触(Light Contacts)
構音器官の強い接触は吃音を引き起こす。ある音韻で吃りそうだと予期したとき、その音韻を含む単語を言う前に、あらかじめ自分の構音器官を所定の位置に調節したり、吃ったときのことをイメージしながら練習したりする。構音器官を軽く接触させて子音を発音する。構音器官の力を抜き、呼気あるいは声の流れを途切れさせずに子音を発声する手本を子どもに示す。
・ 固有受容感覚(Proprioception)
口唇、顎、舌の筋肉の筋紡錘に存在する機械受容器から送られる感覚フィードバックは、発話時の筋肉の動きを調整する重要な役割を果たす。固有受容感覚からのフィードバックに留意させる。 構音器官からの感覚情報に意識的に注意を向けることを促進させると考えられる。子どもが固有受容感覚のスキルを正確に使えることが確認できたら、弾力的な発話速度や軟起声、構音器官の軽い接触のスキルと組み合わせる。このスキルの組み合わせを「スーパーフルーエンシー」と呼ぶ。
吃音を流暢な発話に置き換えるスキルを身につけた子どもは発話に対する自信を得、吃音の予期を流暢な発話の予期に変えるようにもなるだろう。このような子どもは吃音を予期したとしても、もはや構音器官を所定の位置に固定したり、吃音を生じさせる要因になる予期不安によって過度に緊張したりすることはなくなっているだろう。