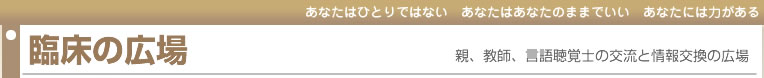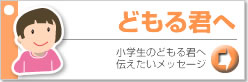ジョゼフ・G・シーアンの考え
私は、「治す努力の否定」の考え方をたいへん興味深く、うれしく拝見しました。あなた方が、吃音問題に関して、ひとつの方向を打ち出されたこと、またそこに到達するまでに費されたあなた方の努力に、私は敬意を表します。
興味深いお手紙をいただいたお礼の意味もこめて、1970年出版の私の著書『Stuttering:Research and Therapy』を別便で送りました。お読みになって、感想を聞かせていただけると大変うれしいです。
吃音の問題をオペラント条件づけによって研究している人々や、吃音は簡単に治ると宣伝する人々を含め、多くの吃音臨床家に対してあなた方が抱くのと同じ疑惑を私も感じています。
しかし私は、吃音の問題について悲観的ではありません。確かに吃音は、治らないかもしれません。一生吃音のままで過ごさなければいけないかもしれません。しかし吃音であるが故に、自分を卑下して生きていかなければいけない必要は少しもないのです。吃音が治らないからといって自分のすべてを諦めることはないのです。楽な吃り方で明るく生きる吃音者になることは、どの吃音者にもできることなのです。
そのためには、吃る自分を素直に受け入れることが大切です。そして、話したい語や話さなければいけない場面を避けないで生きていきましょう。吃音者が、自分の問題に正面から立ち向かい、吃りながらも話し続けていくとき、どもりの問題解決に明るい展望が開けるのです。それはこれまでの私たちの研究が立派に証明してくれています。
がんばりましょう。
(1977年)
随意吃の危険性
「ゆっくり吃らずに話す」は、それができなければ、本人がやめればいいが、「随意吃」はかなり危険を伴う。私も実際にしばらく練習をしてみたが、ますます吃るようになり、恐くなって途中でやめてしまった。随意吃の本来の目的は、吃音の恐怖や不安に向き合うことだが、「わざと吃らなくても」、普段の吃る状態を隠さず、あまり逃げずに話すという、ただ自分が吃る事実を認めればいいことで、「随意吃」をわざわざ練習することはない。
言語病理学第一人者、ウェンデル・ジョンソンでさえ失敗している。アメリカの言語病理学者、フレデリック・P・マレーは自著の中で、言語治療を受けたいという人にこうアドバイスしている。
「どんな吃音治療法でも、その全てがある吃音者にある程度の成功をおさめている。1900年の初め頃、アメリカで隆盛をきわめた悪評の高い営利的な吃音矯正所でさえも、一部の人には役立ってきた。チュレーン大学のジョン・フレッチャー博士は、「あまりにも多種多様な治療法で吃音がよくなるのは実に困ったことだ。もしそうでなければ、原因について、もう少し分かるだろうに」と言う。
吃音の治療について腹立たしいことの一つは、ある人には効く治療法が、必ずしも別の人にはうまく合わないという点である。
最も有名な例はこうだ。1930年代の初め、チャールズ・ヴァン・ライパーは、アイオワ大学でアルバイトでトラビス博士の運転手だった時、吃音があまりひどくて、ガソリンスタンドでも、ガソリンの注文に苦労した。ライパーは、しばしばブリンゲルソン博士の指導を受けながら、治療に数ヵ月間費やした。博士は、ヴァンライパーの不随意的なことばの詰まりに対する制御力をつけさせるため、随意的な吃音の練習をさせた。そうしているうちに顕著な改善が認められた。一年で彼は教職につけるまで上手に話すことを習得していた。
当時、ジョンソン博士もアイオワ大学にいた。彼は、この時までに吃音をかなり改善させてはいたが、それでもなお深刻な問題だった。彼はチャールズ・ヴァンライパーの吃音が消えて行くのを見てたいへん感激し、同じような治療プログラムを立てて自分もやってみた。ところが、彼の吃音がたちまち非常に悪化したため、話すことをまったく中止するよう指示され、一週間釣旅行をして、その間沈黙を守るようにと言われてしまった。
ある治療法が一人の人に効いても、別の人に効果がないのはなぜかという問いに対して、容易に答えることはできない。
『吃音の克服』(田口恒夫他訳 新書館)(P.234)
吃音は自然に変わっていくもの
吃音は、本来自然に変わっていくものだと私は考えている。吃り始めるのもある日突然に起こる。そして、ひどく吃ったり、治ったかのような「波」を繰り返す。この波は、何かのきっかけがある時もあるが、多くは自然の変化である。吃音は意図的にコントロールするものではなく、自然な変化に委ねるものだと、私は確信するようになった。医学が自然治癒力や免疫力に注目するように。
「吃音を治す努力の否定」から34年。私は吃音を治したり、ライパーの言う吃り方を学ぶという吃音コントロールの努力は一切しない吃音の取り組みを続けてきた。成人の吃る人のセルフヘルプグループの活動だけでなく、吃る子どもの指導にあたることばの教室の担当者や言語聴覚士など吃音臨床の専門家に対しても、そのように提言をしてきた。小学生から高校生を対象に「吃音親子サマーキャンプ」で18年間、吃る子どもとかかわってきた。吃る人のセルフヘルプグループでも、吃音親子サマーキャンプでも、「吃音を治し、改善する」アプローチを一切していないにもかかわらず多くの子どもや成人に大きな変化が見られた。
吃音の悩みから解放されただけでなく、吃音そのものにも変化が現れてきた。これらの実践の中で、吃音は「治す、改善する」を目指して取り組むものではなく、自然に変化していくものだとの確信を強くもつようになった。それは私自身の吃音の変化に素直につきあってもいえることだった。
学童期の吃音。思春期の吃音。吃音を治そうと必死になった21歳頃の吃音。治すことを諦めた頃の吃音。大阪教育大学の教員として学生に講義や大勢の前で講演をしたときの吃音。それらはどんどん変化していった。43歳の時、第一回吃音問題研究国際大会を開催した頃、私は人前で緊張して話をするときにはほとんど吃らなくなっていた。
しかし、55歳の時、石川県教育センターで、新人教員研修の講義で、「初恋の人」の文章を読んだとき、自分でも驚くほど吃った。吃っていても、吃ることが嫌ではない、動揺することもなく、不思議な、おもしろい体験だった。この日を境に、私は再び得意だったはずの緊張する人前でも吃るようになった。この現実に向き合い、私は「吃音は変化する」ものだと確信したのだった。