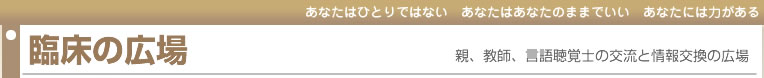アメリカの言語病理学
1930年代、アイオワ大学を中心に吃音の学際的な吃音臨床研究がなされた。現在の言語病理学はその流れにあるといえるだろう。ウェンデル・ジョンソン、チャールズ・ヴァン・ライパー、ジョゼフ・G・シーアンがその中心だった。
私は、ライパー、シーアンとは手紙を通して交流があり、私の「吃音を治す努力の否定」の主張に共感し、メッセージを寄せてくれたことがある。
1991年4月、自らの死期の近いことを悟ったライパーが、アメリカのグループNSPの機関紙『Lctting Go』に最後のメッセージを寄せた。
「私はこのほど心臓障害のため、主治医から、残された時間で身辺整理をするようすすめられ、その仕事を片づけました。しかし、やり残していることがひとつあります。私は、長年親しんできたこのニュースレター『Letting Go』ならそれを片づけるのに一役買ってくれるだろうと思っています。私は死ぬ前に、どうしても85年の人生で吃音について私が学んだことを、多くの吃音者たちに伝えておきたいのです。
私は、これまでに何千人という吃音者たちに接し、たくさんの研究に携わり、吃音の本を出版したり、多くの記事を書きました。重要なのは、私自身がこの間ずっと吃音を持っているという点であり、また私自身、リズムコントロールにリラックス効果にスロースピーチに呼吸法、精神分析や催眠術にいたるまで、ほとんどすべての吃音治療を経験してきたのです。しかし、どれもその成果を見ることなく、一時的に流暢さを取り戻したかと思うと、すぐに逆戻りするだけでした。それでも今では、吃ることがあっても、ほとんど気づかれないほど流暢に話せるようになっています。
私の人生が、とても幸福で成功に満ちたものになったのは、ある基本的な考え方との出会いのお陰でした。それを是非皆さんに紹介しておきたかったのです」
(セラピーのきっかけとなった老人と出会いの話)
» 私の提起に対するライパーからの手紙
「治す努力の否定」の問題提起をされたあなた方の手紙を実に楽しく読ませていただきました。その考えに賛成するかとの問いに、私は、はっきりと「イエス」とお答えします。
成人になってもひどく吃っている吃音者は、世界中のどんな方法を使ってもほとんど治ることがないと私は確信しています。遠い昔からある、このどもりの問題を、私は、長年研究してきました。
自分のどもりはもちろんのこと、何千人もの吃音者を診てきました。報道機関を通してさまざまな治療方法が公表されるたびに、そのうちのひとつくらいは本物があるだろうと期待して、その検討もしてきました。しかし、それらはいつも子どもだましであったり、フォローアップでのチェックが不正確であったりしたのです。このような情勢の中から、私たち吃音者は、おそらく一生吃って過ごさなくてはならないだろうという事実を認める必要が生じてきました。ぜんそくや心臓病を患っている人が、その治療が難しいという事実を受け入れているのと同様に、私たちもその事実を受け入れようではありませんか。そして、私たちがその事実を受け入れると同時に、どもりを忌むべき不幸なものとしてではなく、ひとつの考えねばならない問題として理解し受け入れてくれる人を増やすために、吃音者自身が社会啓蒙することが必要なのです。
しかし、吃音者はいつの日かなめらかに話せるようになるという望みをすべて捨ててしまわなくてはならないと言っているわけではありません。コミュケーションに全く支障を起こさず、気楽にスムーズに吃ることができるのです。そのためにはまず今後も吃り続けるであろうという事実を受け入れることです。そして、不必要に力んだりせずに、うまく吃るにはどうしたらよいかを習得することです。おおっぴらに吃ってみる勇気があるならば、どんな吃音者でもできることです」
» ライパーの「流暢性」の呪縛
ライパーに親しみと尊敬の深い思いを持ちながら、私は、ライパーが後に続く人々に大きな呪縛を残したのではないかと指摘しなくてはならない。「吃音は治らない」として受け入れることを重視しながらも、「流暢性」にこだわったことだ。
ライパーのこの主張は、自身の吃音の長い苦闘の歴史があるからだろう。ライパーはアイオワ大学で「随意吃」の提唱者ブリンゲルソンから指導を受けて、楽に吃るようになった。その経験が、彼の臨床に大きく影響を与えた。有名な吃音方程式は吃音の問題の把握に役に立つ一方で、後に続く人々に大きな縛りを与えたと私は考える。
それが「流暢性」だ。方程式の分子に吃音を悪化させる要因をおき、分母に吃音を軽減させる要因として、「士気」と「流暢性」をおいた。
ライパーと私の決定的な違いは、ここにある。私は分母には、「流暢性」に変えて「吃ってでもできた経験」をおく。
ライパーは「随意吃」を学んだことで、吃音の苦しみから解放されたが、私は、吃音矯正所で「随意吃」を教えられながら、使わずに、吃音セラピーを諦めた。その後は、一切の吃音コントロールはやめて、ただ「吃る事実を認め、吃りながら日常生活を丁寧に大切に生きた」。そして、治そうとしていたときは変わらなかった私の吃音は、どんどん変化していった。これは当時の私が経済的に貧しかったことが幸いしている。東京での生活を親に一切頼ることができず、生活費から学費まで学生生活の全てを稼ぐために、私はアルバイトをした。どんなに吃っても苦しくても、アルバイトをやめるわけにはいかなかった。吃音コントロールは全く役に立たず、怒鳴られ、恥ずかしさや不安や恐怖を感じながら、私は話していった。一方、当時創立したセルフヘルプグループの活動にも夢中になっていた。グループのために、私はどんな所へも出かけ、どんどん話していった。必死に生きる日常生活が、結果として言語訓練になったのだろう。吃音をコントロールしようとしていた時には、全く変化のなかった私の吃音は、「治すことにこだわらずに」生きる中で変わっていった。
「随意吃」などのセラピーのおかげで吃音が変化したライパーと、日常生活を必死に生きることで吃音が自然に変化した私。「吃音を受け入れよう」では共通しながら、ライパーは「楽に吃る」ことを指導できると考えた。これは、弟子ギターのスーパーフルーエンシーに引き継がれている。
果たして、吃る子どもや吃る人に「楽に吃る」ことは指導できるのだろうか。「楽に吃る」ベースには、ライパーが指導を受けたヴリンゲルソンの「随意吃」がある。ギターが「随意吃」を重視していることに、勉強不足の私は正直驚いた。「随意吃」が多くの吃る人に拒否され、受け入れられなかったから、ジョンソンやライパーの「楽に吃る」が出てきたのだと私は考えていたからだ。