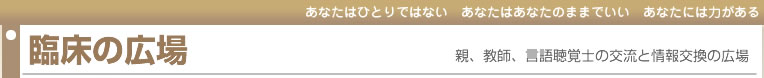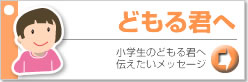吃音治療・吃音コントロールの難しさ
» 私の経験
私は小学2年生の秋から吃音に悩み、辛い学童期・思春期を生きた。その時、私を支えていたのは「いつか必ず治る」という思いだった。吃っている限り私の明るい未来はない。吃音が治ることだけを夢見た。吃っている間は「仮の人生」で吃音が治ってから私の人生が始まると思っていた。
21歳の夏休み、東京正生学院という吃音矯正所で、1か月は寮で生活し、一日中訓練に明け暮れた。その後3か月通院して、治す努力を続けた。
» 「流暢に話す派」と「流暢に吃る派」
私はこれまで、民間吃音矯正所を批判してきた。しかし、現在の世界の吃音治療の現状をみると、日本の吃音矯正所があながち大きな間違いをしたわけではないと気づいた。「必ず治る」と宣伝し過ぎたこと、呼吸練習の重視は問題だとしても、実際の吃音コントロール法は、今、オーストラリアやアメリカなどの大学で行われている「流暢性の緩和・形成」の治療法と大差がないのである。
「まず態度、口を開いて息吸って、母音をつけて軽く言うこと」
浜本正之の中央吃音学院で毎回唱和させられた。これは、後で紹介するギターの「吃音緩和法と流暢性形成法」と原理的にはほぼ同じなのには驚く。
日本の吃音矯正といわれるものは、1903年、東京小石川の伊沢修二(東京芸術大学の前身、東京音楽学校校長)の楽石社に始まる。伊沢の「ハヘホ」練習から始まる発声訓練は、後の吃音矯正所の原型となる。梅田薫、野中肖人、浜本正之、望月庄一郎、田澤嘉聲等の著作を読み返すと、お互いが批判し合っているものの、基本となる「ゆっくり話す」「軽く発音する」などは共通している。
1965年、私が最初に受けた吃音セラピーが、東京正生学院だったことを、今、とても幸いだったと思う。ここでは、アメリカで論争になっていた、「流暢に話す派」と「流暢に吃る派」がすでに対立する構図になっていたからだ。
東京正生学院の創立者、梅田薫・医学博士は、今、オーストラリアの大学で現に行われている、ゆっくりと吃音をコントロールして話す「わーたーしーはー」を徹底して教えた。一方、早稲田大学で心理学を学び、アメリカの言語病理学に精通するご子息の梅田英彦副院長は、アイオワ学派の「吃っても、どんどん話そう」という考え方を紹介し、「随意吃」を教えた。私たちは、ドイツ法・抑制法、アメリカ法・表出法と呼んでいた。
院長は熱心に吃音コントロールを教えたが、多くの人々は矯正所の中ではできても、日常生活で応用していくことはできなかった。また、一時的に効果があっても数ヶ月で再発していた。若い副院長の「吃っても、どんどん話そう」という考え方に私たちは惹かれていった。意図的に吃る、わざと吃るという「随意吃」は実行できなかったが、吃ってでも話していく態度は養われたと思う。
東京正生学院で、全く違う二つの考え方に出会い、それらを4か月、300人ほどと真剣に取り組み、議論した経験をとてもありがたいことだと思う。どちらか一方しか教えられなかったら、私は、「吃音が治らない」ことに諦めがつかなかったかもしれない。アメリカで論争になっている両方を同時に体験できたおかげで、私はその両方とも違う「治す努力の否定」をその後提起できたのだと思う。
そこでの「ゆっくりと、軽く発音する」も「随意吃」の「楽に吃る」もほとんど役に立たず、300人の吃る人たちは、教えられても実践ができなかった。一時治ったかにみえた吃音が何ヶ月後あるいは数年後、再び現れた。この「再発」という現象も、アメリカでも日本でも状況は変わらない。
日本では、「必ず治る」と教えられたために、「治る、治す」ことへの憧れは強いものになり、治らない場合、自分の「努力不足」を責め、治すことにとらわれる道へと落ちていったのだった。
私に残されたのは、「吃音が治らず、改善もされなかった」現実と、多くの吃る人に出会えたこと、そして吃音についての考え方として「恐れがあっても、不安があっても、吃ってどんどん話していこう」という、アイオワ学派の教えだった。
その後創立した吃る人のセルフヘルプグループでは、そのうち吃音をコントロールすることはしなくなった。吃っても話していく態度が根づいたのはアメリカの言語病理学の大きな遺産だろう。