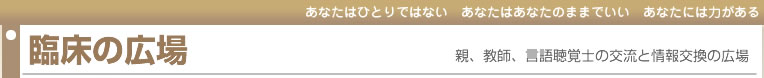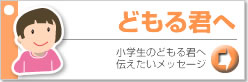はじめに
1974年、私は、吃音に悩む多くの人が「吃音を治す」ことにこだわり、治す努力に精神的、時間的、金銭的な多大のエネルギーを使っても成果がないどころか、ますます、吃音の悩みが深まった大いなる内省から「治す努力の否定」を提起した。
それから34年、昨年5月参加した第8回世界大会や、アメリカの言語病理学者バリー・ギターの翻訳書の出版(長澤泰子監訳・学苑社)で、アメリカを中心とした世界の最新の研究臨床が明らかになった。世界の吃音の臨床は70年ほどほとんど変わっていないことに驚き、改めて「吃音を治す努力の否定」を提起しなければならないと考えた。
吃音の臨床の大きな流れは「吃音の治療・改善」にあることは、翻訳書やクロアチア大会でも明らかである。だから、こっちの道もあるのだよと、選択肢を提起したい。「吃音の治療・改善」一色よりも、選択肢が広がる意味は小さくないだろう。
浄土宗の開祖・法然(1133~1212)は「選択念仏本願集」で旧仏教を「聖道門」として否定し、「浄土門」の日本の仏教を打ち立てた。
この区別に則して、アメリカ言語病理学を整理し、日本の、私たちの、吃音への取り組みの選択肢として、再度「治す努力の否定」を提案したい。
法然の「聖道門」と「浄土門」の区別
仏教の目的〈仏になる〉道は、一つではなく様々な手段があるという主張に対して、次の自覚に立って、法然は専ら念仏を称えることを主張する。
・日本は仏教の本国から遠いという自覚。
・修行を実践してゆく上で自分は無力だとの自覚。
〈仏になる〉とは、人間存在の不安や苦悩から根本的に解放されることだが、法然以前の仏教は、宗派を問わず、そのために、様々な努力目標を掲げていた。在家の人間には、寺院や仏像を造る、写経、僧への布施などを求め、人を殺すな、嘘をつくな、生きものの命を奪うなと教えた。これらは大多数の庶民にはできないことばかりだった。 出家者でも、よほどの精神的集中力と肉体に恵まれていなければ修行は難しく、〈仏になる〉ことは容易ではなかった。そのことを法然は、修行の不足ではなく、人間が本来持つ「煩悩」があるからだと言う。人間にとって「煩悩」の除去は不可能で、「煩悩」の存在を認めた上でいかにすれば〈成仏〉が可能なのかを考えた。
法然は徹底して自らも「凡夫」と認識し、「煩悩」に縛られている愚か者でも救われる仏教として、「信じて、ただ念仏を称えよ」と教えた。
源氏と平家が争う乱世の時代。法然の主張は、修行の難しさや、戒律を守れずに仏教と縁がないと考えていた人々に歓迎されたが、旧仏教からは、激しい反発を受ける。
法然の、一切の人間が救われる救済原理の根拠が「聖道門・浄土門」の区別である。旧仏教を「聖道門」と一括した上で、それを全否定した。釈尊が歩んだように、瞑想を繰り返し、心身をコントロールして深い智恵を獲得することで〈仏〉になる「聖道門」は、いかにすぐれた尊い教えであっても、釈尊の死から年月が経ちすぎ、感化力は衰えている。また、教えは難しく、いかなる修行によっても悟りを得ることは難しい。誰でもが信じさえすれば実行できる易しい行である「念仏を称える」「浄土門」が新しい仏教だと宣言した。
私は、「吃音の治療・改善」を目指す、吃音コントロールはきわめて難しいものだと体験的に考えている。日本の100年の吃音治療の歴史の中で、ほとんどの人が難しく実現できなかった方法でもある。アメリカの言語病理学と、技法の名称や表現に違いはあるが、1903年の伊沢修二等の方法と大きな差はない。100年たった現代でも吃音コントロールの方法は変わらない。長い年月の実践の結果、成果が上がらなかった吃音治療法を、私は法然の言う「聖道門」「難行」だと言いたいのだ。