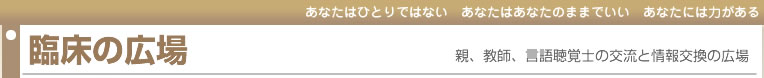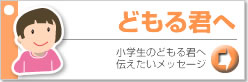「治す努力の否定」の理論的根拠
» 三つの事実
1.確実に治る、改善できる治療法はない。
2.治っていない人は多い。
3.吃音の悩み、受ける影響には個人差がある。
日本はアメリカと違って信頼できる、大学で臨床する吃音臨床家はきわめて少ない。ほとんどの日本の吃る人はアメリカ言語病理学の恩恵を受けていない。では、アメリカ人に比べて日本の吃る人が吃音に悩み、困難な状態にあるかと言えば、必ずしもそうではないだろう。日米比較はできないものの、世界大会などで世界の吃る人々と出会う限り差がない。ということは、言語病理学をもとにした吃音セラピーを受けなくても、日本の吃る人たちは、自分なりの対処法をみつけ、悩んだ時期はあったものの、自分なりの豊かな人生を送っているということになる。
私が「治す努力の否定」を提起した時、後押しとなったことがある。
1.私とセルフヘルプグループの仲間の変容
私自身が不安や恐れをもちながらも、日常生活を大切に生きる中で、どんどん変わっていった。吃音にあまり悩まなくなり、自分なりの人生を送るようになった。私だけでなく、セルフヘルプグループに集まった人の多くがそうだった。
2.一人の青年の実践
私が大阪教育大学の言語障害研究室に勤務していた時代、いわゆる重度な吃音で、舌を出す随伴症状のあった消極的な一人の吃る青年の吃音に、6か月取り組んだ。治す努力を一切しないで、「ただ、日常生活を丁寧に生きる」ことだけをこころがけ、彼の話すことから逃げる行動に焦点をあてて取り組んだ。その結果職場での生活態度が変わった。
目指したわけではないが、しばらくして、舌が出なくなり、吃音も軽くなった。この経験から、私の考えは、誰にでも通用するものだと確信した。
3.全国巡回吃音相談会
全国35都道府県38会場で相談会を開いて、3か月集中的に多くの吃る人に出会った。その時、吃音に悩む人だけでなく、吃りながら豊かに自分らしく生きている人とたくさん出会った。自分の経験からも、吃っていれば吃音に困り、悩んでいるはずだと思っていた先入観が崩された。
ほとんど吃音が目立たないのに、非常に悩んでいる人。かなり吃っているのに、平気で生きている人。吃音の苦労や悩みは、吃音の症状とは正比例しないことも実態調査で知った。吃音のコントロールができなくても、自分の人生を生きることはできる。いつまでも、流暢に話すこと、吃らず吃音をコントロールすることにこだわるより、吃音と共に生きる覚悟を決めた方がいい。そして、「治す努力の否定」を提案したのだった。
その後、34年間の取り組みの中でも、吃音のコントロールをしなくても多くの人が吃っていても、日常生活に支障なく生活ができるようになっていった。そして、自然に吃音そのものも変わっていった。吃音にあまり悩まなくなり、話すことから逃げなくなり、充実して生きる人に、吃音のコントロールは必要がないだろう。
終わりに
日本のことばの教室の実践のすばらしさ
法然の「聖道門・難行」と「浄土門・易業」にあやかって、吃音コントロールがいかに難しいものであるかを明らかにしたかったために、日本のことばの教室の素晴らしい実践について触れられなかった。近年、日本のことばの教室は、「吃音の治療・改善」の難しさに目を向け、治すことにこだわらない実践をしている所も少なくない。
治すことよりも吃る子どもの自己肯定に注目する研究も出てきた。私の知る限り、子どもの吃音の学習や、表現力を高める実践など、日本の実践はすばらしいと私は考えている。
アメリカの方法が紹介されることで、やはりことばの教室では、スーパーフルーエンシーの指導ができなければダメな臨床家だと思わないで欲しい。せっかくのいい実践から吃音コントロールに向かわないで欲しいと願うばかりだ。
長年の吃音研究を誠実に続けてこられた、水町俊郎愛媛大学教授との共著で、『治すことにこだわらない、吃音とのつき合い方』(ナカニシヤ出版)を出版した。吃音コントロールとは違う実践をまとめた実践集もあわせてお読みいただきたい。
・『吃音と向き合う、吃る子どもへの支援~ことばの教室の実践集』
(日本吃音臨床研究会発行)