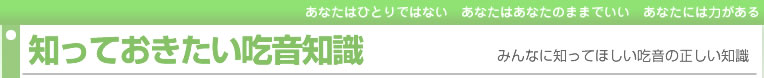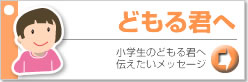吃音治療の歴史
» はじめに
吃音の原因については、現在のところ定説はない。したがってすべての吃音者に有効な治療法はまだ確立されていない。しかし、吃音の原因について、研究者、臨床家が自説を正しいと信じてきたように、治療に関しても自らの開発した治療法が唯一絶対のものであると主張する臨床家は多い。これまで公開されてきたさまざまな治療法の中から主なものを取り上げ、その利点、問題点を探っていこう。
» 対症療法
1.対症療法の流れ
伝統的な抑制法としての対症療法は、1800年代、ヨーロッパを中心に行われてきた。吃音の原因は、発語・呼吸器官に障害があるとし、呼吸および発声練習をすすめた。
伝統的な治療法のほとんどは、いかに吃音を抑えるかを目的とした。吃ることを抑え、それによって流暢な話し方を確立し、吃音を治療する。しかし、この方法では、一時的に流暢に話せても、また元の状態に戻ってしまう逆もどり現象に悩まされた。これは、民間吃音矯正所へ行った多くの吃音者が経験を通して知っていることである。
1930年になって、アメリカ・アイオワ大学のスピーチクリニックにおいて、医学・教育・心理学の領域から組織的な調査研究が進められた。その中心となったのが、ブリゲルソン、ウェンデル・ジョンソン、チャールズ・ヴァンライパーであった。彼らは吃らずに話すという抑制法を真っ向から批判し、吃音に対する恐れや回避をなくすことの重要さを強調した。吃らずに話すという抑制法とは逆に吃ることを奨励し、どんどん話すようにし、吃った状態を客観的にとらえ、吃り方を徐々に変えていこうとした。抑制法と対比し、表出法ともいわれる。
2.抑制法
a.注意転換法(ディストラクション法)
昔から民間矯正所で行われてきた方法は、ほとんどこのディストラクション法だといってよい。
・ワ-タ-ク-シ-ハ-と歌うように話す
・ンワタクシハ ンアオナデス と語頭にンやウの音をつける
・エート、エートなど連係語をつけて話す
・手を振りながら、指を折りながら話す
これらの手法を使うことによって、吃るかもしれないという不安や恐れから注意をそらせて、吃音を抑制する方法である。つまり、「吃ってはいけません。たとえ不自然な話し方であっても、身振りをつけて話そうとも吃ってはいけません。とにかくどんなことをしてでも吃ることはやめなさい」ということで、吃ることは悪いことだから、絶対に避けるべきであるとの考え方にむすびつく。
民間矯正所の全盛時代、日本各地で、吃音矯正家が自分の矯正法の優位性を主張した。そのほとんどがこの注意転換法であり、矯正家の数ほど治療法があった。
矯正家でなくても、吃音者自身が長年の生活の中で吃って困ったとき、なんとか通り抜けてきた経験を持っている。エート、アーなどを入れたり、指を折ったりすることは誰もが経験する。吃ったときになんとかそこから抜け出そうとしたテクニックが、そのまま治療法になったと言っても言い過ぎではない。これらは一時的に効果があったとしても、その効果が長続きしないのが特徴であり、たとえ吃音が治ったと思えても、多くは再発する。アメリカではスピーチセラピストの倫理規定の中でこの注意転換法は禁じられているほどである。なぜなら、速効と劇的な効果があることがあり、麻薬依存のような状態になり、効果は一時的なものなので、効果がなくなったときの心理的悪影響は大きく、吃音への恐れや不安をさらに大きくしていく可能性があるからである。また、注意転換法は、慣れてくると効果が失われるだけでなく、使った方法が随伴症状として組み込まれ、症状そのものを悪化させることもある。話すときに舌や口型に注意するあまり、話すときに舌が出るようになり、その後は吃ることそのものより、舌が出ることが大きな悩みとなったという実例がある。
b.暗示法
ことばによる言語暗示、薬物(にせ薬)を用いる暗示があり、誰がかけるかによって他者暗示、自己暗示と区別される。「あなたはどもりではない」「あなたのどもりはもう治った」と他者暗示による催眠療法は、催眠療法家の宣伝の中に適応症例のひとつとして、吃音が入っているので、現在も使われていると思われる。
また、かつての矯正所の治療の中でも、呼吸練習・発声練習と同様に暗示の効果も重視された。梅田 薫(1958年「吃音の研究と療法」)は、次のように言う。
「吃音や神経症の諸症状のようなものは病的観念がなくなれば、精神は平静となり、そのまま治ってしまう」とし、次のような暗示をすすめた。「おおいに治った、治った、治った」「もう吃らない、楽に言える」
被暗示性が強く、催眠にかかりやすい人は、この暗示の効果がある場合がある。しかし、多くの場合、一時的なものである。自分は決して吃らないと確信を持って、自分に言い聞かせることのできる間は、吃ることも減少するかもしれない。しかし、心の奥底で吃音に対して否定的な感情を持っている限り、何かの失敗やきっかけで確信がゆらぎ、元の状態に戻ってしまう。一度は治ったと思える経験をしただけに、その後の落ち込みはかなり大きい。
c.弛緩法(リラクゼーション法)
吃っているとき、吃るかもしれないと不安な状態にあるとき、心身に緊張がみられることはよく知られている。反対に心身がリラックスしているときは吃ることが少ない。たとえば、小さい子どもや犬に話しかけるとき、お酒を飲んでリラックスしているときなどは、あまり吃らない。当然、これらの手法を用いて心身の緊張を弛緩させる治療法が考えられた。具体的な方法として、ジャコブソンの漸進的弛緩法、シュルツの自律訓練法などがある。これらの方法は、吃音治療に直接、単独に使われても効果はなく、行動療法などのプログラムの中に組み込まれている。つまり、弛緩法を用いつつ、その他の対症療法を行おうとする。
3.修正技法(アイオワ学派)
伝統的な抑制法に対して、アイオワ学派の人々は、
「この方法は、吃音者に『つえ』を与えるにすぎない。急速に吃音が治っていくということは、突然の再発の前兆である」と批判した。
「吃ってはいけない。不自然な話し方であっても、またどんなことをしてでも、とにかく吃るのだけはやめなさい」
この抑制法は、吃音の中心問題であるべき「吃ることへの恐れ」を減らすどころか、強化することになると主張した。アイオワ学派の人々はこう主張する。
「どんどんしゃべって吃りなさい。ただし、はたから見て異常だと思える吃り方をできるだけ少なくして」
吃ってでも話すことを吃音者にすすめ、吃ることへの恐れを吃音問題の中心だと考え、吃ることを隠すことより、吃音をオープンにすることによって、その恐れを減らそうとしたが、具体的な方法は、人によって少しずつ違っていた。
a.ブリンゲルソンの随意吃
・もし、吃音が体質的なものなら、それを持ったまま生きることを学ぶ必要がある。
・吃音に対して、本人が異常に反応することがなくなれば、聞き手も異常に反応することが減るだろう。
ブリンゲルソンはこのように考え、吃音者が自分の吃音を受容し、それに対して客観的な態度をとることの重要さを主張した。ブリンゲルソンのいう客観的態度とは、自分の吃音について他人と自由に話し合えることであった。それを効果的にするために集団療法を取り入れた。他人の吃っているのを見、自分も吃り、互いに吃り方や吃ったときの感情について話し合うことによって、自分の吃音を客観的にとらえることができるようになるというのである。ブリンゲルソンは、吃りそうだと思うことばの第一音を自発的に連発すること、たとえば、「タマゴ」と言いたいときに「タ、タ、タ、タ、タ」と繰り返す吃り方をすすめ、「随意吃」と名づけた。この方法は、吃音者の吃ることへの恐れを、吃ってしまうことによって減らすことでは効果があったが、吃音者の抵抗が強かった。さらに、たとえ吃ることへの恐れが減っても、吃症状そのものにはあまり変化がなかった。吃音に対する客観的な態度を育成すると同時に、吃症状そのものを変えていく努力もなされた。随意吃を絶対的な治療法として使うことの危険が早くから指摘されたものの、後のジョンソンやヴァン・ライパーに大きな影響を与えた。
b.ジョンソンの知覚と評価の再学習
ジョンソンは随意吃を「正常な非流暢さ」というとらえ方で活かした。ブリンゲルソンと同じく、ジョンソンも吃ることへの恐れが吃音の中心であると考えていた。吃音は吃ることを予期するために起こる回避反応であり、吃ることを避けないことが吃音を減少させることになると考え、吃りそうなことばを軽く、楽に繰り返すことをすすめた。つまり、吃ることを恐れて、あわてたり、緊張したりせずに、単純な吃り方を続けることによって、流暢ではないけれども正常な話し方「正常な非流暢さ」が身につくと考えた。
ジョンソンはまた、非吃音者にも非流暢性があり、吃音者と非吃音者との差は、自分の非流暢性を気にするかどうかにあり、吃音者が自分のことばに対して持っている特別なとらえ方と感情が吃音を起こさせると考えた。ジョンソンは、吃音者が自分の吃音について語るときに使う不適当なことばに注意を向けさせた。たとえば、「話そうとするとき、くちびるをきつくしめてしまう」とは言わずに、「私のくちびるは、きつく合わさってしまう」と言うことを指摘した。そうすることによって、うまく話せないのは、自分自身がしている行為そのものであることを分からせようとした。この知覚と評価の再学習を基礎に、自らすすんでいろいろな場に出ていき、話すことが重要であると強調した。このときに、自発的に軽く、楽に吃ることをすすめたのである。
c.ヴァン・ライパーの流暢な吃音
ヴァン・ライパーは、吃音は大部分学習された行動であると考えた。吃音の原因はいろいろあるにせよ、吃音を強化し、発展させたのは自分自身であると考えた。その学習されたものの大部分は、予期不安からくる回避反応とさまざまなフラストレーションであるという。ヴァン・ライパーは、学習によって身につけたこれらのものを、練習によって取り除こうとした。つまり、習慣になってしまっている吃るときに起こるさまざまな心理状態や、はた目に異常と思える行動を、練習によって少なくしていこうとした。
彼は、目的を、吃らずに話すことではなく、流暢に吃ることにおいた。気楽に話せる場面、たとえば成人吃音者のグループの中などで、自分の苦手としないことばの言い出しを軽く繰り返したり、引き伸ばしたりする練習をする。慣れるにしたがって、実際の生活場面で苦手なことに対しても同様の話し方をする。このような練習や経験によって吃ることに対する恐れを減らそうとした。流暢に吃る方法として、ヴァン・ライパーは一連の実際的な方法を開発した。
イ.準備的構え
吃音者は話さなければならないとき、次のような準備的構えすることに、ヴァン・ライパーは気づいた。
・話そうとして発語器官の筋肉を緊張させてしまう。
・発語器官を固定したままで、言わなければならないとあせる。最初の音が言いにくい音であると、どうしても言わなければならない最も重要な音だと考え、異常に身構えてしまう。
・最初の音をあらかじめ構音してみるくせがある。つまり「タ」と言おうとするとき、歯茎に舌をもっていく。
吃るかもしれないと恐れている語を言う直前に、吃音者はこのような準備的構えをしているのである。ヴァン・ライパーは、吃り方を変えるのには、このときが最も良いタイミングだと考えた。そして、それらの準備的構えをなくすために新しい準備的構えを練習すればよいと考えた。たとえば、発語器官の筋肉の緊張を緩め、苦手な第一音を意識せず、不適切な準備をしないで、すぐ発音するという方法である。
ロ.引き伸ばし法
新しい準備的構えがうまくできず、これまでのように吃り始めたとき、単純な引き伸ばしを行い、言い切るようにする。唇や舌が過度に緊張しブロック(難発)の状態になったとき、無理にことばを出そうとしないで、その緊張を意識的に緩めながら、軽く引き伸ばすようにして発音する。
ハ.解消法
新しい準備的構えができなかったり、引き伸ばし法で単純な引き伸ばしができなかったとき、無理に声を出そうとしないで一旦休止し、自分のしていることを分析し、反省し、もう一度言い直す。言い直すときは、流暢に話さなければならないというのではなく、吃り方に少しでもよい変化があればいいのである。
準備的構え-引き伸ばし法-解消法、この一連の方法は、もちろん対症療法のひとつではあるが、一種の心理療法の役目も持っていた。たとえば、解消法で自分の吃音と向かい合い、分析することは、吃音と直面することになり、これは心理療法の基本になるからである。吃音者がことばにつまったとき、吃ることへの恐れや、話したいが吃るから話さないという心の中での葛藤や、異常な話し方を変えていくということは、吃音者が自分の吃音に対する洞察を深めるチャンスとなるのである。
» おわりに
対症療法を中心に説明してきた。対症療法に対して非対症療法があり、精神分析法、来談者中心療法、行動療法、森田療法などが使われている。吃音の臨床家は、成人吃音には非対症療法だけでは十分な効果が得られないとして、対症療法と併用する場合が多い。
アメリカの著名な言語病理学者で、恐らく世界で一番多い臨床経験をもつチャールズ・ヴァン・ライパーは、吃音者にこう言います。
『成人になってもなお吃っている吃音者は、世界中のどんな方法を使ってもほとんど治ることがないと、私は確信しています。
遠い昔からあるどもりの問題を、私は長年研究してきました。自分のどもりはもちろんのこと、何千人もの吃音者を診てきました。報道機関を通じて様々などもりの治療法が公表されるたびに、そのうちのひとつくらいは本物があるだろうと期待して、その検討もしてきました。しかし、それらはいつも子どもだましであったり、その結果の確認が不正確であったりしたのです。
このような状況の中から、私たち吃音者はおそらく一生吃って過ごさなくてはならないであろうという事実を認める必要が生じてきました。
ぜんそくや心臓病を患っている人が、その治療が難しいという事実を受け入れているのと同様に、私たちもその事実を恥ずかしがらずに受け入れようではありませんか』
現在も新しい治療方法だと宣伝する臨床家は後を断ちません。その効果・限界は、従来からの伝統的な治療法の効果・限界と大差がないように思われます。近い将来、劇的に効果のある吃音治療法が開発される見込みは薄いでしょう。