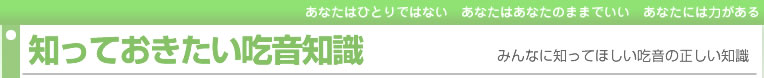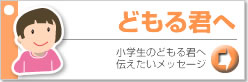吃音(どもり)とは何か
» はじめに
吃音は、長年の調査・研究にもかかわらず、その原因や本態において分からないことが多く、依然として謎に包まれている。しかし、明らかになっていることもあり、分かっている範囲だけでも知っておくことは、《吃音と上手につき合う》ために必要なことである。
» 吃音の定義
吃っていると聞き手が感じても、本人は吃音と思っていない場合がある。一方、周りからは吃っているとは気づかれないほど流暢に話す人が吃音に悩んでいる。
失語症者の中にも吃音によく似た言語症状がみられる。また、「あわてたり、びっくりしたりした時など、誰だって吃りますよ」と言われることがある。これらは、吃音とは呼ばない。失語症の場合は吃様症状と呼ばれる。非吃音者のなめらかでない話しことばは、正常な流暢さであるとウェンデル・ジョンソンは言う。吃音とは何か、人によってその定義は異なるが、現時点での主流の意見は次のようなものである。
1)音を繰り返したり、つまったりするなどの明確な言語症状がある。
2)器質的(脳や発語器官等)に明確な根拠が求められない。
3)本人が流暢に話せないことを予期し、不安を持ち、悩み、避けようとする。
» 発吃の時期
吃音はほとんどの場合、幼児期に起こる。成人してから吃り始める例はあるが、ごくまれである。ジョンソンの研究では4分の3が3歳2ケ月以前に発吃している。
中学生になってから吃り始めた人、成人になってから吃り始めた人に最近は時々出会うようになった。また、交通事故の後、直接の後遺症ではないが、退院後の孤独な生活を経て、再び社会に出たとき周りの目が気になり始めてから吃り始めた例。不況のリストラに脅えて、50歳になってから吃り始めた例もある。それらの人は、それ以前全く吃らず、むしろ流暢であったという。吃症状は、幼児期に発吃している人と変わらない。
» 発生率と性差
吃音の発生率は、人口の約1パーセントという数字を世界各国共通に出している。
しかし、多くの調査は幼児期から思春期の吃音を対象としており、成人吃を含めたものではない。隠そうと思えば隠すことができ、隠したいと考える人が成人吃音者には少なくないだけに、正確な数字を出すことは不可能である。1パーセントから5パーセントと推定する学者もいるが、もっと少ない可能性もある。
また、吃音は男子に圧倒的に多く、男女比は、2対1から10対1と言われる調査結果があるが、3倍以上となるのは確実である。
» 吃音症状
日本音声言語医学会では、吃音検査法を確立するための検査項目の検討が続けられている。吃音症状をかなり詳しく分類している。しかし、詳しすぎる検査は、かえって問題把握を難しくしたり、症状にとらわれすぎる可能性がある。あまり詳細なチェックは必要ないが、吃音症状にどのようなものがあるか、次に示すような項目程度は知っておいてよい。専門用語では少し違った表現になっているが、一般的に分かる表現にした。
ア 言語症状
語を繰り返したり、つまったりする音声言語面に現れる症状で、おおざっぱには三つに分類できる。
1.連発(語音・音節の繰り返し)
「タタタタマゴ」のように音を繰り返す症状で、吃り始めた初期にみられるものである。これは誰でも吃っていることが分かる。
2.伸発(引き伸ばし)
「タ-マゴ」のように音を引き伸ばす言い方で、これも初期にみられるが、成人になるにしたがって緊張が加わる。
3.難発(ブロック)
「・・・・・・タマゴ」のようにつまって音が出てこない。ブロックといわれる成人吃音の多くにこの難発がみられる。最初の一音が出れば後は割と話せるので、周りの人は吃音だと分からないことが多い。本人も言いやすいことばに言い換えたり、黙ったりするので、よけいに分からなくなる。「タタタタ」と連発するものだけが吃音だと思っている人は案外多い。吃音が理解されにくいわけである。
イ 随伴症状
吃っている状態から抜け出すためにしようとした動作が身についてしまったものである。瞬き、目をこする、体をのけぞらす、手足を振る、足をばたつかせるなどがある。当初はそれらが効を奏しても、次第に効き目が薄れ始め、他の動作を模索する。やがて動作だけが残り、吃るたびにその動作を起こしてしまい、吃ること以上に本人を苦しめることになりかねない。吃ると舌が出る人がいて、その人は吃ってもいいが、舌が出ないようにしたいと、舌が出ることに悩まされた。
ウ 情緒性反応
吃るかもしれないという予期や不安により、また、吃ったことによって、表情や態度に変化が起こる。自分の吃音にどの程度敏感になっているかによって、この反応は変わる。
表情 赤面、こわばる、当惑
視線 そらす、チラッと見る
態度 虚勢、攻撃的態度、おどけ、恥ずかしそうな態度、落ち着かない
行動 恥ずかしそうに笑う、いらつく、せきばらいする
話し方 先を急ぐ、小声になる、単調になる
エ 工夫
吃らずに話そうとするために行う工夫
延期 間をあける、回りくどい表現をする、「アノ-」「エ-」などを入れる
助走 話すスピードを速める、語音に弾みをつける
解除 一度話すのをやめて、再び試みる
オ 回避
吃音症状が悪化し、吃音に対する意識が強まるにつれて、回避が始まる。この回避が強まれば強まるほど吃音は悪化していく。
話す場所や相手を避ける
中途で話をやめる(考えるふり、分からないと言う、黙る)
相手が言ってくれるのを待つ
ジェスチャーを多く使う
ことばや語順を言い換える
» 適応効果と一貫性
同じ文を繰り返し読むと、1回目よりは2回目、2回目よりは3回目と吃り方は軽くなる。これを適応効果と言う。だから朗読が当たるとき、何かの発表のとき、練習するのはそのためである。しかし、研究によるとこの効果も限界があり、4回を過ぎると、後はあまり差がない。繰り返しても、1回目も2回目も同じ語で吃る現象を一貫性と言う。従来は、適応効果が高いほど、吃音を変化させる可能性が大きく、一貫性が高いほど、吃音の程度が重いと考えられ、吃音調査の中に取り入れられていた。現在、アメリカでは、根拠が薄いとの理由であまり使われていない。
» 波
調子のいいときと悪いときの波があるのが吃音の特徴とも言える。吃る人本人も、「最近調子が悪い」とか、親は、「しばらくほとんど吃らなかったのに、最近ひどいんです」などと言う。吃音に波があると知っておくと、いたずらに症状の変化に振り回されなくてすむ。
この波は、時間により、季節により、また短期、長期とあらわれかたはさまざまである。 吃音のこの波現象が、吃音の受容を難しくさせている要因のひとつだろう。調子がよくて吃らない時が本当の自分か、よく吃るときが自分なのかつかめない。
» ディストラクション効果(注意転換)
民間吃音矯正所である人が吃音が治ったと言っている。そこは効果があるのかと問われることがある。「わーたーくーしーはー」などとそれらの矯正所では教える。かなりの効果があり、しばらくは吃らない。手を振りながら話したり、リズムをつけながら話したり、不自然な調子をつけて話したりすると、吃らなくなる現象と同じである。これをディストラクション効果と言う。一部の民間矯正所では、ディストラクション効果に頼って治療している。一時的によくなっても、その効果は長くて4カ月ほどしか続かない。注意転換も習慣化されてしまうとその効果を失うのである。英語の時間、日本語は吃るが英語のリーディングは吃らないという人がいる。これもディストラクション効果の一種である。ネイティブ並に話せるようになると、日本語同様吃るようになる。
このディストラクション効果の危険なところは、使った方法が随伴症状に組み込まれてしまうことである。また一時的にも治ったと錯覚することで、「吃音は治る」という考えに縛られるおそれがある。アメリカでは、このディストラクション効果だけをねらった治療は禁止されているほどである。
» 吃るときと場面
歌や謡曲、詩吟などでは吃らない人が多い。「どもりの小唄」ということばがあるくらいである。が、なぜそうなのかは分からない。しかし、この事実を利用して吃音に活かしている人は多い。筆者の父は重度な吃音で、それを治すために謡曲を習い、その師範になった。生業とするほどに打ち込んだが、確かに謡曲では全く吃らないし、それをお弟子さんに教えている時は比較的吃らなかった。しかし、家族と話すときはひどく吃っており、亡くなるまでかなり吃っていた。
親しい人と話すときにはほとんど吃らないが、大勢の前では吃る人と、反対に緊張する場面では吃らないが家族や親しい人の前では吃るという人がいる。朗読の方がいい人、会話の方がいい人、差の全くない人などさまざまである。
朗読の難しい人でも、誰かと一緒に読むと吃らない。これを利用した治療法の一つとして、斉読法がある。朗読が苦手なこどもにこの斉読法は臨床場面でよく使われる。