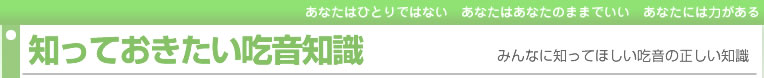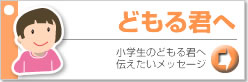吃音の原因について
» はじめに
「ある本で、『どもりは母親がつくる』と書いてあるのを読みました。母親の育て方が悪かったから私はどもりになったのです。今は、母親を恨んでいます」
「どもりは遺伝するんでしょう。自分の子どもがどもりになるかと思うと不安です」
「どもりは横隔膜のけいれんから起こると聞き、呼吸練習とその呼吸に合わせた発声練習をずっとしています。これでどもりは治ると思います」
「左ききを右利きに治すとどもりになると、新聞記事で読んでショックを受けた。無理やり利き手を変えた親が憎い。今は左手で文字も書くようにしている」
吃音の原因についての誤った認識、偏った認識から、このように間違った対処の仕方や、思い込みで、新たな悩みが発生する。
吃音の治療は、吃音の原因を探り、仮説を立てることによって始まる。したがって、原因についてどのような仮説を立てるかによって、治療法(対処法)は違ってくる。呼吸や発声器官に原因を求めるところから、あの伝統的な呼吸・発声を中心とする吃音矯正法が考えられた。
なぜ吃るようになったのか? 原因は何なのか?
素直な疑問を持つのは当然だが、吃音の原因について正しい知識を持っている人は、それほど多くはない。いたずらに不安を持ったり、適切でない治療法にのめりこまないために、吃音についての正しい知識を持つことは必要不可欠なことだと言える。
吃音の原因については、これまで無数と言えるほどの学説が出されたが、まだ定説はない。どんぐりを食べるとどもりになるといった迷信や、舌が短いからなどという説は姿を消したが、一般にはまださまざまな推測が残っている。ローマ時代、吃音は悪霊にとりつかれたために起こると言われ、19世紀に入ると、器質的要因や機能的要因が言われ、19世紀後半には精神科医らによって、神経症の一種と考えられるようになった。この頃、吃音の原因についての説を唱える人達は、自分の主張する説だけが吃音の原因であると考え、自説の正当性を主張し、他の学説を批判した。しかし、近年、吃音の原因は、吃音者ひとりひとり違っており、一つの原因説ですべての吃音者の原因を説明することはできないと考えられるようになった。吃音にはいくつかの原因があり、それらが重なり合っていると考えるようになったのである。
実際に臨床的に吃音者と接し、何らかの原因説をあてはめてみると、少なくともその人の吃音に関しては説明できることがあり、定説はないとはいえ、吃音研究者らが考えた原因説を知っておくことは意味のないことではないだろう。
» 三つの原因論
一般的に20世紀になって研究された吃音の原因論は、次の三つに大別できる。
素因論(本人の身体や遺伝的要因)
神経症説(本人の心理的不安や葛藤、自我の強さ)
学習説(周囲から与えられた刺激に対する反応として身につくもの)
1 素因論
1925年から1945年にかけて、主としてアメリカで、発吃が吃音者自身の身体的な機能や素質、遺伝などに関連しているのではないかと考えられ、盛んに研究された。その主なものを紹介する。
a 大脳半球優位説
人間の大脳半球は、左右いずれかの側がペースメーカーとして他方をリードする役割を持っている。言語機能は、この大脳半球の優位差がはっきりして、安定しているとき正常に働く(多くの人の場合、左半球が優位)。この両半球の優位性が乱れたり、優位差が少ないと言語機能に異常が起こり、吃音があらわれると説明する。両手利きに吃音者が多いとか、左利きを右利きに変えると吃るようになると言われ、一時大きな影響を与えたが、その後、眼、手、足を含む利き側の臨床的な研究で、吃音者と非吃音者との間に有意な差が見られないことが分かり、今では、この説はほとんど取り上げられていない。
吃る人の脳に何かがあるのではないかということは、依然研究が進められている。近い将来何かがわかるかも知れない。
b フィードバック理論
人間の脳は、自動制御装置と同じような原理で働いているという仮説を立て、ことばに応用したのがこの理論である。
非吃音者に自分の話し声を、発語より少し遅れて耳にフィードバックさせると、話すとき耳に入ってくる自分の声が邪魔になり、吃音とよく似た話し方になる。これを、フィードバック回路に故障が起こったと考え、吃音者が吃るのもフィードバック回路に異常があるのではないかと考えた。実際に、聴覚フィードバックの遅れがことばの混乱を引き起こすことは、数多くの研究でも明らかである。しかし、このように人工的に作られたことばの乱れと、吃音者の吃症状とは異質なものであるというニーリィの説は一般に受け入れられている。
c 遺伝的要因
吃音者は、女性より男性に多い。また、吃音の家系には吃音がやや多いという調査結果もある。これらをもとに吃音は遺伝的な要因を持つという説を唱える人はいる。しかし、ある特徴が家系に伝わるのは、習慣や生き方、教育、しつけなど社会的、環境的な要因によるものが大きいという反論があり、この反論がむしろ支持されている。
いわゆる遺伝については、今後もっと明らかになっていくだろうが、遺伝と言える根拠は薄い。
2 神経症説
吃るのは、その人が情緒的障害を持つからであり、自我が十分育たず、周囲の評価を気にする、不安定で自己認識が不確実な人格構造が原因だとする説である。吃音は情緒的な葛藤が基礎になっており、それが外にあらわれたにすぎないと考える。精神科医と心理学者の一部がこの説をとっている。精神科医がこの立場をとるには、それなりの理由がある。厳しい情緒的な問題を持つ吃音者が相談に訪れるのは、民間矯正所やセルフヘルプ・グループではなく、精神科医の所であろう。したがって、精神科医はそれらの厳しい情緒的問題を持つ吃音者と多く関わりを持つようになり、この説が捨て難いのだろうと推察はできる。
吃音者のパーソナリティに特徴的なパターンはあるのか、情緒的問題はあるのかなどについて、吃音者と非吃音者に差があるかないか、多くの研究がなされた。種々の心理テストや面接法によって比較検討がなされたが、吃音者に特徴的なパーソナリティパターンを見い出すことはできなかった。ただ、検査項目の中で「話すこと」に関連したものについては、神経症的、内向的傾向が見られた。これは、吃音者が本来持っているものというより、吃ることによって、後になってつけ加えられた二次的な特徴であると考えるのが一般的である。
しかし、吃音者の一部には、神経症の症状を持つ人、精神病理の立場から考えた方がいい人がいることは事実である。
3 学習説
吃音は「学習された行動」であるという説である。吃音は、聞き手と話し手の間に生じる緊張や葛藤や不安などと、ことばの獲得期の非流暢な話し方が結び合って身についていくものと考える。話し手が自分の吃音を意識するにつれ、話すことを恐れたり、話さなければならない場面を避けたりするようになる。話すことに対するむつかしさや恥ずかしさを予期する気持ちが重なり合って、それがさらに吃症状をひどくしていくというのである。
a 診断起因説
ウェンデル・ジョンソンは「吃音はこどもの口から始まるのではなく、親の耳から始まる」と言った。吃音といわれる子の、ことばを繰り返したり、引き伸ばしたりする話し方は、この頃の子ども(2、3歳)に共通した正常な範囲のことばのなめらかさの不足であるとし、その話し方に対して両親、特に母親が『どもり』というレッテルを貼ってしまう。そのレッテルを貼った後、つまり、『どもり』と診断した後から、どもりが起こると説明した。この説は、精神衛生上、好ましい親子関係を作ることの大切さを指摘し、子どもにどう接してよいかわからなかった親に、好ましい接し方を提示したことで、吃音児指導に大きな影響を与えた。しかし、親が誤ったレッテルを貼ったことが原因であるとは言いきれない。たとえば、親は全く意識していないという例は多く、原因論としては、そのままあてはまらない場合も少なくない。また、この説を安易に臨床的に応用すると、「どもりは母親が作った」ということになり、治らなかった場合、母親を責めることになり、母親を不必要に苦しめる恐れもある。
b フラストレーション説
ジョンソンの言う「吃音は親の耳から始まる」だけでなく、「子どもの耳から始まる」というものである。あることを伝えたい、思ったことをことばで表したい、話すことによって人を動かしたいという子どもの欲求は強い。しかし、ことばの発達途上にあって、自分の思うようにことばが繰れない、上手な聞き手が見当たらないなど、思ったこと、言いたいことを言えない条件がある。そのために、繰り返したり、引き伸ばしたりすることばの乱れが起こる。そのことばの乱れを自分の耳で聞き、異常さを意識する。その異常さに対しフラストレーションを感じるというのである。そのフラストレーションから、だんだんと吃音が発展していくという。フラストレーションは、吃音の原因としてだけではなく、吃音が次第に発展していく過程においても、大きな役割を担っていると言える。
c 吃音予期闘争説
話す前にうまく話せないと考え、そのために発語器官の筋肉が緊張し、話すことに躊躇する、つまり、話すことを妨げる行為から吃音が起こると考える。
ブルーメルは、子どもの吃音は、自覚も努力もない音の繰り返しや引き伸ばしで始まるとし、それを一次吃と名づけた。その繰り返しや引き伸ばしを注意されるたびに、うまく話そう、うまく話せないかもしれないという反応を示すようになり、そのような状態の吃音を二次吃と名づけ、吃音が予期闘争反応となるのは、この二次吃においてだと説明した。 一方、ジョンソンは、ブルーメルが一次吃と名づけたものは、正常な幼児のことばの非流暢性とあまり変わらないとし、子どもが予期闘争反応を示すようになるのは、子どものせいではなく、両親の、子どものことばに対する異常な反応にあると主張した。
シーアンは、二重接近-回避型の抗争として吃音を説明した。話したいという欲求と話したくないという欲求、黙っていたいという欲求と黙っているのが怖いという欲求が、相争うことによって吃音が起こると説明した。
これら吃音予期闘争説を唱える人々は、吃音の始まりや進展をこの説によって説明しようと試みているが、特定のこどもについての説明はできても、すべての吃音について十分説明できるとは言い難い。しかし、吃音を闘争または回避といった予期反応であるとし、それを支持する専門家は多い。
» 吃音の進展
ブルーメルは、吃り始めて間のない、軽くことばを繰り返すような吃音と、吃ることへの恐れや不安を持ち、慢性化し複雑化した成人の吃音とは明確に区別すべきだとして、一次吃、二次吃と名づけた。その後、ヴァン・ライパーは吃音の進展を次の4段階で区別した。
イ 第1段階
始まって間のない吃音は、主として力まない吃り方である。「タ、タ、タ、タマゴ」「タタ-マゴ」といったように、軽い音の繰り返しや引き伸ばしで、話すときにあまり力が入っていない。話すことへの不安や恐れはないし、フラストレーションを感じている様子はなく、話すときに意識はしていない。
ロ 第2段階
音の繰り返しや、ことばの引き伸ばしが徐々に変化してくる。「タ、タ、タ、タマゴ」と言っていたのが、「タ・・・・・タ・ターマーゴ」といったような言い方に変化する。この頃から、話すときに少し意識するようになる。
ハ 第3段階
ことばがつまり、いわゆる難発の状態になり、発語に際して緊張が生まれ、それが表情や身体にあらわれる。首を振る、手を振る、体を動かすなどの随伴運動が生じる。心理面では欲求不満が起こり、吃るのではないかという予期不安が起こってくる。
ニ 第4段階
難発の状態が一層激しくなり、ことばが出ない間隔が長くなり、頻度も多くなる。心理面では予期不安が一層大きくなり、恐怖が生じる。話すことを避ける回避行動もあらわれ、コミュニケーションに大きな障害となる。吃るかもしれないという不安と恐れで、話す場面に出ていけなくなる。そして、ますます不安や恐れが大きくなり、吃らずに話そうとすればするほど吃ってしまう悪循環に陥る。