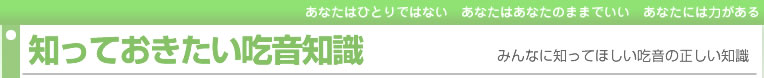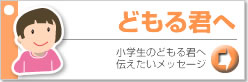慢性的吃症状症候群
『吃音とコミュニケーション』1988.1.20
伊藤伸二
「何百年もの間、吃音症状の頻度や重さが主要関心事であり、吃症状を治してしまうことが治療の目標になってきました。また、最近でも症状を治すことが治療だという考え方が復活してきました。吃る度合いを調べ、その数を減らすよう努力せよということですが、これが本当の意味で改善でしょうか…」
これは、1986年、第一回吃音問題研究国際大会の中のシンポジウムでのヴィヴィアン・M・シーアンの発言である。
1986年、ASHA(American Speech Hearing Association>の大会で、ユージーン・クーパー博士は、直らない吃音者、慢性的吃症状症候群について発表した。
「治療法が完全な流暢性を求めるのではなく、いかに楽に吃るかということに焦点をあててきた場合には、治らない吃音者がいるということ、つまり慢性的吃症状について指摘する必要はなかった。しかし、現在のように再び『吃音は治る』という唱い文句を掲げる治療が流行している時代にあっては慢性的吃症状について人々に知らしめ、研究を深める必要を強く感じている」
時を同じくし、シーアン、クーパー共に「吃音は治る、治す」という考え方が『復活』『再び流行』ということばを使って指摘し、それに対する危倶を述べている。
日本においても、吃音を持っていては決して楽しい有意義な人生は送れない。吃音者は、吃音を治したいという夢を捨ててはいけないし、研究者・臨床家も吃音を治すことをあきらめてはいけないという考えは根強く、今また出され始めている。
吃音問題解決には次の3つの方向がある。
(1)どもりが完全に治る
(2)自分が納得できるまでに軽くなる
(3)どもりに変化がなくても、どもりに左右されずに生きられる
果たして、全ての吃音者が望むであろう(1)の解決は現実的であろうか。
私たちが言友会20年の活動の中で知り得た範囲の経験や情報からすると、ほとんどの吃音者が治療を受けた、受けないにかかわらず、吃音は治っていない。だからといって吃音は治らないとは言い切れない。事実、かつて吃ったことがあるが、今は吃らないという人は大勢いる。しかし、その多くは、作家の藤沢周平さんのように「いつ、どうして治ったのかの記憶が全くありません。推定を言えば、中学の頃に級長になったりして、無理にも発言せざるを得ない立場に置かれ、次第に自信を持つようになったかと思われますが、確信はできません。いつのまにか治っていたという感じです」という人が多く、吃音を治したいと自分が努力して治したという人はそれほど多くはないように思う。吃音は治らないとは言い切れなくても(1)を目指すのは現在のところ、非現実的である。
(2)についてはどうだろうか。
結果としてこのような状態になることは可能である。言友会の中には、特別に吃音治療を受けた経験もなく、また努力をしなくても、日常生活を大切にし、吃っても話す生活を続けることによって、このような状態になった人は大勢いる。しかし、これも結果としてそうなったのであって、そのことに焦点をあて治療法を駆使し、努力して達成できるかとなると、疑問は残るし、問題もある。
(3)についてはどうだろうか。
言友会がここ10年主張し続けているのはこのアプローチである。
どもりは治る、治そうと考えるのではなく、クーパーの慢性的吃症状の特徴を見て、自分があてはまれば、自らを慢性的吃症状症候群と位置づけるのも一つの生き方だといえる。位置づけたからといって悲観する必要はない。クーパーも、治らないけれども、いい知らせはあると言っている。シーアンも、吃ってもどんどん話していけば道は開けると励ましている。
『吃音は治る、治す』が復活しつつある現在だからこそ、言友会の『吃音者宣言』は重要な意味を持つ。歴史の繰り返しにもう一度歯止めをかけるのは、一人一人の吃音者が、たとえ吃っていても自分らしく、より良く生きていく、その積み重ねだろう。